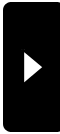「第5回新城市市民まちづくり集会」に行ってきた
11月27日、第5回新城市市民まちづくり集会が開催された。
私はブログでの書きっぷりからご存じのとおり「文句メイカー」を自負している。
何か言われればケチをつけたくなる性分で、およそ生産的な話し合いには向いていない。
この「まちづくり集会」では話し合いのルールとして、
・「批判しない」
・「ひとりだけでしゃべらない」
・「人の意見に耳を傾ける」
(・・・確かこんな内容だったと思う)
毎回この3つが説明される。
どれひとつとしてきっちり守れる自信がない。
とはいえ、文句メイカーの矜持として「自ら見聞きしたものに文句を言う」ことにしているからには「まちづくり集会」に参加しない事にはブログに書くことができない。
こういう時には「善人賢者モード」に自ら切り換えることにしている。
ウソの人格で話し合いに臨むワケで、もう会場に行く前から気が重い。
こんなことしなくちゃならないなら参加したくない、とさえ思う。全然楽しみじゃない。
ブツブツと心の中で文句を言いながら会場の出入り口に着くと、気重な私とは対照的に職員さんたちが明るく声をかけてくれる。
実にご苦労なことだ。こんな根暗な顔している(に違いない)おっさんにも丁寧に案内してくれる。ホント恐縮してしまう。
一応市民自治会議委員という肩書なので事前に参加案内を頂いていて、「参加します」と返事を出しておいた。
会場の新城文化会館大会議室の入り口には、事前に参加表明した市民とそうでない市民とに分かれて受付がなされていて、私は事前参加の方に行き受付を済まそうとした。
・・・のだが、ナントそこには私の名前が無い。
しかし「善人賢者モード」のワタクシ、こんな人を馬鹿にしたような仕打ちを受けても全く平気。
「オレは相変わらず企画部/まちづくり推進課から嫌われているなぁ。この前の市民自治会議でもメールで2度も質問送ったにも関わらず無視されたしなぁ。」と改めて感慨を深くした。
飛び入り参加というカタチで受付を済ませ、10番テーブルへ行くよう指示された。
今回のまちづくり集会では市議会議員さんがほぼ全員参加されたことがトピックとなっていたが、私のテーブルにはいなかった。
まぁ21もテーブルがあったのだから、議員さんがいないテーブルがあってもおかしくない。
今回のテーマは「女性(あなた)が未来(まち)を変える」
第1部は「活躍女子のお話」と題して、実際に市内外で活躍している女性やそのサポートをしている男性、行政や議会の立場からの話、などが発表された。
日本の社会における慣習的な女性の役割、すなわち「家事」「育児」「夫を支える」などの目線で見れば、第1部の活躍女子の話はその役割から自由であったり、克服している人、そしてそれを手助けする人であることがわかる。
しかし最近の考え方からいけば、「家事・育児」を「女性」だけが担う必要性は全くない。
「女性」と「男性」にそもそも能力差は無く、差があるとするなら生物学的に「子を産む能力があるか否か」に尽きるだろう。
という考えが新城市民にも割と広がっているように感じたのは、第2部のディスカッションの発表を聞いての事だ。
結果を出さず、「気付き」を求めるのがまちづくり集会のひとつのコンセプトだ。
テーマに沿って『「女性(あなた)が未来(まち)を変える」ために○○しよう』などという結論をまちづくり集会全体としては出すことは無い。
しかし参加した市民にとっては、話し合いの内容を何らかのカタチにしないと「一体私はナニをしにきたのか?」という実感が持てない恐れもある。
この辺り、まちづくり集会のあり方として矛盾を抱えているように感じる。
と、ひとつ問題提起。
さて、それで、その矛盾を克服する手段として、各テーブルごとでは「女性(あなた)が未来(まち)を変える」ためにどうしたらよいかを発表することになっていた。
そして先の「男女に能力差は無い」の話に戻るのだけど、この発表を聞いていると、各テーブルとも「そもそも女性とは?」的な話をしたんじゃないかと思われる印象を受けた。
男性が発表をしたテーブルではまだまだ「男は社会で、女は家庭で」的な考えが濃く臭うモノがあったが、多くのテーブルで「男女関係なく」を主語に置いた発表がなされ、新城市民は割と啓かれた考えを持っているのだなぁと感じた。
しかしここで「善人賢者モード」の私の中の「文句メイカー」がブツブツ言いだすのだ。
「結局、ここにいる人ってのはみんな「善人賢者モード」なんじゃねえの?」
最初に戻ると、このまちづくり集会は、『・「批判しない」』のだ。
そんな中であえて「オレは女は家庭を守るべきで社会に出る必要はないと思っている」とか言ったらどうなるか。
多分、場がシラケる。
そんなことを言わせまいと、テーマに沿った優等生的な意見が場を占めて、みんな「うんうん、そのとおりだねぇ」と善人的な意見でまとまるのだろう。
時間も限られているし、突っ込んだ意見や考えの応酬なんてのはどだいムリなのだ。
となれば、始めから世間で善とされている考えを軸にして、みんなの持ってる「善人賢者モード」で体よく話し合うフリをして「ああ、よく話し合ったねぇ(笑」と終えるのが、「新城市市民まちづくり集会」における全き善きプロトコールなのだ。
そうか、最後には割と楽しく話せたなぁと感じたのは、私の「善人賢者モード」が実はこの集会において最適解だったからなのだなぁ。
私はブログでの書きっぷりからご存じのとおり「文句メイカー」を自負している。
何か言われればケチをつけたくなる性分で、およそ生産的な話し合いには向いていない。
この「まちづくり集会」では話し合いのルールとして、
・「批判しない」
・「ひとりだけでしゃべらない」
・「人の意見に耳を傾ける」
(・・・確かこんな内容だったと思う)
毎回この3つが説明される。
どれひとつとしてきっちり守れる自信がない。
とはいえ、文句メイカーの矜持として「自ら見聞きしたものに文句を言う」ことにしているからには「まちづくり集会」に参加しない事にはブログに書くことができない。
こういう時には「善人賢者モード」に自ら切り換えることにしている。
ウソの人格で話し合いに臨むワケで、もう会場に行く前から気が重い。
こんなことしなくちゃならないなら参加したくない、とさえ思う。全然楽しみじゃない。
ブツブツと心の中で文句を言いながら会場の出入り口に着くと、気重な私とは対照的に職員さんたちが明るく声をかけてくれる。
実にご苦労なことだ。こんな根暗な顔している(に違いない)おっさんにも丁寧に案内してくれる。ホント恐縮してしまう。
一応市民自治会議委員という肩書なので事前に参加案内を頂いていて、「参加します」と返事を出しておいた。
会場の新城文化会館大会議室の入り口には、事前に参加表明した市民とそうでない市民とに分かれて受付がなされていて、私は事前参加の方に行き受付を済まそうとした。
・・・のだが、ナントそこには私の名前が無い。
しかし「善人賢者モード」のワタクシ、こんな人を馬鹿にしたような仕打ちを受けても全く平気。
「オレは相変わらず企画部/まちづくり推進課から嫌われているなぁ。この前の市民自治会議でもメールで2度も質問送ったにも関わらず無視されたしなぁ。」と改めて感慨を深くした。
飛び入り参加というカタチで受付を済ませ、10番テーブルへ行くよう指示された。
今回のまちづくり集会では市議会議員さんがほぼ全員参加されたことがトピックとなっていたが、私のテーブルにはいなかった。
まぁ21もテーブルがあったのだから、議員さんがいないテーブルがあってもおかしくない。
今回のテーマは「女性(あなた)が未来(まち)を変える」
第1部は「活躍女子のお話」と題して、実際に市内外で活躍している女性やそのサポートをしている男性、行政や議会の立場からの話、などが発表された。
日本の社会における慣習的な女性の役割、すなわち「家事」「育児」「夫を支える」などの目線で見れば、第1部の活躍女子の話はその役割から自由であったり、克服している人、そしてそれを手助けする人であることがわかる。
しかし最近の考え方からいけば、「家事・育児」を「女性」だけが担う必要性は全くない。
「女性」と「男性」にそもそも能力差は無く、差があるとするなら生物学的に「子を産む能力があるか否か」に尽きるだろう。
という考えが新城市民にも割と広がっているように感じたのは、第2部のディスカッションの発表を聞いての事だ。
結果を出さず、「気付き」を求めるのがまちづくり集会のひとつのコンセプトだ。
テーマに沿って『「女性(あなた)が未来(まち)を変える」ために○○しよう』などという結論をまちづくり集会全体としては出すことは無い。
しかし参加した市民にとっては、話し合いの内容を何らかのカタチにしないと「一体私はナニをしにきたのか?」という実感が持てない恐れもある。
この辺り、まちづくり集会のあり方として矛盾を抱えているように感じる。
と、ひとつ問題提起。
さて、それで、その矛盾を克服する手段として、各テーブルごとでは「女性(あなた)が未来(まち)を変える」ためにどうしたらよいかを発表することになっていた。
そして先の「男女に能力差は無い」の話に戻るのだけど、この発表を聞いていると、各テーブルとも「そもそも女性とは?」的な話をしたんじゃないかと思われる印象を受けた。
男性が発表をしたテーブルではまだまだ「男は社会で、女は家庭で」的な考えが濃く臭うモノがあったが、多くのテーブルで「男女関係なく」を主語に置いた発表がなされ、新城市民は割と啓かれた考えを持っているのだなぁと感じた。
しかしここで「善人賢者モード」の私の中の「文句メイカー」がブツブツ言いだすのだ。
「結局、ここにいる人ってのはみんな「善人賢者モード」なんじゃねえの?」
最初に戻ると、このまちづくり集会は、『・「批判しない」』のだ。
そんな中であえて「オレは女は家庭を守るべきで社会に出る必要はないと思っている」とか言ったらどうなるか。
多分、場がシラケる。
そんなことを言わせまいと、テーマに沿った優等生的な意見が場を占めて、みんな「うんうん、そのとおりだねぇ」と善人的な意見でまとまるのだろう。
時間も限られているし、突っ込んだ意見や考えの応酬なんてのはどだいムリなのだ。
となれば、始めから世間で善とされている考えを軸にして、みんなの持ってる「善人賢者モード」で体よく話し合うフリをして「ああ、よく話し合ったねぇ(笑」と終えるのが、「新城市市民まちづくり集会」における全き善きプロトコールなのだ。
そうか、最後には割と楽しく話せたなぁと感じたのは、私の「善人賢者モード」が実はこの集会において最適解だったからなのだなぁ。
2016年12月04日 Posted by けま at 02:25 │Comments(0) │まちづくり集会
第3回市民自治会議 2
この前の第3回市民自治会議の続き。
最初に、1・地域産業総合振興条例策定事業について
パブリックコメントには7名19件の意見が寄せられた。
会議は10月28日開催、すでにパブコメは締め切られ自治会議での話し合いも終わっているが、いまだに市のHPへの掲載はなし。
会議では市のHPにおいて市民への公開は約束されたが、この遅さはどうだろう。
まぁ忙しいのだろうけど、いつも言うように情報開示のスピードが遅い。
このパブコメは実際にすべての意見を見てもらうのが一番よいのだけれども、ひとつ挙げてみる。
自分も意見したことなのだが、同じように自治委員の中でも意見した方がいて、同じところに着目しているところに心強さを覚えた。
それは、条例素案の第6条に市民の役割として「事業者が提供する商品及びサービスに関心を深め、購入するよう努めること」という条文。
この条文の「強制するような表現」と「その強制を条例化する危うさ」が指摘され、委員の間で大きな懸念が示された。
ここの表現はこの条例素案を策定した委員さんたちでも大きく議論されたところらしい。
市民にも参加協同意識を持ってほしい、という意気込みの表れとしてこういう表現になったということだが、決して強制するものではないと説明者は言っていた。
が、表現の裏にそのような「隠れた考え」がある条文は問題だと思うのだ。
いったん条例化されればこの条文はこの先ずっと残る。
この「隠れた考え」をわかっている人が死に絶えても条文は残る。
そして未来に「隠れた考え」を知らない人がこの条文を条文だけで解釈して、市民に「地元のモノを買え。買わなければ条例違反だ。」とか言い出したらどうなるか。
大袈裟に考えすぎかもしれないが、条例つまり法律とはそういうものだろう。
条例があるおかげで未来を守ることもできる。例えば環境保全条例などは未来に予想される環境汚染を防ぐためのものだ。
でも条文が拙ければ裏の意図など忘れ去られ、条文の拙さゆえに時の権力者にいいように解釈されて結局市民を苦しめることにもなる。
この条例素案第6条は自治会議委員によって強く懸念が示された。よくよく再考されて、条例文を工夫してほしい。
次は、3・集会を妨げる事態等への対応について
持論であった「ヤジ対策(「ヤジについて」http://kemanomake.dosugoi.net/e797458.html)」を意見してみたが、なんというか一笑に付された感じだった(笑
まぁ、そうだろうなと思いつつ後は黙って皆さんの意見を聞いていた。
私の意見を受けて、とある委員さんが「驚くべき性善説(私の持論のコト)で云々」と語りだしたのが「ヤジは絶対イカン」という御意見。
福井県高浜町の原発説明会を例に出して、「運動員などの猛烈なヤジや反対意見で説明会どころではなくなり、結果的に一番に説明を受けなければならない市民が怖がって参加しなくなってしまった」と言われた。
これには議長の鈴木先生も言及されて、この第3回まちづくり集会の時でも(この時鈴木先生は壇上でコーディネーターを任されていた)「警察には連絡を入れてくれてますか?」と訊ねていたと言われた。
高浜町のような、集会を妨害するような激しい行為があることをかなり本気に危惧していたらしい。
ヤジに代表されるような、集会を妨害する行為はとにかく御法度、というのが通例らしいのだな。
私はヤジを飛ばしていた「守る会」の皆さんの気持ちもよく理解できるのだが、あの場には「善良な市民」も多くいたわけで、やはり「大きな声でヤジる」という行為がその「善良な子羊のような市民」に大きな恐怖を与えたであろうことも想像できる。
まちづくり集会でのヤジの第一発目は選択肢2の説明をしてた人が、選択肢2に不利に働く私見を述べたところから始まった。
このことは最初に持論を意見した時に言及した。
鈴木先生はこのことを受けてくれたのだろうと思うのだが「例えヤジにつながる発言があったとしても、集会はそういうのも含めて進行されなくてはならない。その発言がきっかけのヤジだとしてもヤジに良いも悪いもなく云々」というようなことも言われた。
あの集会が討論会なら失言もアリ、というのはわかる。
しかしあの集会は「情報を共有する会」だったはずで、賛成も反対もしないのが約束だった。
どちらかの選択肢を誘導するような私見を述べたら、それはもう「情報を共有する会」ではなく「討論会」というのがふさわしいだろう。
意見を述べ合うのが討論会なのだから、壇上で私見を言うのが許されてしまった時になぜ客席で黙っていなくてはならないのか。
互いに壇上に立たなければ「公平公正」ではないだろう。
と、あの時に言えたら・・・。
これは今思いついて書いていて、自分の「その場のディベート力」の不甲斐なさに情けなくなる。
結局のところ集会の妨害行為に対しては、集会の企画とはまた別に、妨害行為対策を考えることも必要だろうという結論になった。
「まちづくり集会」は「まちづくり集会実行委員」に企画運営がすべて任されているが、今度からこのような対立がある事柄を集会で企画するときには妨害行為対策も同時に実行委員会の方で話し合われることになるのだろう。
しかしなぁ、ヤジとか妨害行為の恐れがあるのなら、市民とかが集会に集まる意味ってなんなのだろうって思ってしまう。
その場に足を運ぶ意味っていうのかな。
こんだけインターネットが発達してくれば、集会なんて直に参加しないで中継にして、パソコンで市民参加でもいいんじゃないか?
実際ネットで生中継って行われているし。
チャットでその場でどんどん意見してもらったりして、それをサブ画面に流したり。ニコ動みたく画面に意見が流れるのもおもしろいかもなぁ。
というわけで第3回市民自治会議は終了。
次回は12月8日の予定。
最初に、1・地域産業総合振興条例策定事業について
パブリックコメントには7名19件の意見が寄せられた。
会議は10月28日開催、すでにパブコメは締め切られ自治会議での話し合いも終わっているが、いまだに市のHPへの掲載はなし。
会議では市のHPにおいて市民への公開は約束されたが、この遅さはどうだろう。
まぁ忙しいのだろうけど、いつも言うように情報開示のスピードが遅い。
このパブコメは実際にすべての意見を見てもらうのが一番よいのだけれども、ひとつ挙げてみる。
自分も意見したことなのだが、同じように自治委員の中でも意見した方がいて、同じところに着目しているところに心強さを覚えた。
それは、条例素案の第6条に市民の役割として「事業者が提供する商品及びサービスに関心を深め、購入するよう努めること」という条文。
この条文の「強制するような表現」と「その強制を条例化する危うさ」が指摘され、委員の間で大きな懸念が示された。
ここの表現はこの条例素案を策定した委員さんたちでも大きく議論されたところらしい。
市民にも参加協同意識を持ってほしい、という意気込みの表れとしてこういう表現になったということだが、決して強制するものではないと説明者は言っていた。
が、表現の裏にそのような「隠れた考え」がある条文は問題だと思うのだ。
いったん条例化されればこの条文はこの先ずっと残る。
この「隠れた考え」をわかっている人が死に絶えても条文は残る。
そして未来に「隠れた考え」を知らない人がこの条文を条文だけで解釈して、市民に「地元のモノを買え。買わなければ条例違反だ。」とか言い出したらどうなるか。
大袈裟に考えすぎかもしれないが、条例つまり法律とはそういうものだろう。
条例があるおかげで未来を守ることもできる。例えば環境保全条例などは未来に予想される環境汚染を防ぐためのものだ。
でも条文が拙ければ裏の意図など忘れ去られ、条文の拙さゆえに時の権力者にいいように解釈されて結局市民を苦しめることにもなる。
この条例素案第6条は自治会議委員によって強く懸念が示された。よくよく再考されて、条例文を工夫してほしい。
次は、3・集会を妨げる事態等への対応について
持論であった「ヤジ対策(「ヤジについて」http://kemanomake.dosugoi.net/e797458.html)」を意見してみたが、なんというか一笑に付された感じだった(笑
まぁ、そうだろうなと思いつつ後は黙って皆さんの意見を聞いていた。
私の意見を受けて、とある委員さんが「驚くべき性善説(私の持論のコト)で云々」と語りだしたのが「ヤジは絶対イカン」という御意見。
福井県高浜町の原発説明会を例に出して、「運動員などの猛烈なヤジや反対意見で説明会どころではなくなり、結果的に一番に説明を受けなければならない市民が怖がって参加しなくなってしまった」と言われた。
これには議長の鈴木先生も言及されて、この第3回まちづくり集会の時でも(この時鈴木先生は壇上でコーディネーターを任されていた)「警察には連絡を入れてくれてますか?」と訊ねていたと言われた。
高浜町のような、集会を妨害するような激しい行為があることをかなり本気に危惧していたらしい。
ヤジに代表されるような、集会を妨害する行為はとにかく御法度、というのが通例らしいのだな。
私はヤジを飛ばしていた「守る会」の皆さんの気持ちもよく理解できるのだが、あの場には「善良な市民」も多くいたわけで、やはり「大きな声でヤジる」という行為がその「善良な子羊のような市民」に大きな恐怖を与えたであろうことも想像できる。
まちづくり集会でのヤジの第一発目は選択肢2の説明をしてた人が、選択肢2に不利に働く私見を述べたところから始まった。
このことは最初に持論を意見した時に言及した。
鈴木先生はこのことを受けてくれたのだろうと思うのだが「例えヤジにつながる発言があったとしても、集会はそういうのも含めて進行されなくてはならない。その発言がきっかけのヤジだとしてもヤジに良いも悪いもなく云々」というようなことも言われた。
あの集会が討論会なら失言もアリ、というのはわかる。
しかしあの集会は「情報を共有する会」だったはずで、賛成も反対もしないのが約束だった。
どちらかの選択肢を誘導するような私見を述べたら、それはもう「情報を共有する会」ではなく「討論会」というのがふさわしいだろう。
意見を述べ合うのが討論会なのだから、壇上で私見を言うのが許されてしまった時になぜ客席で黙っていなくてはならないのか。
互いに壇上に立たなければ「公平公正」ではないだろう。
と、あの時に言えたら・・・。
これは今思いついて書いていて、自分の「その場のディベート力」の不甲斐なさに情けなくなる。
結局のところ集会の妨害行為に対しては、集会の企画とはまた別に、妨害行為対策を考えることも必要だろうという結論になった。
「まちづくり集会」は「まちづくり集会実行委員」に企画運営がすべて任されているが、今度からこのような対立がある事柄を集会で企画するときには妨害行為対策も同時に実行委員会の方で話し合われることになるのだろう。
しかしなぁ、ヤジとか妨害行為の恐れがあるのなら、市民とかが集会に集まる意味ってなんなのだろうって思ってしまう。
その場に足を運ぶ意味っていうのかな。
こんだけインターネットが発達してくれば、集会なんて直に参加しないで中継にして、パソコンで市民参加でもいいんじゃないか?
実際ネットで生中継って行われているし。
チャットでその場でどんどん意見してもらったりして、それをサブ画面に流したり。ニコ動みたく画面に意見が流れるのもおもしろいかもなぁ。
というわけで第3回市民自治会議は終了。
次回は12月8日の予定。
2015年11月11日 Posted by けま at 12:04 │Comments(0) │まちづくり集会
ただの言い訳
昨日まちづくり集会実行委員会があって傍聴させてもらった。
話し合いは活気に満ちて、委員さんたちが皆積極的に意見を述べ、それがだんだんと一つのカタチに集約されていく様を見ることはとても楽しかった。
傍聴の規定で私は何も意見はできないのだけれども、思わず小さな声で独り言を呟いてしまうような、実にワクワクするような話し合いだった。
正式な発表は近いうちに実行委員会の方からあるだろうから、ここでは具体的なことは触れないでおこう。
漠然としか書けないが、未来に視線を向けたポジティブな内容だ。
楽しく傍聴させてもらいながら、もうひとつ思ったのは新城南部の産廃問題だ。
本当はこの産廃問題を、今話し合われているこの実行委員会で議題として提案できないか?と思っていた。
傍聴規定で私は発言できないことは分かっていたけれども。
提案できないか?と言っておきながら、恥ずかしいことに未だに産廃会議には参加できていない。
その産廃会議、どういう雰囲気でおこなわれているのだろうか。
産廃問題の解決に精力的に尽力しておられる山本拓哉氏の10月23日付ブログでは、
「本当は、欠格事項を摘発して一発不許可で皆でビールかけ!っと願っていましたが、どうも今の法律には不許可にする条項が無いようで、仕方ありません。不戦の戦いで勝利するしかないようです。」
と書かれていた。
長期的な戦いを余儀なくされ、その相手は直接的にはタナカ興業、間接的には市長に行政。
明るい、というかあまり盛り上がる雰囲気ではなさそうな、そんな感じの会議なのだろうか。
想像でしか言えないんだけど・・・。
その想像の範囲でしか言えないのだが、同じ新城市民が行っている会議なのにこの雰囲気の違いはどうだろう?
私には市民にとってとても不幸な状況に見えて仕方ない。
市民誰もが、市の未来を明るく語れるそういう会議を持ちたい。
この前参加させてもらった地域報告会でもいくつか問題は指摘されたが、それらは解決されれば地域の生活がプラスに転化するものが多かった。
(例えばこども園駐車場が夜は真っ暗だ、という問題。外灯が設置されれば安全度が増す、というような。)
しかし産廃問題は、業者が操業すれば今の生活がマイナスになるだけ。
業者が操業しなくて地域の住民が得られることは「今の生活が維持されるだけ」で、プラスの要素は無い。
先にプラスのことが見えない戦いのための会議を、ずっと続けなくてはならない気持ちはいかばかりか。
私に何ができるのか。もう少し拡張すれば、同じ新城市に住む人として何ができるのだろうか。
実効的なことはさておき、すぐに実行できて一番大切なのは「知ること」「知っておくこと」ではないか。
産廃問題、まずは状況を知っておこう。
産廃会議に出てみる(次回は11月1日と言ってました。10月25日には渥美文化会館でも開催されます)とか、
先ほど引用させてもらった山本拓哉氏のブログ(http://takuya-y.jugem.jp/)、
facebookの「新城の環境を考える市民の会」(https://www.facebook.com/shinshiro.sanpai/photos_stream)とかを見るといいと思う。
その上で、みんなが自分で考えて賛成か反対か態度を決めればいい。
今回のまちづくり集会実行委員会は、「知ってもらう」ための良い機会だった。
が、それができなかったオレ。
「できなかった」という言い方が言い訳がましい。それをしなかったオレ、だ。
明るく活気に満ちた会議に冷や水をぶっかけることができなかった。
「ぶっかけられない最低なヤツだ」が、ぶっかけても最低なヤツだろう。
悪者になりきれない偽善だらけの卑怯者の根性なしはわかっていたが、再度自覚した。
でもブログは続けていこう。恥をさらし続けて市の問題を考えていこう。
話し合いは活気に満ちて、委員さんたちが皆積極的に意見を述べ、それがだんだんと一つのカタチに集約されていく様を見ることはとても楽しかった。
傍聴の規定で私は何も意見はできないのだけれども、思わず小さな声で独り言を呟いてしまうような、実にワクワクするような話し合いだった。
正式な発表は近いうちに実行委員会の方からあるだろうから、ここでは具体的なことは触れないでおこう。
漠然としか書けないが、未来に視線を向けたポジティブな内容だ。
楽しく傍聴させてもらいながら、もうひとつ思ったのは新城南部の産廃問題だ。
本当はこの産廃問題を、今話し合われているこの実行委員会で議題として提案できないか?と思っていた。
傍聴規定で私は発言できないことは分かっていたけれども。
提案できないか?と言っておきながら、恥ずかしいことに未だに産廃会議には参加できていない。
その産廃会議、どういう雰囲気でおこなわれているのだろうか。
産廃問題の解決に精力的に尽力しておられる山本拓哉氏の10月23日付ブログでは、
「本当は、欠格事項を摘発して一発不許可で皆でビールかけ!っと願っていましたが、どうも今の法律には不許可にする条項が無いようで、仕方ありません。不戦の戦いで勝利するしかないようです。」
と書かれていた。
長期的な戦いを余儀なくされ、その相手は直接的にはタナカ興業、間接的には市長に行政。
明るい、というかあまり盛り上がる雰囲気ではなさそうな、そんな感じの会議なのだろうか。
想像でしか言えないんだけど・・・。
その想像の範囲でしか言えないのだが、同じ新城市民が行っている会議なのにこの雰囲気の違いはどうだろう?
私には市民にとってとても不幸な状況に見えて仕方ない。
市民誰もが、市の未来を明るく語れるそういう会議を持ちたい。
この前参加させてもらった地域報告会でもいくつか問題は指摘されたが、それらは解決されれば地域の生活がプラスに転化するものが多かった。
(例えばこども園駐車場が夜は真っ暗だ、という問題。外灯が設置されれば安全度が増す、というような。)
しかし産廃問題は、業者が操業すれば今の生活がマイナスになるだけ。
業者が操業しなくて地域の住民が得られることは「今の生活が維持されるだけ」で、プラスの要素は無い。
先にプラスのことが見えない戦いのための会議を、ずっと続けなくてはならない気持ちはいかばかりか。
私に何ができるのか。もう少し拡張すれば、同じ新城市に住む人として何ができるのだろうか。
実効的なことはさておき、すぐに実行できて一番大切なのは「知ること」「知っておくこと」ではないか。
産廃問題、まずは状況を知っておこう。
産廃会議に出てみる(次回は11月1日と言ってました。10月25日には渥美文化会館でも開催されます)とか、
先ほど引用させてもらった山本拓哉氏のブログ(http://takuya-y.jugem.jp/)、
facebookの「新城の環境を考える市民の会」(https://www.facebook.com/shinshiro.sanpai/photos_stream)とかを見るといいと思う。
その上で、みんなが自分で考えて賛成か反対か態度を決めればいい。
今回のまちづくり集会実行委員会は、「知ってもらう」ための良い機会だった。
が、それができなかったオレ。
「できなかった」という言い方が言い訳がましい。それをしなかったオレ、だ。
明るく活気に満ちた会議に冷や水をぶっかけることができなかった。
「ぶっかけられない最低なヤツだ」が、ぶっかけても最低なヤツだろう。
悪者になりきれない偽善だらけの卑怯者の根性なしはわかっていたが、再度自覚した。
でもブログは続けていこう。恥をさらし続けて市の問題を考えていこう。
2015年10月23日 Posted by けま at 08:16 │Comments(0) │まちづくり集会│産廃問題
第2回市民自治会議 2
第2回市民自治会議、2つめの議題は「市民まちづくり集会について」。
資料として第1回、第2回のまちづくり集会のパンフレットをもらったので、その時の議題を見てみると。
第1回(平成25年8月25日)
・第1部 新庁舎建設
・第2部 新城の未来を語る
第2回(平成26年10月19日)
・第1部 若者の主張!私たちの考えるまち
・第2部 皆で話そう!グループディスカッション(若者が住みたいまちについて)
これからの新城をどのようにしていこうか?、ポジティブシンキングでいこう! という感じだろうか。
辛気臭い議題より未来に希望がもてる方がいいだろうな、とは思う。
「市民まちづくり集会」は新城市自治基本条例の第15条に規定されている。
その第1項にはこう書いてある。
「市長又は議会は、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政が、ともに力を合わせてより良い地域を創造していくことを目指して、意見を交換し情報及び意識の共有を図るため、3者が一堂に会する市民まちづくり集会を開催します。」
第3回の市民まちづくり集会は住民投票に伴い行われたもので、わかりにくいとされた選択肢の「情報及び意識の共有を図るため」という目的が重視された。
選択肢を選ばなくはならない前提があるため、「どちらが良いのか?」という視点を拭い去れない。
どうしても選んだ先の優劣(市民一人ひとりにとっての、だが)が気になる。
穏やかに平和的に「情報及び意識の共有を図る」のが非常に難しかった、という事務方の説明は同情的に理解できた。
第1回、第2回ではなかったヤジも第3回では多く飛び、「荒れた第3回」という印象は委員の多くが持っていたようで、このようなまちづくり集会にはしたくなかった気持ちはわかる。
私もこのブログで第3回まちづくり集会の総括をしていたので、そこで考え至った事を意見してみた。
ひとつは、「市民が本当に欲していた情報を提供することができたのか、まちづくり集会実行委員会は反省が必要ではないか?」ということ。
この場に実行委員会の人がいれば「市民が本当に欲していた情報を提供することができたのか?」、
と聞いてみたかったのだけれども、いなかったので提案みたいな感じの言い方になって歯切れが悪かった(笑
聞き方によっては「実行委員会が悪い」みたいな感じの言い方になるのだが、やはりそう捉える委員もいて、「悪者さがしをしても仕方がないので先に繋がる意見を云々」みたいな意見もでた。
まぁ、そう取られても仕方ない。
人がやってることだから、「実行された事柄」に反省を求めれば、「実行された事柄」に関わった人を悪く言ってしまうカタチになるのは仕方ない。
私も「悪者を特定して、はい反省終了!」などとは全く考えてなく、実行委員会の方で提供しようとした情報と、市民が本当に欲していた情報をどう一致させたらよいか、そこを考えていくべきだろうという事をわかってもらいたかったのだけれども。
さてもうひとつは、「議会が決めた条例なのだから質疑応答など、議会が答えるべきところは多かったように思うが、なぜそうしなかったのか?」ということ。
これは事務方から色んな説明を受けた。 実はまだよくわかっていない。
まずは議会には「議決権」しかない、ということ。
今回のまちづくり集会は条例に基づいて開催されたもので、いわゆる「執行権」を持ったまちづくり実行委員会が執り行ったもの。
「執行権」のない議会がまちづくり集会で説明することはできない・・・的な説明だったように記憶している。間違っていたらすいません。個人的によく勉強したいところです。
選択肢がおかしいとかわかりにくいとか、いろいろ問題点の山積みな事柄だったわけだから、実行委員会は「こんな選択肢を説明しなくてはならないまちづくり集会はやりたくない、やれない」と拒否をしたらどうだろう?とも聞いてみたのだが、これも条例で開催が決められている以上は執行権を持つまちづくり集会がやらなくてはならなかった、と説明を受けた。
それはつまり、「どんなにくだらない条例でも議決した以上は執行されなければならない」ということだ、とも言われた。
議決の結果執行されるに至ったくだらない条例は、執行する機関に無理を背負わせることになる。
しかし議会は「議決権」しかないことを理由に、その条例を説明する責任は無い、と、こういう事らしいのだ。
「これは議会が一番悪いですね。決めるだけ決めといてあとは知りません、ってアリなんですか?」
と、かねてから思っていたことも含めて言ったら、実にその通りとばかりに事務方もうなずいていた(笑
事務方のような行政の立場としては議会の議決にはなかなかモノが言いにくいらしい。
しかし・・・、議会がこのようなどうしようもない条例を作ったとして、これにダメ出しするにはどうしたらいいのか?
それがどうもこれといった手だてが無いらしいのだ。
もちろん地方自治法における議員のリコールという手段はあるが、「辞めさせる」のもちょっとイキすぎな感じがするし・・・。。
なにしろ「条例」は一度決まればやるほかないのが定めだ。今回の住民投票でそれがよっくわかった。
今回の住民投票では大多数の議員が選択肢1を推していたが、結果は選択肢2が多く得票した。
民意を汲み取れなかった議員に反省を求める声が議会内で出ているが、そういう反省は表に出てきていない。
議員にも個人としての信念があるだろうから、必ずしも民意に沿わなくてはならないこともないだろうと、私個人としては思う。
それよりも、今回の住民投票のように「道路変更が新庁舎建設とどう結びつくのか、説明しないとわからない」ようなわかりにくい条例を作ってしまったことに議会としての反省を求めたい。
市民はもちろん、執行しなければならなかった実行委員会にも相当な負担をかけたことの重みをわかってほしい。
議員提案にしろ、市から出た提案にしろ、審議には十分な時間をかけてその提案の及ぶ範囲を十分考慮してほしい。
そういう重大な仕事をしているのだという今一度考えてほしいものだ。
資料として第1回、第2回のまちづくり集会のパンフレットをもらったので、その時の議題を見てみると。
第1回(平成25年8月25日)
・第1部 新庁舎建設
・第2部 新城の未来を語る
第2回(平成26年10月19日)
・第1部 若者の主張!私たちの考えるまち
・第2部 皆で話そう!グループディスカッション(若者が住みたいまちについて)
これからの新城をどのようにしていこうか?、ポジティブシンキングでいこう! という感じだろうか。
辛気臭い議題より未来に希望がもてる方がいいだろうな、とは思う。
「市民まちづくり集会」は新城市自治基本条例の第15条に規定されている。
その第1項にはこう書いてある。
「市長又は議会は、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政が、ともに力を合わせてより良い地域を創造していくことを目指して、意見を交換し情報及び意識の共有を図るため、3者が一堂に会する市民まちづくり集会を開催します。」
第3回の市民まちづくり集会は住民投票に伴い行われたもので、わかりにくいとされた選択肢の「情報及び意識の共有を図るため」という目的が重視された。
選択肢を選ばなくはならない前提があるため、「どちらが良いのか?」という視点を拭い去れない。
どうしても選んだ先の優劣(市民一人ひとりにとっての、だが)が気になる。
穏やかに平和的に「情報及び意識の共有を図る」のが非常に難しかった、という事務方の説明は同情的に理解できた。
第1回、第2回ではなかったヤジも第3回では多く飛び、「荒れた第3回」という印象は委員の多くが持っていたようで、このようなまちづくり集会にはしたくなかった気持ちはわかる。
私もこのブログで第3回まちづくり集会の総括をしていたので、そこで考え至った事を意見してみた。
ひとつは、「市民が本当に欲していた情報を提供することができたのか、まちづくり集会実行委員会は反省が必要ではないか?」ということ。
この場に実行委員会の人がいれば「市民が本当に欲していた情報を提供することができたのか?」、
と聞いてみたかったのだけれども、いなかったので提案みたいな感じの言い方になって歯切れが悪かった(笑
聞き方によっては「実行委員会が悪い」みたいな感じの言い方になるのだが、やはりそう捉える委員もいて、「悪者さがしをしても仕方がないので先に繋がる意見を云々」みたいな意見もでた。
まぁ、そう取られても仕方ない。
人がやってることだから、「実行された事柄」に反省を求めれば、「実行された事柄」に関わった人を悪く言ってしまうカタチになるのは仕方ない。
私も「悪者を特定して、はい反省終了!」などとは全く考えてなく、実行委員会の方で提供しようとした情報と、市民が本当に欲していた情報をどう一致させたらよいか、そこを考えていくべきだろうという事をわかってもらいたかったのだけれども。
さてもうひとつは、「議会が決めた条例なのだから質疑応答など、議会が答えるべきところは多かったように思うが、なぜそうしなかったのか?」ということ。
これは事務方から色んな説明を受けた。 実はまだよくわかっていない。
まずは議会には「議決権」しかない、ということ。
今回のまちづくり集会は条例に基づいて開催されたもので、いわゆる「執行権」を持ったまちづくり実行委員会が執り行ったもの。
「執行権」のない議会がまちづくり集会で説明することはできない・・・的な説明だったように記憶している。間違っていたらすいません。個人的によく勉強したいところです。
選択肢がおかしいとかわかりにくいとか、いろいろ問題点の山積みな事柄だったわけだから、実行委員会は「こんな選択肢を説明しなくてはならないまちづくり集会はやりたくない、やれない」と拒否をしたらどうだろう?とも聞いてみたのだが、これも条例で開催が決められている以上は執行権を持つまちづくり集会がやらなくてはならなかった、と説明を受けた。
それはつまり、「どんなにくだらない条例でも議決した以上は執行されなければならない」ということだ、とも言われた。
議決の結果執行されるに至ったくだらない条例は、執行する機関に無理を背負わせることになる。
しかし議会は「議決権」しかないことを理由に、その条例を説明する責任は無い、と、こういう事らしいのだ。
「これは議会が一番悪いですね。決めるだけ決めといてあとは知りません、ってアリなんですか?」
と、かねてから思っていたことも含めて言ったら、実にその通りとばかりに事務方もうなずいていた(笑
事務方のような行政の立場としては議会の議決にはなかなかモノが言いにくいらしい。
しかし・・・、議会がこのようなどうしようもない条例を作ったとして、これにダメ出しするにはどうしたらいいのか?
それがどうもこれといった手だてが無いらしいのだ。
もちろん地方自治法における議員のリコールという手段はあるが、「辞めさせる」のもちょっとイキすぎな感じがするし・・・。。
なにしろ「条例」は一度決まればやるほかないのが定めだ。今回の住民投票でそれがよっくわかった。
今回の住民投票では大多数の議員が選択肢1を推していたが、結果は選択肢2が多く得票した。
民意を汲み取れなかった議員に反省を求める声が議会内で出ているが、そういう反省は表に出てきていない。
議員にも個人としての信念があるだろうから、必ずしも民意に沿わなくてはならないこともないだろうと、私個人としては思う。
それよりも、今回の住民投票のように「道路変更が新庁舎建設とどう結びつくのか、説明しないとわからない」ようなわかりにくい条例を作ってしまったことに議会としての反省を求めたい。
市民はもちろん、執行しなければならなかった実行委員会にも相当な負担をかけたことの重みをわかってほしい。
議員提案にしろ、市から出た提案にしろ、審議には十分な時間をかけてその提案の及ぶ範囲を十分考慮してほしい。
そういう重大な仕事をしているのだという今一度考えてほしいものだ。
2015年10月03日 Posted by けま at 08:43 │Comments(0) │まちづくり集会
ヤジについて
まちづくり集会冒頭での注事事項で、「会場からの発言はお控えください」とあった。
会場からの発言、いわゆるヤジは明らかにルール違反だ。
今年度第1回の市民自治会議ではこのヤジに大きな不満を持った委員さんがいて、
「ヤジを発した本人を特定して、今後出入りを禁止させてはどうか」などと言っていた。
サッカーJリーグの浦和レッズサポーターがやった差別的行為に対する措置を例にしたみたいだ。
ちょいと本旨からズレるかもしれないけど、本人にはどうしようもないコトで区別されることを「差別」と言い、今の世の中、そして特にサッカー界では差別行為に対して厳しい態度が取られているね。
ヤジは差別行為か? 「ヤジ=差別」ゆえにまちづくり集会から排除されるべき、か?
これはおかしいね。
確かにルール違反だけれども、その対処としてサッカーの事例を持ってくるのは違うだろう。
ヤジは、言ってみれば自由な発言で、その会場から排除して発言する機会を奪い去ることは、ヤジを言う人の自由を制限することになり、こっちの方がむしろ差別行為になるだろう。
とは言っても会場からデカい声で喚かれては、壇上で正当な機会を得て発言している人の邪魔になり、よろしくない。
厳しい処罰を用意するのではなく、参加者皆が紳士的にルールを守るのが一番理想なのだが・・・。
こういう問題は知恵を使ってウマく解決したいものだ。
まず、そもそもなぜヤジがとぶのか?
始めから妨害目的なら、まちづくり集会の開催直後から盛んにヤジをとばせばいいはずだが、今回のまちづくり集会では最初からしばらくの間は会場は静かだったのだ。
ヤジが初めて確認できたのは、選択肢2の説明の時だ。
説明していた山本一昭氏が「庁舎が道路を挟んで分かれているため、市民や職員の移動安全上効率上、問題になります」と言ったときヤジがとんだ。
ちなみにDVDで41分45秒ぐらいのときだ。
「問題になります」という言い方は、“悪いこと”“ネガティブ”なイメージがある。
ここに敏感に反応したのだろう。
「選択肢2はよくない」というミスリードは両選択肢にとって公平では無い。
このヤジのタイミングは注目すべきだ。
すなわち、ヤジを発した人は発言者の言う事をよく聞いてくれているのだ。
よく聞き、その発言に対して即座に「おかしい!」と感じたからこそ、「ヤジ」と言うより「率直な意見」が放たれたのではあるまいか。
本当はその発言の内容を知りたいところだが、DVDではよく確認できなかった。
ひょっとしたら「バカヤロー」的なただの罵声だったかもしれない。罵声ではちょっといただけないかな。
あの大きな会場で、今まで静かだった状態で、いきなり大きな声を出せば大きな注目を浴びることは間違いない。
これはかなり恥ずかしい。勇気のいることだ。
実際、41分45秒の初めてのヤジ以降は盛んにヤジがとんだ。誰かがひとり言ってくれれば後に続きやすいものだ。
タイミングのよい、最初のヤジは、実は貴重な発言でもある、と言えないだろうか。
ここからは妄想なのだが、会場に係りの者を多数配置しておき、ヤジを最初に言った人を素早く見つける体制を作っておく。
ヤジを言った人を特定できたら、その人に3分間のスピーチタイムを与える。
会場の一般市民からの正式な発言として記録するし、壇上の人も会場の人たちも皆傾聴する。
終わった後は拍手でその発言の良し悪しを判定する。
くだらない、まさに「ヤジ」でしかない発言なら遠慮なくブーイングする。
壇上の発言に対する鋭い発言なら大喝采する。
しかし会場からの発言は原則的にはルール違反だから、以降は静かにしていてもらう。
というのはどうだろう。
市民まちづくり集会の目的は、 「市民、議会(議員)、行政(市長)が一堂に会し、意見交換や情報共有を行うことで、より魅力あるまちとなるよう力を合わせる場です。」だが、会場にいる多くの一般市民はただ聞くだけになっているのが現状だ。
先に挙げたようなやり方を用いるのは、ヤジ封じと会場の一般市民の意見を言う機会両方を兼ね備えるものとしてなかなかいいんじゃないかと自画自賛するのだが、どうだろうか(笑
会場からの発言、いわゆるヤジは明らかにルール違反だ。
今年度第1回の市民自治会議ではこのヤジに大きな不満を持った委員さんがいて、
「ヤジを発した本人を特定して、今後出入りを禁止させてはどうか」などと言っていた。
サッカーJリーグの浦和レッズサポーターがやった差別的行為に対する措置を例にしたみたいだ。
ちょいと本旨からズレるかもしれないけど、本人にはどうしようもないコトで区別されることを「差別」と言い、今の世の中、そして特にサッカー界では差別行為に対して厳しい態度が取られているね。
ヤジは差別行為か? 「ヤジ=差別」ゆえにまちづくり集会から排除されるべき、か?
これはおかしいね。
確かにルール違反だけれども、その対処としてサッカーの事例を持ってくるのは違うだろう。
ヤジは、言ってみれば自由な発言で、その会場から排除して発言する機会を奪い去ることは、ヤジを言う人の自由を制限することになり、こっちの方がむしろ差別行為になるだろう。
とは言っても会場からデカい声で喚かれては、壇上で正当な機会を得て発言している人の邪魔になり、よろしくない。
厳しい処罰を用意するのではなく、参加者皆が紳士的にルールを守るのが一番理想なのだが・・・。
こういう問題は知恵を使ってウマく解決したいものだ。
まず、そもそもなぜヤジがとぶのか?
始めから妨害目的なら、まちづくり集会の開催直後から盛んにヤジをとばせばいいはずだが、今回のまちづくり集会では最初からしばらくの間は会場は静かだったのだ。
ヤジが初めて確認できたのは、選択肢2の説明の時だ。
説明していた山本一昭氏が「庁舎が道路を挟んで分かれているため、市民や職員の移動安全上効率上、問題になります」と言ったときヤジがとんだ。
ちなみにDVDで41分45秒ぐらいのときだ。
「問題になります」という言い方は、“悪いこと”“ネガティブ”なイメージがある。
ここに敏感に反応したのだろう。
「選択肢2はよくない」というミスリードは両選択肢にとって公平では無い。
このヤジのタイミングは注目すべきだ。
すなわち、ヤジを発した人は発言者の言う事をよく聞いてくれているのだ。
よく聞き、その発言に対して即座に「おかしい!」と感じたからこそ、「ヤジ」と言うより「率直な意見」が放たれたのではあるまいか。
本当はその発言の内容を知りたいところだが、DVDではよく確認できなかった。
ひょっとしたら「バカヤロー」的なただの罵声だったかもしれない。罵声ではちょっといただけないかな。
あの大きな会場で、今まで静かだった状態で、いきなり大きな声を出せば大きな注目を浴びることは間違いない。
これはかなり恥ずかしい。勇気のいることだ。
実際、41分45秒の初めてのヤジ以降は盛んにヤジがとんだ。誰かがひとり言ってくれれば後に続きやすいものだ。
タイミングのよい、最初のヤジは、実は貴重な発言でもある、と言えないだろうか。
ここからは妄想なのだが、会場に係りの者を多数配置しておき、ヤジを最初に言った人を素早く見つける体制を作っておく。
ヤジを言った人を特定できたら、その人に3分間のスピーチタイムを与える。
会場の一般市民からの正式な発言として記録するし、壇上の人も会場の人たちも皆傾聴する。
終わった後は拍手でその発言の良し悪しを判定する。
くだらない、まさに「ヤジ」でしかない発言なら遠慮なくブーイングする。
壇上の発言に対する鋭い発言なら大喝采する。
しかし会場からの発言は原則的にはルール違反だから、以降は静かにしていてもらう。
というのはどうだろう。
市民まちづくり集会の目的は、 「市民、議会(議員)、行政(市長)が一堂に会し、意見交換や情報共有を行うことで、より魅力あるまちとなるよう力を合わせる場です。」だが、会場にいる多くの一般市民はただ聞くだけになっているのが現状だ。
先に挙げたようなやり方を用いるのは、ヤジ封じと会場の一般市民の意見を言う機会両方を兼ね備えるものとしてなかなかいいんじゃないかと自画自賛するのだが、どうだろうか(笑
2015年09月13日 Posted by けま at 08:26 │Comments(0) │まちづくり集会
まちづくり集会総括 8
選択肢について「わかりにくい」ということが市民の間からの声として出ていたし、新聞もそういう記事を載せていた。
この選択肢の意味、そこから派生するいろんな事柄については議会がよく「知っている」はずだった。
なぜならこの住民投票条例は議会発議で議決したものだからだ。
自分たちが議論して決めたものを「知らない」わけがないし、市民から質問があれば議会こそが答えるべきだ。
ところがこのまちづくり集会では、議会が発言したのは住民投票が決まった経緯のみ。
選択肢の説明、質疑応答など、肝心の部分では発言しなかった。
情報を持っている議会が市民との「情報共有」を避けた、と捉えてもいいだろう。
実行委員会に議会から「発言しない」と申し入れがあったのか、実行委員会が議会に「発言するな」と言ったのか。
まぁこれは表向きの「筋論」であって、隠された「公平公正を保つ」ために実行委員会が議会の発言を遠慮してもらったのかもしれない。
その議会が答えない代わりに、質疑応答では「行政(市職員)」が回答した。
もちろんここでも議会が回答するのが筋だ。
実行委員会の見解で、「求める会」が当事者でない故にその主張を前面に押し出すことが避けられた。
だから、このまちづくり集会の当事者の議会は表に立って答えるのは当然だ。
このように「公平公正を保つ」故に筋が通らなくなっている状態を作り出してしまった実行委員会だが、議会が自ら筋を通す態度をとらなかったのも原因だろう。
議会のこの筋を通さない態度。議会自身の総括はあるのだろうか?
新庁舎建設の現計画について圧倒的に詳しいのは行政だ。
その行政が回答するのは「情報共有」の点で望ましいと言えるだろう。
その「情報」については、どういう姿勢であるべきか。
質疑に回答するにあたって選択肢1、2ともに行政が答えている。
選択肢2が「求める会」の提案ではない、と先に書いたが、白井議員のブログでのコメントで田村氏が「両案とも行政案である旨を集会でもご説明申し上げたつもりでしたが・・・」と述べている。
ここでは、「選択肢2は求める会の案ではない」と言うだけでなく、積極的に「選択肢1、2ともに行政が考えた案だ」と言っている。
ということは選択肢1、2ともに行政が市民に「こうですよ!」と披露したモノなわけだ。
選択肢1も2も一生懸命行政が考えたモノで、「どちらがいいか市民に決めてもらおう」と捉えていいのだろう。
そこでこの発言だ。
質疑応答で「選択肢1は現計画を引き継いだもの」、「選択肢2は設計してみないとわからない」。
選択肢1の現計画に基づいた具体的なモノに対して、選択肢2、すなわち設計してみないとわからないシロモノを市民に提示したというわけだ。
2つの案を提示するならどちらも「わかっているモノ」を提示すべきだろう。「設計してみないとわからないモノ」を行政がわざわざ考えたということか。
これは行政の「情報」に対する「不誠実」だろう。こういう情報を共有するのがまちづくり集会か?
行政は「設計してみないとわからないモノ」を提示したことをどう考えているのだろうか?
そんな中で市民は自分の置かれた立場で両案はどう違うのか?その比較でどちらかの選択肢を選ぼうと質問した。
これも先のブログでその模様を書いたが、市民は具体的に比較したかったことは間違いない。
しかしこのまちづくり集会では、
「50億5階建てとか30億3階建てを問うものではありません。」との発言があり、
・「建設費用」は現計画(49億700万)を目標とする。
・「庁舎面積」は機能を確保した上で縮小する。
・庁舎の階数、建設費用はまだ確定されていない。
というばかりで、具体的な数字は建設費用の上限値だけだ。
投票広報に忠実であるのは確かだが、これは市民と共有するに足る情報か?
行政には選択肢1の新庁舎が頭にあって、でも市民は具体的に建物を想像できていなくて、これで「より魅力あるまちとなるよう力を合わせる」ことができるのか。
具体的なカタチも示さないのに、「現計画はこんなです」というタテマエで「現計画の新庁舎のイメージ動画」を流すのは市民を意図的に誘導していないか?
実行委員会は市民にどういう情報を知ってもらいたかったのだろうか?
「求める会」と「議会・行政」を対象にした「公平公正さを保つ」ために、
そして投票広報の内容を無批判に忠実に伝えることを優先し、
市民に対していびつな情報を与えることになってしまったのではないか?
開催までの期間がとても短かかったのが実行委員会にとってなにより悔やまれることだろう。
しかし私はもう少し、住民投票に対する市民(どの派にも属さない)の考えをくみ取れなかっただろうかと思うのだ。
この選択肢の意味、そこから派生するいろんな事柄については議会がよく「知っている」はずだった。
なぜならこの住民投票条例は議会発議で議決したものだからだ。
自分たちが議論して決めたものを「知らない」わけがないし、市民から質問があれば議会こそが答えるべきだ。
ところがこのまちづくり集会では、議会が発言したのは住民投票が決まった経緯のみ。
選択肢の説明、質疑応答など、肝心の部分では発言しなかった。
情報を持っている議会が市民との「情報共有」を避けた、と捉えてもいいだろう。
実行委員会に議会から「発言しない」と申し入れがあったのか、実行委員会が議会に「発言するな」と言ったのか。
まぁこれは表向きの「筋論」であって、隠された「公平公正を保つ」ために実行委員会が議会の発言を遠慮してもらったのかもしれない。
その議会が答えない代わりに、質疑応答では「行政(市職員)」が回答した。
もちろんここでも議会が回答するのが筋だ。
実行委員会の見解で、「求める会」が当事者でない故にその主張を前面に押し出すことが避けられた。
だから、このまちづくり集会の当事者の議会は表に立って答えるのは当然だ。
このように「公平公正を保つ」故に筋が通らなくなっている状態を作り出してしまった実行委員会だが、議会が自ら筋を通す態度をとらなかったのも原因だろう。
議会のこの筋を通さない態度。議会自身の総括はあるのだろうか?
新庁舎建設の現計画について圧倒的に詳しいのは行政だ。
その行政が回答するのは「情報共有」の点で望ましいと言えるだろう。
その「情報」については、どういう姿勢であるべきか。
質疑に回答するにあたって選択肢1、2ともに行政が答えている。
選択肢2が「求める会」の提案ではない、と先に書いたが、白井議員のブログでのコメントで田村氏が「両案とも行政案である旨を集会でもご説明申し上げたつもりでしたが・・・」と述べている。
ここでは、「選択肢2は求める会の案ではない」と言うだけでなく、積極的に「選択肢1、2ともに行政が考えた案だ」と言っている。
ということは選択肢1、2ともに行政が市民に「こうですよ!」と披露したモノなわけだ。
選択肢1も2も一生懸命行政が考えたモノで、「どちらがいいか市民に決めてもらおう」と捉えていいのだろう。
そこでこの発言だ。
質疑応答で「選択肢1は現計画を引き継いだもの」、「選択肢2は設計してみないとわからない」。
選択肢1の現計画に基づいた具体的なモノに対して、選択肢2、すなわち設計してみないとわからないシロモノを市民に提示したというわけだ。
2つの案を提示するならどちらも「わかっているモノ」を提示すべきだろう。「設計してみないとわからないモノ」を行政がわざわざ考えたということか。
これは行政の「情報」に対する「不誠実」だろう。こういう情報を共有するのがまちづくり集会か?
行政は「設計してみないとわからないモノ」を提示したことをどう考えているのだろうか?
そんな中で市民は自分の置かれた立場で両案はどう違うのか?その比較でどちらかの選択肢を選ぼうと質問した。
これも先のブログでその模様を書いたが、市民は具体的に比較したかったことは間違いない。
しかしこのまちづくり集会では、
「50億5階建てとか30億3階建てを問うものではありません。」との発言があり、
・「建設費用」は現計画(49億700万)を目標とする。
・「庁舎面積」は機能を確保した上で縮小する。
・庁舎の階数、建設費用はまだ確定されていない。
というばかりで、具体的な数字は建設費用の上限値だけだ。
投票広報に忠実であるのは確かだが、これは市民と共有するに足る情報か?
行政には選択肢1の新庁舎が頭にあって、でも市民は具体的に建物を想像できていなくて、これで「より魅力あるまちとなるよう力を合わせる」ことができるのか。
具体的なカタチも示さないのに、「現計画はこんなです」というタテマエで「現計画の新庁舎のイメージ動画」を流すのは市民を意図的に誘導していないか?
実行委員会は市民にどういう情報を知ってもらいたかったのだろうか?
「求める会」と「議会・行政」を対象にした「公平公正さを保つ」ために、
そして投票広報の内容を無批判に忠実に伝えることを優先し、
市民に対していびつな情報を与えることになってしまったのではないか?
開催までの期間がとても短かかったのが実行委員会にとってなにより悔やまれることだろう。
しかし私はもう少し、住民投票に対する市民(どの派にも属さない)の考えをくみ取れなかっただろうかと思うのだ。
2015年09月12日 Posted by けま at 10:19 │Comments(0) │まちづくり集会
まちづくり集会総括 7
公平 → かたよらず、えこひいきのないこと。
公正 → 公平で邪曲のないこと。明白で正しいこと。
住民投票の経緯を追っている中での一番の情報源は白井倫啓議員のブログだ。
その4月25日のブログ内コメントで、まちづくり集会実行委員長の田村氏がこう述べていた。
「公平・公正を保つため、憶測や思い込みを廃し、客観的事実に基づいて集会を開催しようと取り組んでいます」
つまり住民投票において「求める会」といわゆる「市長案」の対立構造が存在することを意識していたのだ。
だからこそ「公平公正を保つ」と言っているのだろう。
そしてその「公平公正を保つ」対象は、選択肢2を推す「求める会」と選択肢1を推す「市長・行政・議会主流派」だ。
「公平公正を保つ」手段として、まちづくり集会での意見する機会を平等することを意識したように見える。
住民投票にいたる経緯説明では「求める会」と「議会」両方にしてもらった。
質疑応答では質問者として「求める会」、回答者として「行政」となった。
この質疑応答では様々な階層の市民からの質問に行政が回答する形式をとったため、時間的に言えば圧倒的に行政が多く、「求める会」はわずか15分余りで、ここは「公平」ではなかったと言えるかもしれない。
しかし様々な市民の階層のひとつとして、単独で「求める会」が選ばれていることは大きな配慮だったようにも思える。
まちづくり集会実行委員の今回の住民投票条例に対する見解は、
・今回の市民まちづくり集会は、議員発議による住民投票条例によるもの。
・「求める会」は「住民投票を求めた」が、今回の集会において「住民投票を求めた」当事者ではない。
・これまでの3回(20日.27日.1日)の実行委員会では、集会の主催者である議会からは、「選択肢2が、これまで「求める会」が提案してきものと同じである」ことは明確だとの説明は受けていない。そのため「議会からの説明を聞く限り」では、当事者とはならない。
・あくまで現在各戸配布されているこの投票広報に基づいて集会を開催することが任務
というもの(白井議員ブログ内での田村氏コメントより)。
「求める会」が当事者の住民投票ではない。選択肢2も「求める会」の提案ではない。
というわけだ。
その見解でまちづくり集会を見てみれば、実行委員は「求める会」と「市長案派」の両方に対して概ね「公正公平」であったと言ってもいいだろう。
「市民が主役のまちづくりルールブック」という小さなパンフレットがあって、その中に市民まちづくり集会の目的が書いてある。
「市民、議会(議員)、行政(市長)が一堂に会し、意見交換や情報共有を行うことで、より魅力あるまちとなるよう力を合わせる場です。」
これは今回のまちづくり集会の冒頭でも実行委員長田村氏も述べていた。
「公平公正を保つ」のはいわば“隠された”目的と言えるが、この表向きの目的も当然果たされなければならない。
では議会、行政はどういう態度であっただろうか?
公正 → 公平で邪曲のないこと。明白で正しいこと。
住民投票の経緯を追っている中での一番の情報源は白井倫啓議員のブログだ。
その4月25日のブログ内コメントで、まちづくり集会実行委員長の田村氏がこう述べていた。
「公平・公正を保つため、憶測や思い込みを廃し、客観的事実に基づいて集会を開催しようと取り組んでいます」
つまり住民投票において「求める会」といわゆる「市長案」の対立構造が存在することを意識していたのだ。
だからこそ「公平公正を保つ」と言っているのだろう。
そしてその「公平公正を保つ」対象は、選択肢2を推す「求める会」と選択肢1を推す「市長・行政・議会主流派」だ。
「公平公正を保つ」手段として、まちづくり集会での意見する機会を平等することを意識したように見える。
住民投票にいたる経緯説明では「求める会」と「議会」両方にしてもらった。
質疑応答では質問者として「求める会」、回答者として「行政」となった。
この質疑応答では様々な階層の市民からの質問に行政が回答する形式をとったため、時間的に言えば圧倒的に行政が多く、「求める会」はわずか15分余りで、ここは「公平」ではなかったと言えるかもしれない。
しかし様々な市民の階層のひとつとして、単独で「求める会」が選ばれていることは大きな配慮だったようにも思える。
まちづくり集会実行委員の今回の住民投票条例に対する見解は、
・今回の市民まちづくり集会は、議員発議による住民投票条例によるもの。
・「求める会」は「住民投票を求めた」が、今回の集会において「住民投票を求めた」当事者ではない。
・これまでの3回(20日.27日.1日)の実行委員会では、集会の主催者である議会からは、「選択肢2が、これまで「求める会」が提案してきものと同じである」ことは明確だとの説明は受けていない。そのため「議会からの説明を聞く限り」では、当事者とはならない。
・あくまで現在各戸配布されているこの投票広報に基づいて集会を開催することが任務
というもの(白井議員ブログ内での田村氏コメントより)。
「求める会」が当事者の住民投票ではない。選択肢2も「求める会」の提案ではない。
というわけだ。
その見解でまちづくり集会を見てみれば、実行委員は「求める会」と「市長案派」の両方に対して概ね「公正公平」であったと言ってもいいだろう。
「市民が主役のまちづくりルールブック」という小さなパンフレットがあって、その中に市民まちづくり集会の目的が書いてある。
「市民、議会(議員)、行政(市長)が一堂に会し、意見交換や情報共有を行うことで、より魅力あるまちとなるよう力を合わせる場です。」
これは今回のまちづくり集会の冒頭でも実行委員長田村氏も述べていた。
「公平公正を保つ」のはいわば“隠された”目的と言えるが、この表向きの目的も当然果たされなければならない。
では議会、行政はどういう態度であっただろうか?
2015年09月12日 Posted by けま at 09:14 │Comments(0) │まちづくり集会
まちづくり集会はどんな感じだった? 8
自分自身のために「まちづくり集会総括」として、実際のまちづくり集会はどうだったのか?ということをだらだらと書き続けてきた。
だらだら書いていくうちに自分でも色々気づくことができたのが、このブログでの個人的な収穫だ。
というわけで、この回で「まちづくり集会はどんな感じだった?」も終わりだ。
・地域(代表区長会)
1 防災拠点としての庁舎被害と危機管理はどうするのか?
回答 → 東庁舎は耐震性に問題があるので選択肢1でもって取り壊し一棟集約を考えた。選択肢2では東庁舎被害での行政混乱(情報収集や情報提供において)を可能な限り少なくする、と言う計画になるのだろうと思います。
(まるで他人事な物言いだ。選択肢2についても責任持った回答をしないのはなぜ?)
2 災害時市役所が機能不全になった場合の情報提供はどうなるのか?地域を任されている区長としてはどう責任を果たせばよいか?
回答 → 新庁舎は大震災にはびくともしないことが大前提。しかし東庁舎には被害があるかもしれない。その時には行政は混乱するだろう。
(ヤジが入る。よく聞き取れないが東庁舎の被害への言及が原因か?)
3 合併特例債が使えなくなったら、地域の保全安全が維持できるか不安を持っている。
回答 → 選択肢1については「現計画を引き継いだ形になっている(市側発言)」ので合併特例債は使う。選択肢2では・土地Cの費用・東庁舎の改修メンテに合併特例債は使えない。そういう理解でお願いします。
地区の期待は非常時に防災拠点として機能するか否か?ということなんだが、新城・鳳来・作手の3地区代表の方がそろって同じようなことを質問しているのがちょいと引っかかるねw
どの質問も引き合いに出されているのが「東庁舎は被害に遭うし、カネはかかる」。
しかしここでしっかり言質を取れたのが「(選択肢1については)現計画を引き継いだ形になっている」だ。
これは大事な発言。
・経済界(地域産業総合振興条例審議委員会)
1 規模縮小に伴い三河材を使わなくなること、地域の産業をどう活用するのか、この2点。選択肢の違いを。
回答 → コスト削減のための見直し優先順位を考えると、市民サービスに直接影響の少ない太陽光パネル・木製ルーバーを抑えることになる。市では独自の木材促進の方針を持っている。内装には選択肢1も2も木材を使っていこうと思っている。地域産業の活用については1・2ともに同じようにやっていく。
2 情報管理についてどうやっているか。
回答 →情報持ち出しリスクは2棟になる選択肢2のほうが高い。
3 税負担について再度説明を。
回答 → 新庁舎建設を原因に税金が上がることはない。
(ヤジが入る。鈴木先生注意する。)
「情報管理についてどうやっているか。」という質問は補足すると、この質問者の会社では社外に情報の入ったメディアを持ち出すときに厳しいルールがあって、多くの市民の情報を有する市ではどうしているか?ということだった。
まぁ確かに2棟間の移動は屋外になるわけだからそういうリスクはあるかもね。
でもなぁ、敷地内の移動でもあるわけで、それは敷地内(屋外だけど)の防犯の範疇じゃないかな?その会社が問題にしたいのは、情報を持っている人が社外(市役所的には敷地外)に出たときの情報取扱いポリシーのことなんじゃないか?それが新庁舎とどう関係するのかわかんないけど。
少し時間が余ったみたいで、コーディネーターの鈴木先生から、
↓
「もし追加で質問があったら各グループひとつだけ、どうですか?」
・求める会
1 見直しによって当初の予算以内に収めるのが選択肢1なのか?
回答 → 現時点の見直し状況では予算内に収まっている。
(ヤジ入る。)
・子育て世代
1 車では来れない市民層にはどういう対応を?
回答 → 市バス利用等を考えていきたい。
鈴木先生のまとめ
↓
「住民投票の情報を共有する努力が為された」
ここで質疑応答終了。
最後に実行委員会委員長田村氏の発言
↓
「投票結果は数字でしか出てこないが、その裏の市民の思いを尊重してほしい。忘れてはいけない。」
主催者を代表して、市議会議長、市長からあいさつ。
議長 夏目勝吾 →普通のあいさつなんで割愛
市長 → 市長のここでのあいさつは市長ブログ(http://tomako.dosugoi.net/e764045.html)に要点が載っている。
この回では「防災の観点では、東庁舎は被害に遭うし、カネはかかる」ということと、「東庁舎と新庁舎の間を行き交う時に情報の入ったメディアを落とす、盗られるかもしれない」ということが質問から回答された。
あと、「(選択肢1については)現計画を引き継いだ形になっている」と言質が取れた。
「まちづくり集会は公平公正だったのか?」という全体的な判断をこの後やってみたい。
そして書いていくうちに思ったのだが、住民投票条例議決の経緯を鑑み、議会と行政はどうあるべきだったのか考えてみたい。
あと、ヤジに対してどうするべきか?
とりあえず、この3点。次回に考えてみよう。
だらだら書いていくうちに自分でも色々気づくことができたのが、このブログでの個人的な収穫だ。
というわけで、この回で「まちづくり集会はどんな感じだった?」も終わりだ。
・地域(代表区長会)
1 防災拠点としての庁舎被害と危機管理はどうするのか?
回答 → 東庁舎は耐震性に問題があるので選択肢1でもって取り壊し一棟集約を考えた。選択肢2では東庁舎被害での行政混乱(情報収集や情報提供において)を可能な限り少なくする、と言う計画になるのだろうと思います。
(まるで他人事な物言いだ。選択肢2についても責任持った回答をしないのはなぜ?)
2 災害時市役所が機能不全になった場合の情報提供はどうなるのか?地域を任されている区長としてはどう責任を果たせばよいか?
回答 → 新庁舎は大震災にはびくともしないことが大前提。しかし東庁舎には被害があるかもしれない。その時には行政は混乱するだろう。
(ヤジが入る。よく聞き取れないが東庁舎の被害への言及が原因か?)
3 合併特例債が使えなくなったら、地域の保全安全が維持できるか不安を持っている。
回答 → 選択肢1については「現計画を引き継いだ形になっている(市側発言)」ので合併特例債は使う。選択肢2では・土地Cの費用・東庁舎の改修メンテに合併特例債は使えない。そういう理解でお願いします。
地区の期待は非常時に防災拠点として機能するか否か?ということなんだが、新城・鳳来・作手の3地区代表の方がそろって同じようなことを質問しているのがちょいと引っかかるねw
どの質問も引き合いに出されているのが「東庁舎は被害に遭うし、カネはかかる」。
しかしここでしっかり言質を取れたのが「(選択肢1については)現計画を引き継いだ形になっている」だ。
これは大事な発言。
・経済界(地域産業総合振興条例審議委員会)
1 規模縮小に伴い三河材を使わなくなること、地域の産業をどう活用するのか、この2点。選択肢の違いを。
回答 → コスト削減のための見直し優先順位を考えると、市民サービスに直接影響の少ない太陽光パネル・木製ルーバーを抑えることになる。市では独自の木材促進の方針を持っている。内装には選択肢1も2も木材を使っていこうと思っている。地域産業の活用については1・2ともに同じようにやっていく。
2 情報管理についてどうやっているか。
回答 →情報持ち出しリスクは2棟になる選択肢2のほうが高い。
3 税負担について再度説明を。
回答 → 新庁舎建設を原因に税金が上がることはない。
(ヤジが入る。鈴木先生注意する。)
「情報管理についてどうやっているか。」という質問は補足すると、この質問者の会社では社外に情報の入ったメディアを持ち出すときに厳しいルールがあって、多くの市民の情報を有する市ではどうしているか?ということだった。
まぁ確かに2棟間の移動は屋外になるわけだからそういうリスクはあるかもね。
でもなぁ、敷地内の移動でもあるわけで、それは敷地内(屋外だけど)の防犯の範疇じゃないかな?その会社が問題にしたいのは、情報を持っている人が社外(市役所的には敷地外)に出たときの情報取扱いポリシーのことなんじゃないか?それが新庁舎とどう関係するのかわかんないけど。
少し時間が余ったみたいで、コーディネーターの鈴木先生から、
↓
「もし追加で質問があったら各グループひとつだけ、どうですか?」
・求める会
1 見直しによって当初の予算以内に収めるのが選択肢1なのか?
回答 → 現時点の見直し状況では予算内に収まっている。
(ヤジ入る。)
・子育て世代
1 車では来れない市民層にはどういう対応を?
回答 → 市バス利用等を考えていきたい。
鈴木先生のまとめ
↓
「住民投票の情報を共有する努力が為された」
ここで質疑応答終了。
最後に実行委員会委員長田村氏の発言
↓
「投票結果は数字でしか出てこないが、その裏の市民の思いを尊重してほしい。忘れてはいけない。」
主催者を代表して、市議会議長、市長からあいさつ。
議長 夏目勝吾 →普通のあいさつなんで割愛
市長 → 市長のここでのあいさつは市長ブログ(http://tomako.dosugoi.net/e764045.html)に要点が載っている。
この回では「防災の観点では、東庁舎は被害に遭うし、カネはかかる」ということと、「東庁舎と新庁舎の間を行き交う時に情報の入ったメディアを落とす、盗られるかもしれない」ということが質問から回答された。
あと、「(選択肢1については)現計画を引き継いだ形になっている」と言質が取れた。
「まちづくり集会は公平公正だったのか?」という全体的な判断をこの後やってみたい。
そして書いていくうちに思ったのだが、住民投票条例議決の経緯を鑑み、議会と行政はどうあるべきだったのか考えてみたい。
あと、ヤジに対してどうするべきか?
とりあえず、この3点。次回に考えてみよう。
2015年09月07日 Posted by けま at 16:09 │Comments(0) │まちづくり集会
まちづくり集会はどんな感じだった? 7
「さまざまな分野の市民からの質疑応答」がこのプログラムでの趣旨なわけだが、「新庁舎見直しの住民投票を求める会」がここにいて質問するのはちょっと異質な感じだ。
この時「求める会」の席には関係者の他に白井倫啓議員・加藤芳夫議員がいた。
しかし建前から言えば回答側に議員がいるべきなのだ。
これも何回も書いているが、今回の住民投票条例は議会で議決されたものだ。選択肢も議会で話し合われ決まったものだ。選択肢について市民から質疑があれば、その選択肢を決めた議会が回答するのが筋というものだろう。
なのに条例を議決した議員が、自ら作った条例に質問する側にいるこの構図をどう考えたらいいのだろうか・・・?
というか、このおかしさに実行委員会は気づかなかったのか。気づいていながら敢えてこうせざるを得なかったのか。
このおかしさは、議会内で住民投票条例が提案されるまでの経緯や提案された後の経緯を白井議員のブログで眺め、山崎祐一議員が編集、発行人の「新城公論(平成27年3月31日)」を眺めると一応の「答え」が見えてくる。
議会での出来事を我々市民が知る手がかりは議会を傍聴すること、その中継を見ること。後日市のHPで公開される録画を見ること、議事録を読むこと。これが市民の知ることのできる、いわゆる公的な情報と言えるだろうか。
しかしこの情報だけでは・・・
とその続きを書こうとして、念のために市のHPから新城市議会会議録を検索してみたら27年度3月定例会の議事録がアップロードされていた。
『4月の議会報告会ではアップされておらず、まちづくり集会の時ににも確かアップされてなかった。なので住民投票が議決された経緯の公的情報は最近まで無く、それをうかがい知るには白井議員のブログ、山崎議員の「新城公論」を読むしかなかった。それは各議員の私見が大いに反映された二次的な情報しか得られないという状況であり、そこから得られる「答え」はワイドショー的なスキャンダラスなものになりがちで、その「答え」を「真実」として見てよいものか?しかし、公的な情報も議会での答弁であり形式的なものなので、そういう建前的な議論で「真実」は見えてくるのか?』
という感じで書こうとしていたのだけれど、この「27年度3月定例会議事録」、各議員の述べていること、やり取りが割とスリリングでおもしろい。
ここから住民投票条例議決の真実の一面が見えてくるかもしれない。
かなり話が飛んでしまった。これは個人的におもしろく感じたので後でじっくり読んでみよう。
話を戻して、このおかしな構図の中で本来回答側のにいるべき白井議員が質問をした。
・新庁舎見直しの住民投票を求める会
質問に入る前に白井倫啓市議会議員より「求める会の立場」の説明があった。
↓
『3月議会直前まで議会は「現計画の見直しはしない、住民投票は認めない」という立場だった。その後市長の仲介があり立場を一変させ「住民投票をやってほしい」となった。
住民投票を決める過程で「選択肢1は行政が、選択肢2は求める会が書くのが当たり前」というところまでいったが、市長・議会が納得しなかった。そして広報を市長が作ることになり、選択肢1も2も市長が書くに至ってしまったが、選択肢1は50億5階建て、選択肢2は30億3階建て、という立場は明らか。という立場から質問します。』
1 投票用紙での選択肢1、2の表記順を投票間近になって変更することはありえるか?
回答 → 条例で順番がきまっているので条例通り施行する。
2 選択肢1は5階建て、選択肢2は3階建てだが、防災拠点としての機能は大丈夫か?
回答 → 新庁舎部分は大丈夫です。
3 選択肢はどちらも行政の責任で出したもの。2は「(行政が)大丈夫(?東庁舎の耐震性、耐用年数のことを言っているのか?)ではない(と言っている)。」そういうものを選択肢として出すのか?
回答 → 選択肢2は東庁舎を使うことになっている。そして東庁舎が地震で壊れれば改修が必要。平成32年以降(合併特例債の期限)は全部市からの税金で賄わなければならない、とさっきから説明している。
4 求める会では「東庁舎は議会・市民スペース、会議室スペースとしての利用を。市役所の基本機能は新庁舎に集中するべきだ」、と考えている。新庁舎のほうが危ない(地震などの災害に対して?)ということはないか?
回答 → 新庁舎が危ないということはない。
5 選択肢2も現状の7つの施設に分散している市役所機能をひとつにまとめるものだ。(選択肢2も)利便性、効率性は現状より上がるはずだが、その見解を。
回答 → 3階建て30億、5階建て50億を問うものではない。新庁舎は何平米になるかはわからない。敷地面積(広報の土地A)は選択肢2のほうが小さい。
(ここでヤジ多くなり、鈴木先生より注意が入る。「客席からのヤジがうるさくて質問が聞こえない。運営に協力してほしい」)
(しかしヤジ止まらず。白井議員の質問中にもヤジが飛ぶ)
(回答途中だが白井議員が意見する)
↓
市長は求める会の署名の重みを受け止めると言った。市は5階建て50億を、求める会は3階建て30億をうたっており、この思いを受け止めた(筆者注→ と、求める会は考えている)からこそ住民投票は成立したのだ。
6 市の公共施設白書では今後市の公共施設の維持管理に莫大な費用が掛かることが書かれている。そんな中での新庁舎建設において、選択肢1も2も新庁舎の維持管理費が書かれていないが、新庁舎維持管理費のさらなる上乗せが考えられる中で、財政は大丈夫なのか。
回答 → 白書は現状を示したもの。それを今後どう維持管理していくかを2か年かけて検討していく。現在の新庁舎とは切り離して考えていく。
7 鳳来支所は今後どうするのか?
回答 → 鳳来総合支所は次の総合計画でしっかり位置づけする。今ある機能をそのまま残していく。
ここで時間となって終わっている。
求める会は一貫して「30億3階建て」の立場で、現計画の縮小を求めている。
行政、すなわち市側は現計画推進の立場で、本来なら求める会と市側はお互いが対等な議論をする立場として壇上に立っていなければならないのだな。
それが市民の一つの階層として質問しかできない立場に置かれている。
これが求める会のもっとも不満とするところで、ヤジもその不満の現れなのだ。
実行委員会の解釈でこのようになってしまったわけで、それも理解はできる。
しかし市民は比較を求めていたことは、この前の質問者の質問からわかる。
事前にそれを察知することは不可能だったと思うが、市民にとってのわかりやすさを求めるのなら2者の討論形式がよかったのではないかと、後の祭りではあるがそう思ってしまう。
この時「求める会」の席には関係者の他に白井倫啓議員・加藤芳夫議員がいた。
しかし建前から言えば回答側に議員がいるべきなのだ。
これも何回も書いているが、今回の住民投票条例は議会で議決されたものだ。選択肢も議会で話し合われ決まったものだ。選択肢について市民から質疑があれば、その選択肢を決めた議会が回答するのが筋というものだろう。
なのに条例を議決した議員が、自ら作った条例に質問する側にいるこの構図をどう考えたらいいのだろうか・・・?
というか、このおかしさに実行委員会は気づかなかったのか。気づいていながら敢えてこうせざるを得なかったのか。
このおかしさは、議会内で住民投票条例が提案されるまでの経緯や提案された後の経緯を白井議員のブログで眺め、山崎祐一議員が編集、発行人の「新城公論(平成27年3月31日)」を眺めると一応の「答え」が見えてくる。
議会での出来事を我々市民が知る手がかりは議会を傍聴すること、その中継を見ること。後日市のHPで公開される録画を見ること、議事録を読むこと。これが市民の知ることのできる、いわゆる公的な情報と言えるだろうか。
しかしこの情報だけでは・・・
とその続きを書こうとして、念のために市のHPから新城市議会会議録を検索してみたら27年度3月定例会の議事録がアップロードされていた。
『4月の議会報告会ではアップされておらず、まちづくり集会の時ににも確かアップされてなかった。なので住民投票が議決された経緯の公的情報は最近まで無く、それをうかがい知るには白井議員のブログ、山崎議員の「新城公論」を読むしかなかった。それは各議員の私見が大いに反映された二次的な情報しか得られないという状況であり、そこから得られる「答え」はワイドショー的なスキャンダラスなものになりがちで、その「答え」を「真実」として見てよいものか?しかし、公的な情報も議会での答弁であり形式的なものなので、そういう建前的な議論で「真実」は見えてくるのか?』
という感じで書こうとしていたのだけれど、この「27年度3月定例会議事録」、各議員の述べていること、やり取りが割とスリリングでおもしろい。
ここから住民投票条例議決の真実の一面が見えてくるかもしれない。
かなり話が飛んでしまった。これは個人的におもしろく感じたので後でじっくり読んでみよう。
話を戻して、このおかしな構図の中で本来回答側のにいるべき白井議員が質問をした。
・新庁舎見直しの住民投票を求める会
質問に入る前に白井倫啓市議会議員より「求める会の立場」の説明があった。
↓
『3月議会直前まで議会は「現計画の見直しはしない、住民投票は認めない」という立場だった。その後市長の仲介があり立場を一変させ「住民投票をやってほしい」となった。
住民投票を決める過程で「選択肢1は行政が、選択肢2は求める会が書くのが当たり前」というところまでいったが、市長・議会が納得しなかった。そして広報を市長が作ることになり、選択肢1も2も市長が書くに至ってしまったが、選択肢1は50億5階建て、選択肢2は30億3階建て、という立場は明らか。という立場から質問します。』
1 投票用紙での選択肢1、2の表記順を投票間近になって変更することはありえるか?
回答 → 条例で順番がきまっているので条例通り施行する。
2 選択肢1は5階建て、選択肢2は3階建てだが、防災拠点としての機能は大丈夫か?
回答 → 新庁舎部分は大丈夫です。
3 選択肢はどちらも行政の責任で出したもの。2は「(行政が)大丈夫(?東庁舎の耐震性、耐用年数のことを言っているのか?)ではない(と言っている)。」そういうものを選択肢として出すのか?
回答 → 選択肢2は東庁舎を使うことになっている。そして東庁舎が地震で壊れれば改修が必要。平成32年以降(合併特例債の期限)は全部市からの税金で賄わなければならない、とさっきから説明している。
4 求める会では「東庁舎は議会・市民スペース、会議室スペースとしての利用を。市役所の基本機能は新庁舎に集中するべきだ」、と考えている。新庁舎のほうが危ない(地震などの災害に対して?)ということはないか?
回答 → 新庁舎が危ないということはない。
5 選択肢2も現状の7つの施設に分散している市役所機能をひとつにまとめるものだ。(選択肢2も)利便性、効率性は現状より上がるはずだが、その見解を。
回答 → 3階建て30億、5階建て50億を問うものではない。新庁舎は何平米になるかはわからない。敷地面積(広報の土地A)は選択肢2のほうが小さい。
(ここでヤジ多くなり、鈴木先生より注意が入る。「客席からのヤジがうるさくて質問が聞こえない。運営に協力してほしい」)
(しかしヤジ止まらず。白井議員の質問中にもヤジが飛ぶ)
(回答途中だが白井議員が意見する)
↓
市長は求める会の署名の重みを受け止めると言った。市は5階建て50億を、求める会は3階建て30億をうたっており、この思いを受け止めた(筆者注→ と、求める会は考えている)からこそ住民投票は成立したのだ。
6 市の公共施設白書では今後市の公共施設の維持管理に莫大な費用が掛かることが書かれている。そんな中での新庁舎建設において、選択肢1も2も新庁舎の維持管理費が書かれていないが、新庁舎維持管理費のさらなる上乗せが考えられる中で、財政は大丈夫なのか。
回答 → 白書は現状を示したもの。それを今後どう維持管理していくかを2か年かけて検討していく。現在の新庁舎とは切り離して考えていく。
7 鳳来支所は今後どうするのか?
回答 → 鳳来総合支所は次の総合計画でしっかり位置づけする。今ある機能をそのまま残していく。
ここで時間となって終わっている。
求める会は一貫して「30億3階建て」の立場で、現計画の縮小を求めている。
行政、すなわち市側は現計画推進の立場で、本来なら求める会と市側はお互いが対等な議論をする立場として壇上に立っていなければならないのだな。
それが市民の一つの階層として質問しかできない立場に置かれている。
これが求める会のもっとも不満とするところで、ヤジもその不満の現れなのだ。
実行委員会の解釈でこのようになってしまったわけで、それも理解はできる。
しかし市民は比較を求めていたことは、この前の質問者の質問からわかる。
事前にそれを察知することは不可能だったと思うが、市民にとってのわかりやすさを求めるのなら2者の討論形式がよかったのではないかと、後の祭りではあるがそう思ってしまう。
2015年09月05日 Posted by けま at 11:17 │Comments(0) │まちづくり集会
まちづくり集会はどんな感じだった? 6
質疑応答のさらなる続き。
前回の市民委員に続いて、子育て世代(東部こども園、小中学校PTA連絡協議会)の皆さんが質問した。
子育てに関連することで市役所を訪れる機会はとても多い。
ましてや小さな子どもは一緒に連れて来ざるを得ず、新庁舎の構造が一番ダイレクトに響く市民層の方々だ。
・子育て世代
1 新庁舎建設に伴い、中学生医療費無料がなくなるということはあるのか?
回答 → 市民サービスが低下しないように考えている。その点安心してほしい。(ここでもヤジ)
2 子供の用事では庁舎をあちこち移動することが多い。選択肢1と2ではどうなるのか?
回答 → 現計画では一棟集約でその問題を解決する(「ワンストップサービス・ワンフロア」とか言うらしい)。選択肢1では「現計画を引き継いでいる」が規模縮小するため現計画の傾向のままでいけるかわからない。選択肢2では選択肢1より庁舎の規模が小さくなるので、その条件でワンフロア化できるかは設計してみないとわからない。
3 雨の日の子供連れ来庁は大変。選択肢2では庁舎の近くに駐車スペースがないがどうなるのか?
回答 → 選択肢1では現計画の駐車場案で。選択肢2では土地A部に作る駐車場が庁舎最寄になるとすると、設計してみないとわからないが、数台分しかないのでは。今言えるのは土地Bのメイン駐車場からは道(桜淵東新町線)を渡るのが不便だろう。
(ここで盛んにヤジがとぶ。 選択肢2の不便さを強調するような言い回しだからだろう。不便がないよう努力すると言うべきでは。)
4 選択肢1の取り付け道路だと新城こども園に行くために遠回りをしなくてはならないのか?
回答 → 選択肢1の図、星印のところは人・自転車通行可。不便ではないと思う。
最初に書いた通り、具体的に自分たちが行動するときにどうなるのか?という質問が多い。
これが当然なのだな。
市役所を訪れるのに便利か不便かで決めたい市民もいるし、そのためにはなにより新庁舎の具体的なカタチを示さなくてはならないのだ。
ところがまちづくり集会では、くどいようだが(笑)「50億5階建てとか30億3階建てを問うものではなく」「庁舎の階数、規模、建設費用はまだ確定されていない」ことが前提で、具体的なカタチは示せない建前だ。
特に選択肢2では全くの無計画であることを市側は露呈しており、こんな状態で子育て世代の皆さんに回答するのは不誠実だ。
質問3でのあいまいかつ選択肢2を貶めるような回答では、ヤジが飛ぶのもうなずけるというものだ。
次の質問は、福祉(身体障碍者福祉協会)の皆さん。
こちらの方々も移動に不自由する方が多く、新庁舎の構造が一番気になる市民層だ。
・福祉
1 障碍者用駐車スペース、選択肢1では3台分あるがもう少し増やせないか。選択肢2では身障者用駐車スペースは何台分あるか? 雨降りのとき濡れないで来庁できるか?
回答 → 選択肢1での「3台分」は法律的に導き出した台数。その他に妊婦さん用など3台分、計6台分確保してある。選択肢2では「具体的な設計に入っていない」が、バリアフリー新法により2から3台は確保する。雨降り時は選択肢1では(現計画と同じなので)屋根がある。選択肢2では設計してみないとわからない。
(ここでも「設計してみないとわからない」。どちらの選択肢も比較として同じモノを提出しないと正しい判断ができないだろう)
2 坂道・段差はバリア。新庁舎(選択肢1・2とも)はどうなっているか。選択肢1で身障者用スペースに駐車できなかった場合、一般駐車場から庁舎までフラットか? 選択肢2では東庁舎から新庁舎まで段差または坂はないか?
回答 → 現計画では段差はない。選択肢1では「現計画を受け継ぐ」。選択肢1の駐車場は雨水導き用のわずかな傾斜はあるが基本的にフラット。選択肢2は「設計してみないとわからない」。新庁舎と東庁舎の間の道は「バリア」になるだろう。東庁舎内にも自走できない段差があり、これもバリア。
3 身障者の福祉会議が月に一度ある。合併後広域になり大人数の市民が使用できる会議室が必要。選択肢1、2とも規模縮小であるが会議室が削られることはないか?むしろ増やしてほしい。
回答 → 会議室の運用面は今後考えていかなくてはならないが、現計画では共同スペースとして2つある。選択肢1では機能として2つは残したいと考えている。選択肢2では「面積が小さくなるので条件的に厳しくなる」(ヤジがとぶ)が、そういう会議室は必要になるかもしれないと思っている。
この質問回答に対して鈴木先生が補足
↓
「市民協同目的で話し合いをし、そういうスペースは作るとなった。そのような利用を選択肢1も2も保障できるようするべきだろう。」
質問1での回答で、選択肢2では「具体的な設計に入っていない」と発言している。
質問2での回答で、選択肢1は「現計画を受け継ぐ」と発言している。
まちづくり集会での「事業費、階数、規模は未定」は、はっきり「タテマエ」であると市側は言っているのも同じなのだ。
選択肢1は現計画のままだから具体的に回答でき、選択肢2は無計画なので具体的回答はできない。
こんなことでは市民は比較ができない。
「選択」するのなら「比較」は必要なのだ。
そして比較されるべき2つのモノは内容は異なって構わないが、同じ「精度」のモノを提供するのが「誠意」であり、その態度こそが「公平公正」というべきものだろう。
公平公正な態度でない市側は責められるべきだと思うが、こういう選択肢を条例化した議会がまず一番に責められなくてはならないだろう。
本来ここでの回答は、住民投票条例を議決した議会がするのが筋なのだ。
前回の市民委員に続いて、子育て世代(東部こども園、小中学校PTA連絡協議会)の皆さんが質問した。
子育てに関連することで市役所を訪れる機会はとても多い。
ましてや小さな子どもは一緒に連れて来ざるを得ず、新庁舎の構造が一番ダイレクトに響く市民層の方々だ。
・子育て世代
1 新庁舎建設に伴い、中学生医療費無料がなくなるということはあるのか?
回答 → 市民サービスが低下しないように考えている。その点安心してほしい。(ここでもヤジ)
2 子供の用事では庁舎をあちこち移動することが多い。選択肢1と2ではどうなるのか?
回答 → 現計画では一棟集約でその問題を解決する(「ワンストップサービス・ワンフロア」とか言うらしい)。選択肢1では「現計画を引き継いでいる」が規模縮小するため現計画の傾向のままでいけるかわからない。選択肢2では選択肢1より庁舎の規模が小さくなるので、その条件でワンフロア化できるかは設計してみないとわからない。
3 雨の日の子供連れ来庁は大変。選択肢2では庁舎の近くに駐車スペースがないがどうなるのか?
回答 → 選択肢1では現計画の駐車場案で。選択肢2では土地A部に作る駐車場が庁舎最寄になるとすると、設計してみないとわからないが、数台分しかないのでは。今言えるのは土地Bのメイン駐車場からは道(桜淵東新町線)を渡るのが不便だろう。
(ここで盛んにヤジがとぶ。 選択肢2の不便さを強調するような言い回しだからだろう。不便がないよう努力すると言うべきでは。)
4 選択肢1の取り付け道路だと新城こども園に行くために遠回りをしなくてはならないのか?
回答 → 選択肢1の図、星印のところは人・自転車通行可。不便ではないと思う。
最初に書いた通り、具体的に自分たちが行動するときにどうなるのか?という質問が多い。
これが当然なのだな。
市役所を訪れるのに便利か不便かで決めたい市民もいるし、そのためにはなにより新庁舎の具体的なカタチを示さなくてはならないのだ。
ところがまちづくり集会では、くどいようだが(笑)「50億5階建てとか30億3階建てを問うものではなく」「庁舎の階数、規模、建設費用はまだ確定されていない」ことが前提で、具体的なカタチは示せない建前だ。
特に選択肢2では全くの無計画であることを市側は露呈しており、こんな状態で子育て世代の皆さんに回答するのは不誠実だ。
質問3でのあいまいかつ選択肢2を貶めるような回答では、ヤジが飛ぶのもうなずけるというものだ。
次の質問は、福祉(身体障碍者福祉協会)の皆さん。
こちらの方々も移動に不自由する方が多く、新庁舎の構造が一番気になる市民層だ。
・福祉
1 障碍者用駐車スペース、選択肢1では3台分あるがもう少し増やせないか。選択肢2では身障者用駐車スペースは何台分あるか? 雨降りのとき濡れないで来庁できるか?
回答 → 選択肢1での「3台分」は法律的に導き出した台数。その他に妊婦さん用など3台分、計6台分確保してある。選択肢2では「具体的な設計に入っていない」が、バリアフリー新法により2から3台は確保する。雨降り時は選択肢1では(現計画と同じなので)屋根がある。選択肢2では設計してみないとわからない。
(ここでも「設計してみないとわからない」。どちらの選択肢も比較として同じモノを提出しないと正しい判断ができないだろう)
2 坂道・段差はバリア。新庁舎(選択肢1・2とも)はどうなっているか。選択肢1で身障者用スペースに駐車できなかった場合、一般駐車場から庁舎までフラットか? 選択肢2では東庁舎から新庁舎まで段差または坂はないか?
回答 → 現計画では段差はない。選択肢1では「現計画を受け継ぐ」。選択肢1の駐車場は雨水導き用のわずかな傾斜はあるが基本的にフラット。選択肢2は「設計してみないとわからない」。新庁舎と東庁舎の間の道は「バリア」になるだろう。東庁舎内にも自走できない段差があり、これもバリア。
3 身障者の福祉会議が月に一度ある。合併後広域になり大人数の市民が使用できる会議室が必要。選択肢1、2とも規模縮小であるが会議室が削られることはないか?むしろ増やしてほしい。
回答 → 会議室の運用面は今後考えていかなくてはならないが、現計画では共同スペースとして2つある。選択肢1では機能として2つは残したいと考えている。選択肢2では「面積が小さくなるので条件的に厳しくなる」(ヤジがとぶ)が、そういう会議室は必要になるかもしれないと思っている。
この質問回答に対して鈴木先生が補足
↓
「市民協同目的で話し合いをし、そういうスペースは作るとなった。そのような利用を選択肢1も2も保障できるようするべきだろう。」
質問1での回答で、選択肢2では「具体的な設計に入っていない」と発言している。
質問2での回答で、選択肢1は「現計画を受け継ぐ」と発言している。
まちづくり集会での「事業費、階数、規模は未定」は、はっきり「タテマエ」であると市側は言っているのも同じなのだ。
選択肢1は現計画のままだから具体的に回答でき、選択肢2は無計画なので具体的回答はできない。
こんなことでは市民は比較ができない。
「選択」するのなら「比較」は必要なのだ。
そして比較されるべき2つのモノは内容は異なって構わないが、同じ「精度」のモノを提供するのが「誠意」であり、その態度こそが「公平公正」というべきものだろう。
公平公正な態度でない市側は責められるべきだと思うが、こういう選択肢を条例化した議会がまず一番に責められなくてはならないだろう。
本来ここでの回答は、住民投票条例を議決した議会がするのが筋なのだ。