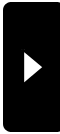印刷局見学の後、どこ行ったんですか?
8月10日に開催された「議員面談要請に伴う会合」に出かけてきた。
この会合は新城市政を考える会さんの主催で行なわれた。
正直に言うと、この事件、というか裁判についてよく知らなかった。
当日頂いた資料を読み、この会合での考える会さんからの質問やこの事件に関係する議員さん方からの回答を聞いていていくらか分かってきたが、それはそれでまた疑問も湧いてきたりして少し消化不良な感じだ。
それからずっと考えてきて、いくらか考えもまとまってきたので久しぶりにこちらのブログに書いてみることとする。
この裁判での争点は、
「二日目の国立印刷局見学が具体的に市政にとって有益であったかどうか」
の、この一点だ。
身もフタもない書き方をしてしまうが、議員さん方の市政に関与する際の頭脳の働き方やセンスは議員さんによってかなり差がある、と思っている。
一生懸命知恵を絞って視察・見学先を決めて、そちらに赴いて説明を聞き、報告書を提出してもらうもA4用紙一枚にしかならなかった。
としても、そりゃもうしょうがないじゃんか、という気がしている。
そういう議員さんなんだもの。私たち市民もそういう人を選んじゃったんだしね。
議員さんの活動を善意に解釈すれば、基本的には「全てが新城市を良くしたい!」という善意の発露だと思う。
だから、議員さんが視察・見学先に行く前から一々細かいこと言うのは、
基 本 的 に 、
言わない方がいいと思っている。
くどいようだけど、彼らなりの善意の発露だと解釈してあげたいから。
そういう意味でこの裁判での争点は、自由でフリーダムな議員さんの活動をいくらか妨げることにならないかと、少々腑に落ちない点でもあった。
ところが、この時の会合での不正規な発言の中で、「『桜を見る会』みたいなのに参加したじゃないか。」「そういう写真を見たぞ」という類のものを耳にしたことを不意に思い出した。
これがこの二日目宿泊にどのように関係するのか(特に時系列的に)は、今となってはよくわからない。
けれども、これは全くの想像になるけれども、この「なんとかの会」みたいなものに参加するのが主たる目的だとしたら。
そしてこの「ナントカの会」出席が二日目午前に行われた印刷局視察の後の、午後に行われたものなら。
はい、以下はワタクシの全くの想像です。
ナントカの会出席したい。
それは二日目午後だから、一日目の用事がすんで一旦新城に帰ってもう一度東京に行くのメンドクサイ。
午前にどうでもよくて短く済ませられる視察を一件入れて「そのために宿泊します」という風にしておいて。
それで午後からのナントカの会に出席できるようにすれば、午前は公務で、午後は公務無しの私的な用事っていうことで体裁も整ってイイじゃないの。
などというようなことを想像してしまいますよ。なんだか辻褄があうじゃないの。
本来なら「私的用事のために宿泊をしたのか否か」が問われる事件だったんじゃないのだろうか?
私的な用事で公金を使った宿泊をされたら、そりゃ税金を納める市民としては全く納得できない。
しかし「午前の『公務』のための宿泊」とくれば、この場合の宿泊を否定するのは難しい。
そして公務が済んだ後に私的な行動を取るのは、これは多少の倫理的な問題を含むと感じるけれども、一般市民でも仕事帰りに飲みに行って通勤用の定期で帰宅なんてことはよくあることを考えれば、これも否定しにくい。
それゆえに、「二日目の国立印刷局見学が具体的に市政にとって有益であったかどうか」 を争点にしたのではないかな、と。
つまり、先ほど挙げた「公務」すなわち「印刷局見学」を、公務に値しないシロモノだと証明できれば、「公務に値しないシロモノ」のための「宿泊」も無効にできる。
と、想像力をたくましくしてみたけれども、さらに仮の話を続けさせてもらえば、
私たち市民が本当に知りたいのは、「二日目の国立印刷局見学が具体的に市政にとって有益であったかどうか」ではなく、
「宿泊の本当の目的は?」とか「印刷局見学の後はどこに行ったんですか?」 となるかな。
もちろん本当のことは言わないのだろうけど、裁判でもないのにその程度のことが言えないのなら、とてもじゃないが「新城市をよくしたい」という善意の発露を期待できる議員では無い、とは言えるだろう。
この会合は新城市政を考える会さんの主催で行なわれた。
正直に言うと、この事件、というか裁判についてよく知らなかった。
当日頂いた資料を読み、この会合での考える会さんからの質問やこの事件に関係する議員さん方からの回答を聞いていていくらか分かってきたが、それはそれでまた疑問も湧いてきたりして少し消化不良な感じだ。
それからずっと考えてきて、いくらか考えもまとまってきたので久しぶりにこちらのブログに書いてみることとする。
この裁判での争点は、
「二日目の国立印刷局見学が具体的に市政にとって有益であったかどうか」
の、この一点だ。
身もフタもない書き方をしてしまうが、議員さん方の市政に関与する際の頭脳の働き方やセンスは議員さんによってかなり差がある、と思っている。
一生懸命知恵を絞って視察・見学先を決めて、そちらに赴いて説明を聞き、報告書を提出してもらうもA4用紙一枚にしかならなかった。
としても、そりゃもうしょうがないじゃんか、という気がしている。
そういう議員さんなんだもの。私たち市民もそういう人を選んじゃったんだしね。
議員さんの活動を善意に解釈すれば、基本的には「全てが新城市を良くしたい!」という善意の発露だと思う。
だから、議員さんが視察・見学先に行く前から一々細かいこと言うのは、
基 本 的 に 、
言わない方がいいと思っている。
くどいようだけど、彼らなりの善意の発露だと解釈してあげたいから。
そういう意味でこの裁判での争点は、自由でフリーダムな議員さんの活動をいくらか妨げることにならないかと、少々腑に落ちない点でもあった。
ところが、この時の会合での不正規な発言の中で、「『桜を見る会』みたいなのに参加したじゃないか。」「そういう写真を見たぞ」という類のものを耳にしたことを不意に思い出した。
これがこの二日目宿泊にどのように関係するのか(特に時系列的に)は、今となってはよくわからない。
けれども、これは全くの想像になるけれども、この「なんとかの会」みたいなものに参加するのが主たる目的だとしたら。
そしてこの「ナントカの会」出席が二日目午前に行われた印刷局視察の後の、午後に行われたものなら。
はい、以下はワタクシの全くの想像です。
ナントカの会出席したい。
それは二日目午後だから、一日目の用事がすんで一旦新城に帰ってもう一度東京に行くのメンドクサイ。
午前にどうでもよくて短く済ませられる視察を一件入れて「そのために宿泊します」という風にしておいて。
それで午後からのナントカの会に出席できるようにすれば、午前は公務で、午後は公務無しの私的な用事っていうことで体裁も整ってイイじゃないの。
などというようなことを想像してしまいますよ。なんだか辻褄があうじゃないの。
本来なら「私的用事のために宿泊をしたのか否か」が問われる事件だったんじゃないのだろうか?
私的な用事で公金を使った宿泊をされたら、そりゃ税金を納める市民としては全く納得できない。
しかし「午前の『公務』のための宿泊」とくれば、この場合の宿泊を否定するのは難しい。
そして公務が済んだ後に私的な行動を取るのは、これは多少の倫理的な問題を含むと感じるけれども、一般市民でも仕事帰りに飲みに行って通勤用の定期で帰宅なんてことはよくあることを考えれば、これも否定しにくい。
それゆえに、「二日目の国立印刷局見学が具体的に市政にとって有益であったかどうか」 を争点にしたのではないかな、と。
つまり、先ほど挙げた「公務」すなわち「印刷局見学」を、公務に値しないシロモノだと証明できれば、「公務に値しないシロモノ」のための「宿泊」も無効にできる。
と、想像力をたくましくしてみたけれども、さらに仮の話を続けさせてもらえば、
私たち市民が本当に知りたいのは、「二日目の国立印刷局見学が具体的に市政にとって有益であったかどうか」ではなく、
「宿泊の本当の目的は?」とか「印刷局見学の後はどこに行ったんですか?」 となるかな。
もちろん本当のことは言わないのだろうけど、裁判でもないのにその程度のことが言えないのなら、とてもじゃないが「新城市をよくしたい」という善意の発露を期待できる議員では無い、とは言えるだろう。
2020年08月22日 Posted by けま at 14:40 │Comments(2) │新城市議会
5月臨時会を傍聴してきた
市議会の話。
市議会において議案が提出されて、議員により賛成反対の意志表示がなされて、そして議案の成立不成立が決まる。
これが大体の流れだけれども、実際には細かなルールがあったり聞き慣れない言葉があったりで詳しくわからないことが多かった。
で、先日行われた5月臨時会議を傍聴に行ったのだが、市議会議長と市議会各委員会の委員長の不信任決議案が実に6回も行なわれるという場面に遭遇した。
同じようなことを6回も。
漢字や英単語を暗記するときは、ひたすら読む書くを繰り返す。
不信任決議案が提出されてその決議が行われるまでの流れを、なんと6回も見せられれば、わからない事の多かった議会で物事が決まる仕組みも漢字や英単語と同じく流石に覚えられるというものだ。
と、まぁ半分は新しい知見を得ることができて満足できた反面、同じことを6回も見せられてあきてしまった気持ちが半分といったところだ。
では満足できたところの「議会で物事が決まる仕組み」的なところで思ったところをいくつか。
今回の不信任決議案のような、事前に議案として上程されていないものを議会で取り扱う場合、その議案が緊急性を要するものか否か? がカギとなる(らしい)。
緊急性があるかどうかを、1)まずは議員皆さんにお尋ねし、2)異議が無ければ、つまり緊急性を要するものであると了解されれば、3)議案として議論に入る。
というプロセスを踏む。
なので、2)のところで誰か一人の議員が「異議あり」と言えば、そこで緊急性を要するものと判断されなかったとして、「議案とはならない」というものらしい。
これは後で書こうと思うのだけれども、今回不信任を突きつけられた委員長の皆さん方は新城市議会においては多数派のお歴々なので、最後の採決で必ず不信任案を否決できる(実際そうなった)。
なので、どうせ否決できるのだからこの 2)の段階で「異議あり」と多数派のうちの誰かに言わせて、不信任案自体を議案にしなければよかったんじゃないかと思うのだが、実際そうはならなかった。
なぜか?
これはこの2)の段階では「異議あり」と言わない暗黙、あるいは議会運営上の慣習的なルールかもしれず、実際のところよくわからない。
どこかで機会があったら議員さんに聞いてみたいと思っている。
次に、この6回の決議にはなぜか市長や副市長といった行政のエライ人たちもずっっっと席に着いていたこと。
委員長の人事に関することに思われる今回の不信任決議案は行政には直接関係ないと思うのだけど・・・。
思いつくのは委員会や議会の開催要件の中に行政の出席があるのかな?ということぐらいだろうか。
いつもの全員協議会にはいないし、各委員会にも出席したとかいう事は聞いたことが無い。
しかしそうすると、この日の予算決算委員会は文字通り「委員会」だが、行政は出席していたことの説明にならない。予算決算は市民からの税金の使途に関係する重要な委員会ではあるけれども、何をもって「重要」か?は一概に決められないと思うので、ルールとしては曖昧だ。
というか、これは議員からの質疑に行政が回答しなければならないからか。予算決算議案の提出者が行政なのだから、その場に行政がいなければ回答できないな。
と考えると、不信任決議案は議員からの発議なので、ますます行政が会議場にいなければならない理由がない。
という感じで、ここでも議会運営のルールの謎にぶつかった。
取りあえずは市長はじめ、行政側のエライ人たちには気の毒なことだったと思う(早く帰るか、執務に戻りたいと思っただろう)。
次は「討論」のこと。
議会が始まる前に市のHPで公開される「発言通告書」。
これは各議員がその議会でこういう発言をしたい、という旨をあらかじめ伝えておく書類なのだけれども、その項目のなかに「発言の種類」というものがある。
「討論」もその発言の種類のなかのひとつで、その議案に対する賛成反対の理由を述べるものだ。
今回の6回の不信任決議案も最後には賛成反対の採決を取る。
なので討論も6回、反対賛成の立場の議員さんたちが自論を展開した。
今回のこの討論、とても聞きごたえのある場面だった。
特に不信任決議案に賛成している(議長、委員長を辞めさせたい議会少数派)議員の皆さんの発言には熱量が豊富にあると感じた。
不信任決議に反対(議長、委員長を辞めさせない議会多数派)の議員をどうにか説得したい、考えを改めてほしいという気持ちが感じられた。
議案の意味を理解するために「質疑」という発言があり、その発言で議案の意味が理解できたら、あとは議員自身の判断で賛成反対を決めて、採決。
この流れで十分と言えば十分だけれども、やはり市民としてはなぜ賛成なのか反対なのかを知りたいところで、その理由はこの「討論」で披露される。
なので「討論」での発言は、議員が市民に対して自分の考えを伝える役割が大きかったように思う。
ところが今回の討論での発言は対市民というより、対議員、その場にいる議員に対するメッセージ性を強く感じた。
考えてみれば自分の思うように議案を可決、否決させたいのが議員の本質だろう。
ならば自分と異なる意思を持っている議員の、その意思を自分の言論でもって変えさせようとするのが「討論」の場に相応しい態度というものではないか。
そしてその態度を強く感じたのが不信任案に賛成する、議会少数派の議員さんたちの発言だった。
ではなぜこんなに熱量のある発言が賛成議員さんたちから相次いだのかは、私のブログでもぼちぼち取り上げている「新城市議会政務活動費返還請求住民訴訟」に繋がってくるのだけれども、これはまた後ほど書くとして。
市議会では多数決で物事が決まる。
新城市議会では明確な会派は無いものの、今回の不信任決議案での賛成反対で表明しているグループ分けが存在している。
なので最後には必ず今回の不信任案に反対する多数派グループの考えが通ってしまう。
今回もそうだ。結局賛成派の発言は反対派の考えを変えるに至らなかった。
しかし結果的にどうなるかは分かっていても、あれだけ聞いている者の心情や理解に訴えかける発言が我が市の議員さんにもできるのだということがわかった。
そのような発言が、ルール通りにするすると流れていく市議会でも可能なのだという事がわかったことは、市議会の在り方に新しい楽しみを見い出せた気がする。
市議会において議案が提出されて、議員により賛成反対の意志表示がなされて、そして議案の成立不成立が決まる。
これが大体の流れだけれども、実際には細かなルールがあったり聞き慣れない言葉があったりで詳しくわからないことが多かった。
で、先日行われた5月臨時会議を傍聴に行ったのだが、市議会議長と市議会各委員会の委員長の不信任決議案が実に6回も行なわれるという場面に遭遇した。
同じようなことを6回も。
漢字や英単語を暗記するときは、ひたすら読む書くを繰り返す。
不信任決議案が提出されてその決議が行われるまでの流れを、なんと6回も見せられれば、わからない事の多かった議会で物事が決まる仕組みも漢字や英単語と同じく流石に覚えられるというものだ。
と、まぁ半分は新しい知見を得ることができて満足できた反面、同じことを6回も見せられてあきてしまった気持ちが半分といったところだ。
では満足できたところの「議会で物事が決まる仕組み」的なところで思ったところをいくつか。
今回の不信任決議案のような、事前に議案として上程されていないものを議会で取り扱う場合、その議案が緊急性を要するものか否か? がカギとなる(らしい)。
緊急性があるかどうかを、1)まずは議員皆さんにお尋ねし、2)異議が無ければ、つまり緊急性を要するものであると了解されれば、3)議案として議論に入る。
というプロセスを踏む。
なので、2)のところで誰か一人の議員が「異議あり」と言えば、そこで緊急性を要するものと判断されなかったとして、「議案とはならない」というものらしい。
これは後で書こうと思うのだけれども、今回不信任を突きつけられた委員長の皆さん方は新城市議会においては多数派のお歴々なので、最後の採決で必ず不信任案を否決できる(実際そうなった)。
なので、どうせ否決できるのだからこの 2)の段階で「異議あり」と多数派のうちの誰かに言わせて、不信任案自体を議案にしなければよかったんじゃないかと思うのだが、実際そうはならなかった。
なぜか?
これはこの2)の段階では「異議あり」と言わない暗黙、あるいは議会運営上の慣習的なルールかもしれず、実際のところよくわからない。
どこかで機会があったら議員さんに聞いてみたいと思っている。
次に、この6回の決議にはなぜか市長や副市長といった行政のエライ人たちもずっっっと席に着いていたこと。
委員長の人事に関することに思われる今回の不信任決議案は行政には直接関係ないと思うのだけど・・・。
思いつくのは委員会や議会の開催要件の中に行政の出席があるのかな?ということぐらいだろうか。
いつもの全員協議会にはいないし、各委員会にも出席したとかいう事は聞いたことが無い。
しかしそうすると、この日の予算決算委員会は文字通り「委員会」だが、行政は出席していたことの説明にならない。予算決算は市民からの税金の使途に関係する重要な委員会ではあるけれども、何をもって「重要」か?は一概に決められないと思うので、ルールとしては曖昧だ。
というか、これは議員からの質疑に行政が回答しなければならないからか。予算決算議案の提出者が行政なのだから、その場に行政がいなければ回答できないな。
と考えると、不信任決議案は議員からの発議なので、ますます行政が会議場にいなければならない理由がない。
という感じで、ここでも議会運営のルールの謎にぶつかった。
取りあえずは市長はじめ、行政側のエライ人たちには気の毒なことだったと思う(早く帰るか、執務に戻りたいと思っただろう)。
次は「討論」のこと。
議会が始まる前に市のHPで公開される「発言通告書」。
これは各議員がその議会でこういう発言をしたい、という旨をあらかじめ伝えておく書類なのだけれども、その項目のなかに「発言の種類」というものがある。
「討論」もその発言の種類のなかのひとつで、その議案に対する賛成反対の理由を述べるものだ。
今回の6回の不信任決議案も最後には賛成反対の採決を取る。
なので討論も6回、反対賛成の立場の議員さんたちが自論を展開した。
今回のこの討論、とても聞きごたえのある場面だった。
特に不信任決議案に賛成している(議長、委員長を辞めさせたい議会少数派)議員の皆さんの発言には熱量が豊富にあると感じた。
不信任決議に反対(議長、委員長を辞めさせない議会多数派)の議員をどうにか説得したい、考えを改めてほしいという気持ちが感じられた。
議案の意味を理解するために「質疑」という発言があり、その発言で議案の意味が理解できたら、あとは議員自身の判断で賛成反対を決めて、採決。
この流れで十分と言えば十分だけれども、やはり市民としてはなぜ賛成なのか反対なのかを知りたいところで、その理由はこの「討論」で披露される。
なので「討論」での発言は、議員が市民に対して自分の考えを伝える役割が大きかったように思う。
ところが今回の討論での発言は対市民というより、対議員、その場にいる議員に対するメッセージ性を強く感じた。
考えてみれば自分の思うように議案を可決、否決させたいのが議員の本質だろう。
ならば自分と異なる意思を持っている議員の、その意思を自分の言論でもって変えさせようとするのが「討論」の場に相応しい態度というものではないか。
そしてその態度を強く感じたのが不信任案に賛成する、議会少数派の議員さんたちの発言だった。
ではなぜこんなに熱量のある発言が賛成議員さんたちから相次いだのかは、私のブログでもぼちぼち取り上げている「新城市議会政務活動費返還請求住民訴訟」に繋がってくるのだけれども、これはまた後ほど書くとして。
市議会では多数決で物事が決まる。
新城市議会では明確な会派は無いものの、今回の不信任決議案での賛成反対で表明しているグループ分けが存在している。
なので最後には必ず今回の不信任案に反対する多数派グループの考えが通ってしまう。
今回もそうだ。結局賛成派の発言は反対派の考えを変えるに至らなかった。
しかし結果的にどうなるかは分かっていても、あれだけ聞いている者の心情や理解に訴えかける発言が我が市の議員さんにもできるのだということがわかった。
そのような発言が、ルール通りにするすると流れていく市議会でも可能なのだという事がわかったことは、市議会の在り方に新しい楽しみを見い出せた気がする。
2020年05月16日 Posted by けま at 12:21 │Comments(0) │新城市議会
「多数決主義」のもたらしたモノ
要望書、陳情書、と言われても一体何を要望しているのか、何を陳情したのか?
前回のブログで書いた全員協議会は2月17日に行われたものだが、この「要望書」「陳情書」なる言葉を初めて聞いたのは2月5日での全員協議会だ。
2月5日の全員協議会(以後、「全協」と略します)では主に市の高速バスのことについて話し合われたのだがそれも終わりかけた頃、丸山議員から「実は・・・」という感じで議員全員に配られたのがこの「要望書」だった。
これが何を意味するのか、私にはさっぱり?だったのだけれども、なんだかエライもんが出てきたという雰囲気で、以後議論が白熱した。
この議論が終わった後も、元市議の加藤さんがとある議員さんに食って掛かる勢いで迫って、とにかくスゴイ場面に遭遇したもんだと興味深かった。
この出来事は浅尾議員のブログ(「ブログ 疑惑の「要望書」が、とうとう明らかに!」)やパパパさんのブログ(「ステップを踏んでいない要望書」)で詳しく書かれていて、全協の後にこちらを読ませてもらって凡そ(おおよそ)理解できた。
というわけで、私は個人的な感想を。
今回の要望やら陳情やらは有志の議員さん達が行なったことで、そのこと自体はなにもおかしいことではない。
その要望・陳情に賛意を示さない議員さんもいて、それも全くおかしいことではない。
議員さんは自身の考えや信念に基づいて政治的な活動をしてもらえればいい。
市議会議員全員が賛同しているわけではない要望書・陳情書に、有志議員の皆さんが「新城市議会」と印刷してしまったことがおかしいのだね。
表紙に「新城市議会」と印刷してあれば、それを見た人は誰だって「市議会議員全員の要望・陳情なんだな」と思うでしょう。
そりゃ賛意を示していない議員さんにとっては「いやいや私は要望も陳情もしておりませんよ」と言いたくなる。
一体なぜ有志議員さんたちは「新城市議会」と印刷してしまったのか。
私ら一般人だってそれくらいの推測はできる。
「『みんな』が言ってるんですよ!(私らだけの主張じゃなくてね!)」ってコトだよね。
常識的には、私たちは「多くの人が賛同している」という事が、主義主張を通したい時の大きな武器、強い理由になる事を知っているからだろう。
そして有志議員たちに「多くの人が賛同している=それこそ力」という実感を持たせているのは、即ち「多数決主義」であろう。
市議会では多くの議案を最終的には多数決で決める。
定例会では一応賛成、反対討論が行われるが、その討論を聞いて考えを改めた、などという話は聞いたことが無い。
もう大体どの議員が賛成するか反対するか、その面子は概ね決まっているのが実情だ。
この時多数派になるのが、件の有志議員達だ。なので多数決で決める段階になれば、反対討論がいかに筋道が通っていようが関係なく、彼らの通したい議案がスイスイ通る。
このように有志議員たちは市議会で彼らの賛成する議案が通ることを実感しているので、「数こそ力」と考えていることは間違いない。
少し「数の力」をネガティブに書いてしまったが、「数こそ力」なのはふつうの市民による「デモ」にも表れている。
「これだけの人数が意見しているんですよ」を、目で見える形(多くの群集)で表しているのがデモだ。
このように、議会にしても民衆が意見を表明するにも「数が力」なのは間違いなく、なので「有志議員」という名前よりも数の多い「新城市議会」という名前で要望・陳情しようという気持ちになるのは私たち一般人にも理解できる。
では「数は力」を成立させるにはどうしたらよいのか。
言い換えれば、「安定的に」「楽に」数の力を成立させるにはどうしたらよいか?
ここに市議会議員ならではの理屈が潜んでいるように感じている。
議員にとってのその理屈の表れは「会派」であろうと思っている。
今現在、市議会には会派は存在しないようだが、この前の選挙以前の市議会では議会改革によって無くす方向になっていた会派を復活させた議員達がいた。
この復活させた議員達が、これまた今回の有志議員たちだったのだ。
会派の中でどのような話し合いがあるのかは知らないが、会派のエラい議員がこうと決めれば会派に所属する議員は皆サッとそれに従う。
つまり「楽~に」力を行使できるのだな。
議会での決定権はオレ達「会派(有志議員たち)」にある、という驕った気持ちが生じていたんじゃないか?
そして最近あった交通費や宿泊費の不正請求(これらも有志議員たちがしでかしたこと)は、「これくらいのズルはいいんじゃね?」という順法精神のユルさからきたんじゃないか?
この「驕った気持ち」と「物事をユルく考える」ことが、「別に『新城市議会』って名前を使ったって文句言うヤツはいないだろ」という安易な行動に繋がったんじゃないかと考えている。
この「多数決主義」という物事を決める方法のひとつに「会派」を使いだすと、結局何も考えずに会派の決めたことにただ従うイエスマンを生み出してしまうことがある。
「なんにも考えない議員」という多数決の一番マズイ特徴が露わになってしまう危険性がある。
「何にも考えない」から、自分たちに反対する意見を主張する少数派の議員をないがしろにする。
そして議員数では少数派であっても、その議員を当選させるために投票した市民の数は決して少なくはないのに、その市民たちを結局ないがしろにしていることに気づかない。
さらに言えば「何も考えない」から、不正請求の元になったお金は「市民の税金」ということに気づかないのだ。
議員全員の了承無しに要望・陳情書に「新城市議会」という名前を使ってしまった今回の件は、新城市議会の現状が生み出した事故と言えるんじゃないだろうか。
前回のブログで書いた全員協議会は2月17日に行われたものだが、この「要望書」「陳情書」なる言葉を初めて聞いたのは2月5日での全員協議会だ。
2月5日の全員協議会(以後、「全協」と略します)では主に市の高速バスのことについて話し合われたのだがそれも終わりかけた頃、丸山議員から「実は・・・」という感じで議員全員に配られたのがこの「要望書」だった。
これが何を意味するのか、私にはさっぱり?だったのだけれども、なんだかエライもんが出てきたという雰囲気で、以後議論が白熱した。
この議論が終わった後も、元市議の加藤さんがとある議員さんに食って掛かる勢いで迫って、とにかくスゴイ場面に遭遇したもんだと興味深かった。
この出来事は浅尾議員のブログ(「ブログ 疑惑の「要望書」が、とうとう明らかに!」)やパパパさんのブログ(「ステップを踏んでいない要望書」)で詳しく書かれていて、全協の後にこちらを読ませてもらって凡そ(おおよそ)理解できた。
というわけで、私は個人的な感想を。
今回の要望やら陳情やらは有志の議員さん達が行なったことで、そのこと自体はなにもおかしいことではない。
その要望・陳情に賛意を示さない議員さんもいて、それも全くおかしいことではない。
議員さんは自身の考えや信念に基づいて政治的な活動をしてもらえればいい。
市議会議員全員が賛同しているわけではない要望書・陳情書に、有志議員の皆さんが「新城市議会」と印刷してしまったことがおかしいのだね。
表紙に「新城市議会」と印刷してあれば、それを見た人は誰だって「市議会議員全員の要望・陳情なんだな」と思うでしょう。
そりゃ賛意を示していない議員さんにとっては「いやいや私は要望も陳情もしておりませんよ」と言いたくなる。
一体なぜ有志議員さんたちは「新城市議会」と印刷してしまったのか。
私ら一般人だってそれくらいの推測はできる。
「『みんな』が言ってるんですよ!(私らだけの主張じゃなくてね!)」ってコトだよね。
常識的には、私たちは「多くの人が賛同している」という事が、主義主張を通したい時の大きな武器、強い理由になる事を知っているからだろう。
そして有志議員たちに「多くの人が賛同している=それこそ力」という実感を持たせているのは、即ち「多数決主義」であろう。
市議会では多くの議案を最終的には多数決で決める。
定例会では一応賛成、反対討論が行われるが、その討論を聞いて考えを改めた、などという話は聞いたことが無い。
もう大体どの議員が賛成するか反対するか、その面子は概ね決まっているのが実情だ。
この時多数派になるのが、件の有志議員達だ。なので多数決で決める段階になれば、反対討論がいかに筋道が通っていようが関係なく、彼らの通したい議案がスイスイ通る。
このように有志議員たちは市議会で彼らの賛成する議案が通ることを実感しているので、「数こそ力」と考えていることは間違いない。
少し「数の力」をネガティブに書いてしまったが、「数こそ力」なのはふつうの市民による「デモ」にも表れている。
「これだけの人数が意見しているんですよ」を、目で見える形(多くの群集)で表しているのがデモだ。
このように、議会にしても民衆が意見を表明するにも「数が力」なのは間違いなく、なので「有志議員」という名前よりも数の多い「新城市議会」という名前で要望・陳情しようという気持ちになるのは私たち一般人にも理解できる。
では「数は力」を成立させるにはどうしたらよいのか。
言い換えれば、「安定的に」「楽に」数の力を成立させるにはどうしたらよいか?
ここに市議会議員ならではの理屈が潜んでいるように感じている。
議員にとってのその理屈の表れは「会派」であろうと思っている。
今現在、市議会には会派は存在しないようだが、この前の選挙以前の市議会では議会改革によって無くす方向になっていた会派を復活させた議員達がいた。
この復活させた議員達が、これまた今回の有志議員たちだったのだ。
会派の中でどのような話し合いがあるのかは知らないが、会派のエラい議員がこうと決めれば会派に所属する議員は皆サッとそれに従う。
つまり「楽~に」力を行使できるのだな。
議会での決定権はオレ達「会派(有志議員たち)」にある、という驕った気持ちが生じていたんじゃないか?
そして最近あった交通費や宿泊費の不正請求(これらも有志議員たちがしでかしたこと)は、「これくらいのズルはいいんじゃね?」という順法精神のユルさからきたんじゃないか?
この「驕った気持ち」と「物事をユルく考える」ことが、「別に『新城市議会』って名前を使ったって文句言うヤツはいないだろ」という安易な行動に繋がったんじゃないかと考えている。
この「多数決主義」という物事を決める方法のひとつに「会派」を使いだすと、結局何も考えずに会派の決めたことにただ従うイエスマンを生み出してしまうことがある。
「なんにも考えない議員」という多数決の一番マズイ特徴が露わになってしまう危険性がある。
「何にも考えない」から、自分たちに反対する意見を主張する少数派の議員をないがしろにする。
そして議員数では少数派であっても、その議員を当選させるために投票した市民の数は決して少なくはないのに、その市民たちを結局ないがしろにしていることに気づかない。
さらに言えば「何も考えない」から、不正請求の元になったお金は「市民の税金」ということに気づかないのだ。
議員全員の了承無しに要望・陳情書に「新城市議会」という名前を使ってしまった今回の件は、新城市議会の現状が生み出した事故と言えるんじゃないだろうか。
2020年02月28日 Posted by けま at 11:48 │Comments(0) │新城市議会
全員協議会を傍聴しての帰り道
浅尾議員のブログを読んで知った2月17日の新城市議会の全員協議会に行ってきた。
その前2月5日の全員協議会にも傍聴に行ったのだが、大変面白い劇のような、しかしリアルに深刻な場面に遭遇して味を占めてしまった。
次回もおんなじことが起こんないかと(笑。
傍聴に当たっての困りごとは、議員の皆さんの議論の元になっている資料が傍聴者には無いことだ。
聞いているうちにあの事かな?と想像できたりするモノもあるが、今回は議題が多くてよくわからないモノもあり、話合いをしている内容の理解がなかなか難しい。
資料があれば理解も進むのだがなぁ、と思う。
今回は傍聴席のちょうどお隣にお馴染みの「パパゲーノの夢」のブロガー「パパパ」さんがいらっしゃって、生で解説してくれて大変助かった。
市政に関心がある人たちの間で知らない方はいないであろう、ブロガーのパパパさんに生でお話しを聞かせてもらえるのは現場の良いところだ。
元市議会議員の加藤さんも元気にヤジ(あるいはでかい独り言)をお飛ばしになられていて(笑、傍聴の現場は結構楽しい。
話合われた内容について思った事はまた後に書くとして、今回は全体的に感じたことを書いてみたい。
全員協議会の最後の議題は「広域連合議会」のことについてだった。
浅尾議員の指摘によれば、新城市から3人の議員が参加しているが今回の「広域連合議会」では3人とも質問をしなかったらしく、また「広域連合議会」で配られた資料も他の新城市議会議員には配られていないらしい。
やるべきことをしっかりやってほしいという浅尾議員からの厳しい意見があり、それはごもっともなことだ。
新城市議会での質問なら、例えば小学校の施設が壊れてるとか修理が必要だという気づきやすい視点から教育予算の問題へと視点を大きくした質問に繋げやすい、てのはあるだろう。
手元に広域連合議会の広報「ひがしみかわ」があるのでパラパラと見てみると、広域連合には3つの取り組みがあって、
1・広域連携事業 単独の市町村では実施困難な事業の調査研究
2・共同処理事務 市町村がそれぞれ行っている事務を一括処理することで質、効率を高める(例えば介護保険事業など)
3・権限移譲事務 県の行っている事務を権限移譲してもらい行政サービスをより身近なものにする
と書いてある。
内容が割と巨視的で身近に感じにくい。これをどうやって質問に組み上げたらよいか悩むのではなかろうか。
広域議会の定例会は8月と2月。3月には新城市の定例会もあるなかでこの時期の質問作りもなかなか大変だろうと同情してしまう。
まぁそうは言っても他の広域連合議会議員さんは質問しているワケだし、そもそも巨視的な見方ができなければ通用しない性格を持っているのが広域連合なのだから、広域連合議員はやらせてもらえれば箔がつく名誉職ではないよね。
そういう考え違いにクギを刺したのが今回の浅尾議員の指摘とも言えるだろう。
そして広域連合議会での資料を配布する件。
資料は広域連合議会議員個人に配布されるだけであろうから、そいつを広域議員3名が新城市議会議員15名分コピーして、選り分けて、ホチキスで留めて・・・、なんて作業は大変でしょうなぁ。
とあるところに置いといて、「各自必要な方はコピーして持ってって~」てワケにもいかんのかな。
資料の取り扱い方としてマズイかね。
コピーしながら「これが市議会議員の仕事か・・・」と悩んでしまうんじゃなかろうかw
それは冗談にしても、やってることは市議会議員の本分ではないだろうな。そんな時間があったら定例会のための勉強でもしたらいいんじゃないかと思う。
これら2つのことから考えてしまうのは、議員の仕事をアシストする仕組みを整えてやる必要があるんじゃないかということだ。
「市議会は年4回。1年に4回しか仕事していないじゃないか!」
とは、よく聞く市民の声だ。
それもまたおっしゃるとおりで、私もそう思っていた。
これは個人的なことだけれども、社会に出てウン十年の自分を振り返ってみると、どうにか無難にこなしているのは自分の仕事だけだということに気づく。
アラフィフのおっさんが間違いなくコピーを取って、見やすい資料を作る。しかも手際よく時間をかけずに。果たしてできるだろうか?と自問自答すると・・・つい考え込んでしまう。
もちろん議員はコピーばかりしているわけではないけどねw
ブログを書くときには一通り議員自身のブログやfacebookをチェックするが、議員は地域の付き合いや様々な集まりによく顔を出していることが目立つ。
そういうのも仕事のひとつと言えようが、やはり定例会で質問するという議員の本分ではないだろう。
今回の全員協議会でも本題のバス事業のことや、裁判にもなっている「要望書問題」での議員さんのやりとりを見ていると、議員になる以前は自分の仕事を持っていてそれなりにこなしていただろうに、議員になってしまったばかりに大変なコトになっておるなぁと、考え込んでしまう。
議員さんとはいえ、公人とはいえ、やはり自分のようなアラフィフおっさんとそうは変わらないんじゃないかと。
1年に4回の仕事、つまりひとつの仕事に3か月というのは、上に書いたことをこなしながらするには割と時間が無いのではないかと、凡人の自分に引き寄せて同情してしまうのだ。
・・・かなり“情”に傾いた感じになってしまった(笑。
というワケで、議員の仕事のアシストの件については、秘書的な仕事をやってくれる人を雇用するために報酬を上げる(今の倍くらい)とか、議員事務局の人数を増やして、議員の本分としての仕事はもちろん、本分ではないがやらなくてはならないこと(コピーとか)をもう少し手厚くフォローできる体制を作るとか、してほしいものだよなと傍聴の帰り道思った次第。
その前2月5日の全員協議会にも傍聴に行ったのだが、大変面白い劇のような、しかしリアルに深刻な場面に遭遇して味を占めてしまった。
次回もおんなじことが起こんないかと(笑。
傍聴に当たっての困りごとは、議員の皆さんの議論の元になっている資料が傍聴者には無いことだ。
聞いているうちにあの事かな?と想像できたりするモノもあるが、今回は議題が多くてよくわからないモノもあり、話合いをしている内容の理解がなかなか難しい。
資料があれば理解も進むのだがなぁ、と思う。
今回は傍聴席のちょうどお隣にお馴染みの「パパゲーノの夢」のブロガー「パパパ」さんがいらっしゃって、生で解説してくれて大変助かった。
市政に関心がある人たちの間で知らない方はいないであろう、ブロガーのパパパさんに生でお話しを聞かせてもらえるのは現場の良いところだ。
元市議会議員の加藤さんも元気にヤジ(あるいはでかい独り言)をお飛ばしになられていて(笑、傍聴の現場は結構楽しい。
話合われた内容について思った事はまた後に書くとして、今回は全体的に感じたことを書いてみたい。
全員協議会の最後の議題は「広域連合議会」のことについてだった。
浅尾議員の指摘によれば、新城市から3人の議員が参加しているが今回の「広域連合議会」では3人とも質問をしなかったらしく、また「広域連合議会」で配られた資料も他の新城市議会議員には配られていないらしい。
やるべきことをしっかりやってほしいという浅尾議員からの厳しい意見があり、それはごもっともなことだ。
新城市議会での質問なら、例えば小学校の施設が壊れてるとか修理が必要だという気づきやすい視点から教育予算の問題へと視点を大きくした質問に繋げやすい、てのはあるだろう。
手元に広域連合議会の広報「ひがしみかわ」があるのでパラパラと見てみると、広域連合には3つの取り組みがあって、
1・広域連携事業 単独の市町村では実施困難な事業の調査研究
2・共同処理事務 市町村がそれぞれ行っている事務を一括処理することで質、効率を高める(例えば介護保険事業など)
3・権限移譲事務 県の行っている事務を権限移譲してもらい行政サービスをより身近なものにする
と書いてある。
内容が割と巨視的で身近に感じにくい。これをどうやって質問に組み上げたらよいか悩むのではなかろうか。
広域議会の定例会は8月と2月。3月には新城市の定例会もあるなかでこの時期の質問作りもなかなか大変だろうと同情してしまう。
まぁそうは言っても他の広域連合議会議員さんは質問しているワケだし、そもそも巨視的な見方ができなければ通用しない性格を持っているのが広域連合なのだから、広域連合議員はやらせてもらえれば箔がつく名誉職ではないよね。
そういう考え違いにクギを刺したのが今回の浅尾議員の指摘とも言えるだろう。
そして広域連合議会での資料を配布する件。
資料は広域連合議会議員個人に配布されるだけであろうから、そいつを広域議員3名が新城市議会議員15名分コピーして、選り分けて、ホチキスで留めて・・・、なんて作業は大変でしょうなぁ。
とあるところに置いといて、「各自必要な方はコピーして持ってって~」てワケにもいかんのかな。
資料の取り扱い方としてマズイかね。
コピーしながら「これが市議会議員の仕事か・・・」と悩んでしまうんじゃなかろうかw
それは冗談にしても、やってることは市議会議員の本分ではないだろうな。そんな時間があったら定例会のための勉強でもしたらいいんじゃないかと思う。
これら2つのことから考えてしまうのは、議員の仕事をアシストする仕組みを整えてやる必要があるんじゃないかということだ。
「市議会は年4回。1年に4回しか仕事していないじゃないか!」
とは、よく聞く市民の声だ。
それもまたおっしゃるとおりで、私もそう思っていた。
これは個人的なことだけれども、社会に出てウン十年の自分を振り返ってみると、どうにか無難にこなしているのは自分の仕事だけだということに気づく。
アラフィフのおっさんが間違いなくコピーを取って、見やすい資料を作る。しかも手際よく時間をかけずに。果たしてできるだろうか?と自問自答すると・・・つい考え込んでしまう。
もちろん議員はコピーばかりしているわけではないけどねw
ブログを書くときには一通り議員自身のブログやfacebookをチェックするが、議員は地域の付き合いや様々な集まりによく顔を出していることが目立つ。
そういうのも仕事のひとつと言えようが、やはり定例会で質問するという議員の本分ではないだろう。
今回の全員協議会でも本題のバス事業のことや、裁判にもなっている「要望書問題」での議員さんのやりとりを見ていると、議員になる以前は自分の仕事を持っていてそれなりにこなしていただろうに、議員になってしまったばかりに大変なコトになっておるなぁと、考え込んでしまう。
議員さんとはいえ、公人とはいえ、やはり自分のようなアラフィフおっさんとそうは変わらないんじゃないかと。
1年に4回の仕事、つまりひとつの仕事に3か月というのは、上に書いたことをこなしながらするには割と時間が無いのではないかと、凡人の自分に引き寄せて同情してしまうのだ。
・・・かなり“情”に傾いた感じになってしまった(笑。
というワケで、議員の仕事のアシストの件については、秘書的な仕事をやってくれる人を雇用するために報酬を上げる(今の倍くらい)とか、議員事務局の人数を増やして、議員の本分としての仕事はもちろん、本分ではないがやらなくてはならないこと(コピーとか)をもう少し手厚くフォローできる体制を作るとか、してほしいものだよなと傍聴の帰り道思った次第。
2020年02月19日 Posted by けま at 10:15 │Comments(3) │新城市議会
一体どういう神経?
https://www.facebook.com/takikawa.kenji1124/posts/861161840702880?pnref=story
滝川議員のfacebookの記事によると、この日、神奈川県南足柄市議会の議長さんはじめ議会運営委員会の皆さんが行政視察のために新城市に訪れたそうな。
なんの行政視察かといえば、
『新城市における新庁舎の議会提案による住民投票条例実施に至る経緯とその後について視察』
ということだ。
南足柄市は2020年度を目途に小田原市への編入合併を検討しており、その際議会提案による住民投票も視野に入れているとのこと。
神奈川県南足柄市議会さん、新城市での住民投票などというマイナーな出来事とか、よくこんな情報を掴んだものだと思う。
さてこの出来事。
最初に、新城市の住民投票の経緯と事前にいただいていた質問に議会事務局から説明があったのは結構なことだ。
が、
その場での質問に、滝川議員と鈴木(達)議員が答えた、とかいうのが気に入らないよ、ハッキリ言って。
しかも最後の文、
「公になっている情報以外の裏話も含めてお話しさせていただきました。」
お ま え が 言 う か ね 。
新城市における新庁舎の議会提案による住民投票条例は、2年前の3月議会において議員提出第5号議案(新城市新庁舎建設における現計画見直しを問う住民投票の制定)として提出された。

見てもらえばわかるとおり、提出者、賛成者には滝川・鈴木(達)議員の他に白井、加藤議員の2人の名前もある。
結果としては白井、加藤議員は棄権するのだが、その経緯というのが実に問題アリなのだ。
この時の経緯は白井議員のブログに詳しい。
→ http://slmichihiro.seesaa.net/archives/201503-1.html
最初に話を戻せば、行政視察の場には白井、加藤議員もいなくてはおかしいだろう。
4人の連名で提出したのだから。
もし白井、加藤両議員がこの議会提案に対して、最終的には「提案に関係しておきながら棄権した故に無責任といえる」とかいう理由でこの行政視察の場に呼ばれなかったのなら、それはそれで理屈も通る。
が、滝川議員の「公になっている情報以外の裏話」てのは一体なんだ?
そういう話をするなら、それこそ白井、加藤議員も同席して白井、加藤議員側の「公になっている情報以外の裏話」も聞かせなきゃフェアじゃないだろうよ。
そして滝川議員の言う「公になっている情報以外の裏話」てのは我々市民こそが知りたいことだよ。
あのおかしな住民投票の経緯って当時から疑惑ありありだったじゃないか。それについてのそちらさん側の裏話てのがあるんならぜひお聞かせ願いたい。
それをなんだろうね、さも自慢げに「お話しさせていただきました。(ニコ顔)(ピースマーク)」って。
一体どういう神経なのか。
自分たちの行いに全く非を感じていないとしか思えないし、住民投票のあのわかりにくい選択肢に対しての反省、とまでいかないなら総括でさえも感じられない。
他の記事でも書きましたがね、
な ん で こ ん な 議 員 を 選 ん で し ま っ た の か 。
滝川議員のfacebookの記事によると、この日、神奈川県南足柄市議会の議長さんはじめ議会運営委員会の皆さんが行政視察のために新城市に訪れたそうな。
なんの行政視察かといえば、
『新城市における新庁舎の議会提案による住民投票条例実施に至る経緯とその後について視察』
ということだ。
南足柄市は2020年度を目途に小田原市への編入合併を検討しており、その際議会提案による住民投票も視野に入れているとのこと。
神奈川県南足柄市議会さん、新城市での住民投票などというマイナーな出来事とか、よくこんな情報を掴んだものだと思う。
さてこの出来事。
最初に、新城市の住民投票の経緯と事前にいただいていた質問に議会事務局から説明があったのは結構なことだ。
が、
その場での質問に、滝川議員と鈴木(達)議員が答えた、とかいうのが気に入らないよ、ハッキリ言って。
しかも最後の文、
「公になっている情報以外の裏話も含めてお話しさせていただきました。」
お ま え が 言 う か ね 。
新城市における新庁舎の議会提案による住民投票条例は、2年前の3月議会において議員提出第5号議案(新城市新庁舎建設における現計画見直しを問う住民投票の制定)として提出された。

見てもらえばわかるとおり、提出者、賛成者には滝川・鈴木(達)議員の他に白井、加藤議員の2人の名前もある。
結果としては白井、加藤議員は棄権するのだが、その経緯というのが実に問題アリなのだ。
この時の経緯は白井議員のブログに詳しい。
→ http://slmichihiro.seesaa.net/archives/201503-1.html
最初に話を戻せば、行政視察の場には白井、加藤議員もいなくてはおかしいだろう。
4人の連名で提出したのだから。
もし白井、加藤両議員がこの議会提案に対して、最終的には「提案に関係しておきながら棄権した故に無責任といえる」とかいう理由でこの行政視察の場に呼ばれなかったのなら、それはそれで理屈も通る。
が、滝川議員の「公になっている情報以外の裏話」てのは一体なんだ?
そういう話をするなら、それこそ白井、加藤議員も同席して白井、加藤議員側の「公になっている情報以外の裏話」も聞かせなきゃフェアじゃないだろうよ。
そして滝川議員の言う「公になっている情報以外の裏話」てのは我々市民こそが知りたいことだよ。
あのおかしな住民投票の経緯って当時から疑惑ありありだったじゃないか。それについてのそちらさん側の裏話てのがあるんならぜひお聞かせ願いたい。
それをなんだろうね、さも自慢げに「お話しさせていただきました。(ニコ顔)(ピースマーク)」って。
一体どういう神経なのか。
自分たちの行いに全く非を感じていないとしか思えないし、住民投票のあのわかりにくい選択肢に対しての反省、とまでいかないなら総括でさえも感じられない。
他の記事でも書きましたがね、
な ん で こ ん な 議 員 を 選 ん で し ま っ た の か 。
2017年08月08日 Posted by けま at 12:58 │Comments(2) │新城市議会
ホントくだらない
https://www.facebook.com/naomi.onoda.7/posts/1373370686075818?pnref=story
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,53027,122,941,html
いつの事かと思えば昨年の7月のことですわ。
誰にも何も言わずに帰ったというなら、そりゃ問題ありですよ。
でも報告はしている。事務局にも委員長にも報告はしている。事情聴取の概要にそう書いてある。
イヤになったから帰る、とか めんどくさくなったから帰る、ってんならそりゃ大問題ですよ。
そんなヤル気のないような態度の市議会議員は困る。
しかし視察を続けられない理由が『家庭の事情』なら、それは内容がどうであれ本人には重要なことに違い無いんですよ。
実際、金銭的な損害や信用問題も起きかねないことだったわけですから。
そういう『家庭の事情』を隠れ蓑にして、どっかで酒飲んでたとか、バクチやってたとかいうなら、それはまた大問題で、それこそウソついてまで私欲的な行動を優先させたとして糾弾されるべきでしょうよ。
でも実際そんなことはなく、全くの『家庭の事情』だったんですよ。
一言付け加えさせてもらえば、『家庭の事情』なら、「子どもの運動会で」とか「妻の誕生日で」でもイイと思うね。
議運はこの報告書でいうところの「私的な理由」と「家庭の事情」の線引きをどう考えているんだろう。
ある人の親族や親しい人が亡くなったという事情だって「極めて私的な理由」(これ報告書に書いてある語句)だよ。ある人以外には全く関係ないからね。でもこれは当事者にとっては重大な「家庭の事情」でしょうよ。
一般的な会社の就業規則には仕事を休む場合に欠勤にはならないケースが書いてあるものだ。
例えば先に挙げた例で言えば「忌引き」は欠勤にはならないし、有給休暇とは別に休んでよい日数が書いてあるものだ。
行政視察の中途離脱に関する条例みたいなのがあって、その中に中途離脱してよい事例が書いてあるのかね?
それに照らし合わせて中途離脱を許可するしないを決めているのだろうか。
そういう線引きが明らかでないのなら「家庭の事情」という理由は最大限尊重されなければならないし、その「家庭の事情」がウソであることが明るみになったなら、これはむしろ新城市議会議員政治倫理条例に抵触する問題ではないだろうかね。
視察は重要だと思うけれども、個人の生活を犠牲にしてまで果たすことだろうかね?
複数人で行っているんだから、参加できなくなった議員の分は残りの人たちでフォローすればいいし、例えば2日目までの視察のレポート(この時の視察は3日間の日程)は加藤議員に任せるとか役割分担すればいいだけの事ですよ。
大体、「 報告して、許可が無い 」ってどういう状況なんだか全く想像できない。
報告すれば何らかの返事をするはずでしょう?
「わかりました」とか「了解しました」とか「ああそうですか」とか。
返事があれば、そりゃ「許可を得た」と思うのが普通でしょうよ。
返事せずに無言だったんかね、この総務消防委員長は。
許可が必要な場面で仮に許可はできないと言うのなら、その場で「帰宅したいのはわかりましたが許可はできません。」ってはっきり言わなきゃわからないよ。 忖度しろってんですかね。
ただ報告書の中での「私的な行動の部分の電車賃は私的なポケットマネーで払うべきだ、という認識はありませんか」という議運の質問は納得できるところだ。
しかしこれについても加藤議員は「払うことについてはやぶさかないと認識している」と回答しているのだから、払ってもらえばいいだろう。
・この前記事にした浅尾議員のブログアップした「抗議文」について当時の議運は「適切な対応を求め」た。つまり「削除しろ」ということだが、未だに削除されていない。
・打桐議員も政倫審から「公の場において本人の主体的な行動による謝意を示すことの勧告」を意見されているが、未だにしていない。
・下江議長は平成25年3月の議会改革特別委員会の副委員長だった時に、議会での会派の廃止を決めた。かつて会派廃止の先頭を走っていたにもかかわらず平成27年8月には自らを代表とする「新城同志会」という会派を結成している。
・住民投票のときに市民を脅すようなチラシで不安を煽ったために政倫審に諮られた山崎議員は、審査会への出席を拒み続けた。
・同時期に同じく山崎議員と柴田議員が白井・加藤議員への政倫審への審査請求を行っていて、これは明らかに山崎議員の政倫審審査への報復だった。
理由があって何か言われても平気で無視するし、自分が手掛けたことでさえも平気で無視する。
自らの属する議会活動に誠実な態度を取らないし、やられたらやり返す短慮的な行動。
こ れ が 新城市議会 で す よ。
どのツラ下げて他人の非難をするんだってことですよ。
ホント、どうしてこんなバカばかり選んでしまったんだろう。
そんなバカさ加減がまたまた現出したのがこの事件ですわ。ホントくだらない。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,53027,122,941,html
いつの事かと思えば昨年の7月のことですわ。
誰にも何も言わずに帰ったというなら、そりゃ問題ありですよ。
でも報告はしている。事務局にも委員長にも報告はしている。事情聴取の概要にそう書いてある。
イヤになったから帰る、とか めんどくさくなったから帰る、ってんならそりゃ大問題ですよ。
そんなヤル気のないような態度の市議会議員は困る。
しかし視察を続けられない理由が『家庭の事情』なら、それは内容がどうであれ本人には重要なことに違い無いんですよ。
実際、金銭的な損害や信用問題も起きかねないことだったわけですから。
そういう『家庭の事情』を隠れ蓑にして、どっかで酒飲んでたとか、バクチやってたとかいうなら、それはまた大問題で、それこそウソついてまで私欲的な行動を優先させたとして糾弾されるべきでしょうよ。
でも実際そんなことはなく、全くの『家庭の事情』だったんですよ。
一言付け加えさせてもらえば、『家庭の事情』なら、「子どもの運動会で」とか「妻の誕生日で」でもイイと思うね。
議運はこの報告書でいうところの「私的な理由」と「家庭の事情」の線引きをどう考えているんだろう。
ある人の親族や親しい人が亡くなったという事情だって「極めて私的な理由」(これ報告書に書いてある語句)だよ。ある人以外には全く関係ないからね。でもこれは当事者にとっては重大な「家庭の事情」でしょうよ。
一般的な会社の就業規則には仕事を休む場合に欠勤にはならないケースが書いてあるものだ。
例えば先に挙げた例で言えば「忌引き」は欠勤にはならないし、有給休暇とは別に休んでよい日数が書いてあるものだ。
行政視察の中途離脱に関する条例みたいなのがあって、その中に中途離脱してよい事例が書いてあるのかね?
それに照らし合わせて中途離脱を許可するしないを決めているのだろうか。
そういう線引きが明らかでないのなら「家庭の事情」という理由は最大限尊重されなければならないし、その「家庭の事情」がウソであることが明るみになったなら、これはむしろ新城市議会議員政治倫理条例に抵触する問題ではないだろうかね。
視察は重要だと思うけれども、個人の生活を犠牲にしてまで果たすことだろうかね?
複数人で行っているんだから、参加できなくなった議員の分は残りの人たちでフォローすればいいし、例えば2日目までの視察のレポート(この時の視察は3日間の日程)は加藤議員に任せるとか役割分担すればいいだけの事ですよ。
大体、「 報告して、許可が無い 」ってどういう状況なんだか全く想像できない。
報告すれば何らかの返事をするはずでしょう?
「わかりました」とか「了解しました」とか「ああそうですか」とか。
返事があれば、そりゃ「許可を得た」と思うのが普通でしょうよ。
返事せずに無言だったんかね、この総務消防委員長は。
許可が必要な場面で仮に許可はできないと言うのなら、その場で「帰宅したいのはわかりましたが許可はできません。」ってはっきり言わなきゃわからないよ。 忖度しろってんですかね。
ただ報告書の中での「私的な行動の部分の電車賃は私的なポケットマネーで払うべきだ、という認識はありませんか」という議運の質問は納得できるところだ。
しかしこれについても加藤議員は「払うことについてはやぶさかないと認識している」と回答しているのだから、払ってもらえばいいだろう。
・この前記事にした浅尾議員のブログアップした「抗議文」について当時の議運は「適切な対応を求め」た。つまり「削除しろ」ということだが、未だに削除されていない。
・打桐議員も政倫審から「公の場において本人の主体的な行動による謝意を示すことの勧告」を意見されているが、未だにしていない。
・下江議長は平成25年3月の議会改革特別委員会の副委員長だった時に、議会での会派の廃止を決めた。かつて会派廃止の先頭を走っていたにもかかわらず平成27年8月には自らを代表とする「新城同志会」という会派を結成している。
・住民投票のときに市民を脅すようなチラシで不安を煽ったために政倫審に諮られた山崎議員は、審査会への出席を拒み続けた。
・同時期に同じく山崎議員と柴田議員が白井・加藤議員への政倫審への審査請求を行っていて、これは明らかに山崎議員の政倫審審査への報復だった。
理由があって何か言われても平気で無視するし、自分が手掛けたことでさえも平気で無視する。
自らの属する議会活動に誠実な態度を取らないし、やられたらやり返す短慮的な行動。
こ れ が 新城市議会 で す よ。
どのツラ下げて他人の非難をするんだってことですよ。
ホント、どうしてこんなバカばかり選んでしまったんだろう。
そんなバカさ加減がまたまた現出したのがこの事件ですわ。ホントくだらない。
2017年06月12日 Posted by けま at 03:03 │Comments(2) │新城市議会
議会報告会に行ってきた(八名地区)
とにかく何か言ってやりたい、その気持ちはよくわかる。
新庁舎建設の件、産廃問題、政倫審のことなどなど、市政に対してとにかく不満を持っている人は多いのだろう。
24日に終了した議会報告会。
特にこの議会報告会では皆さんのご不満が爆発するようだ。
何度も書くが、気持ちはよーくわかる。
私もこのブログで不満をたらたら並べ立てて日頃発散してるので(笑 あの場では黙っていられるようなものだ。
大体こういう議会報告会でもなければ、市民が市政に携わる人に何か言う機会などないのだから。
が、このご不満はよくよく聞いていればやはりご自説をぶちまけているだけで、質問にはなっていないことがよくある。
ぶちまけている方も、さてその御自説をどう終いにしようかと、最後の方では言葉を濁しがちになってしまうようだ。
きっとご自身でも言っているうちに気づくのだろう。
「オレの言ってることは質問ではないなぁ・・・」と。
これら皆さんのご意見を聞いていると、こういうご不満は出し尽くした方がよいとつくづく思う。
多分、今の新城市民には不満の噴出先が足りていない。
それら不満を出し尽くしたその先に、建設的な議論が始まるのだと思う。
先日24日に八名地区の議会報告会に行ってきた。
勝手な印象だけれども、八名地区の皆さんの質問は至って冷静だ。そして鋭い。
議会報告会でこういう質問ができるのかと、関心してしまった。
印象に残った質問では、各員会において一番ホットな議論が為されたものは? というものがあった。
結果はこの報告会でも「議会しんしろ」でも掲載されるので、その過程が知りたいというもの。
総務消防では「最近の火災の多さについて」、厚生文教では「こども園基本無償化のついての検討」、経済建設では「まちづくりの基本は観光にあり、との観点からDMOのことなど」と各委員会から回答があった。
こういう回答においては、日頃いけ好かないヤツと思っている議員さんもなかなかの弁が立ち、「しっかり仕事しているじゃないか」という印象を持ってしまうから不思議なものだ。
つまり、「良い質問」なのだろう。
他に印象的だったのは、新城南部を通る東名高速にスマートICを作ってほしいという要望について。
経済建設委員会で採択された件だが、全員が採択ではなかったと聞いている。誰が採択ではなかったのか? と、かなり強い調子で質問していた。
これは冒頭に書いたような不満を述べるというより、本気で要望しているのだという断固した決意のようなものを感じた。
結果としては採択しなかった委員はいなく、内容は採択と趣旨採択であったということ。趣旨採択をした委員さんは、豊橋との兼ね合いもありまだ議論が必要だからと説明していた。
聞いたところによると、というか、おなじみパパパさんの「パパゲーノの夢」でもこの日の様子がブログに書かれていて、
→「八名地区での議会報告会(質問のレベルが高くて驚いた)」
この質問レベルの高さの所以は「産廃問題で鍛えられているから」とのことらしい。
ここで最初の話に戻るのだが、多分八名地区では産廃問題の議論の最初の頃に不満を出し尽くしてしまったのではないのだろうか。
私たちが、質問をするようで結局不満しか言えないという段階をとうの昔にクリアして、物事を建設的に議論し現実的な解決方法を見出していく方法を体得していったように見受けられる。
しかしそのための代償が「産廃問題解決への現実的な取り組みを強要されたことによる」のならば、それは大きな皮肉のような気がする。
問題がなくては真の議論の方法は身に着けられないのだろうか。
そして八名地区の皆さんはもう一つ上の段階にも達しようとしているようにも感じる。
それは東名高速スマートICの要望は八名地域の区長の連名での要望書によるものであり、この議会報告会でもさらに強く要求されたことからだ。
地域活性化のための要望だと思うのだが、なんというかスケールがでかい。
お祭りとかのイベントをやるとかいうレベルではない。
行政が率先してやるような計画だと思うのだが、本当に地域の区長さん達からの独自の発案なのだろうかとさえ思ってしまう。
かなり妄想が入るけれども、産廃問題で思考を鍛えられて、川向うの市北部の無関心さへの反発や「もう行政に期待はしない」という独立独歩の精神が養われた末の、「スマートIC計画」ではないだろうか。
南部の皆さんの強かさや先進性に見習わなくては、というより、とまどってしまうのが正直な気持ちだ。
新庁舎建設の件、産廃問題、政倫審のことなどなど、市政に対してとにかく不満を持っている人は多いのだろう。
24日に終了した議会報告会。
特にこの議会報告会では皆さんのご不満が爆発するようだ。
何度も書くが、気持ちはよーくわかる。
私もこのブログで不満をたらたら並べ立てて日頃発散してるので(笑 あの場では黙っていられるようなものだ。
大体こういう議会報告会でもなければ、市民が市政に携わる人に何か言う機会などないのだから。
が、このご不満はよくよく聞いていればやはりご自説をぶちまけているだけで、質問にはなっていないことがよくある。
ぶちまけている方も、さてその御自説をどう終いにしようかと、最後の方では言葉を濁しがちになってしまうようだ。
きっとご自身でも言っているうちに気づくのだろう。
「オレの言ってることは質問ではないなぁ・・・」と。
これら皆さんのご意見を聞いていると、こういうご不満は出し尽くした方がよいとつくづく思う。
多分、今の新城市民には不満の噴出先が足りていない。
それら不満を出し尽くしたその先に、建設的な議論が始まるのだと思う。
先日24日に八名地区の議会報告会に行ってきた。
勝手な印象だけれども、八名地区の皆さんの質問は至って冷静だ。そして鋭い。
議会報告会でこういう質問ができるのかと、関心してしまった。
印象に残った質問では、各員会において一番ホットな議論が為されたものは? というものがあった。
結果はこの報告会でも「議会しんしろ」でも掲載されるので、その過程が知りたいというもの。
総務消防では「最近の火災の多さについて」、厚生文教では「こども園基本無償化のついての検討」、経済建設では「まちづくりの基本は観光にあり、との観点からDMOのことなど」と各委員会から回答があった。
こういう回答においては、日頃いけ好かないヤツと思っている議員さんもなかなかの弁が立ち、「しっかり仕事しているじゃないか」という印象を持ってしまうから不思議なものだ。
つまり、「良い質問」なのだろう。
他に印象的だったのは、新城南部を通る東名高速にスマートICを作ってほしいという要望について。
経済建設委員会で採択された件だが、全員が採択ではなかったと聞いている。誰が採択ではなかったのか? と、かなり強い調子で質問していた。
これは冒頭に書いたような不満を述べるというより、本気で要望しているのだという断固した決意のようなものを感じた。
結果としては採択しなかった委員はいなく、内容は採択と趣旨採択であったということ。趣旨採択をした委員さんは、豊橋との兼ね合いもありまだ議論が必要だからと説明していた。
聞いたところによると、というか、おなじみパパパさんの「パパゲーノの夢」でもこの日の様子がブログに書かれていて、
→「八名地区での議会報告会(質問のレベルが高くて驚いた)」
この質問レベルの高さの所以は「産廃問題で鍛えられているから」とのことらしい。
ここで最初の話に戻るのだが、多分八名地区では産廃問題の議論の最初の頃に不満を出し尽くしてしまったのではないのだろうか。
私たちが、質問をするようで結局不満しか言えないという段階をとうの昔にクリアして、物事を建設的に議論し現実的な解決方法を見出していく方法を体得していったように見受けられる。
しかしそのための代償が「産廃問題解決への現実的な取り組みを強要されたことによる」のならば、それは大きな皮肉のような気がする。
問題がなくては真の議論の方法は身に着けられないのだろうか。
そして八名地区の皆さんはもう一つ上の段階にも達しようとしているようにも感じる。
それは東名高速スマートICの要望は八名地域の区長の連名での要望書によるものであり、この議会報告会でもさらに強く要求されたことからだ。
地域活性化のための要望だと思うのだが、なんというかスケールがでかい。
お祭りとかのイベントをやるとかいうレベルではない。
行政が率先してやるような計画だと思うのだが、本当に地域の区長さん達からの独自の発案なのだろうかとさえ思ってしまう。
かなり妄想が入るけれども、産廃問題で思考を鍛えられて、川向うの市北部の無関心さへの反発や「もう行政に期待はしない」という独立独歩の精神が養われた末の、「スマートIC計画」ではないだろうか。
南部の皆さんの強かさや先進性に見習わなくては、というより、とまどってしまうのが正直な気持ちだ。
2017年04月26日 Posted by けま at 01:51 │Comments(0) │新城市議会
来る選挙のためにも
さて前回の記事の議員さんの浅尾議員への懲罰動議のご意見。
浅尾議員の懲罰動議は、結果としては懲罰として戒告がなされた。
その戒告文は「議会しんしろ No48」に掲載されていて、これが最終的な懲罰特別委員会の審査結果なのでこの掲載文を元に書こうと思う。
A議員が重く見たのは「特定し企業の経営状況に関する公の場での発言」について、とのことだ。
浅尾議員はこの打桐議員問題について当時議会で質問した際、打桐議員の会社の経営状況に関して具体的な評価に言及した。
この発言については私も以前に触れた(http://kemanomake.dosugoi.net/e931386.html)
浅尾議員の挙げた具体的な評価は実際根拠のあるものだったわけだから、ウソ偽りではない。
ウソ発言でなければ、では何が問題になるのか?
それは、「その発言がなければ浅尾議員の質問が成り立たないものであるかどうか」と言う点だ。
・打桐議員の会社の経営評価は低い(具体的な数字を提示)
↓
・そのような会社がなぜ入札資格を得ているのか。
超簡単に書くと上記のような筋道で浅尾議員は当時質問をしたのだが、これを下記のようにできたはずだと言うのだ。
・入札資格において会社の経営状況は考慮されるか?
↓
・例えば、○○(具体的な資料名)という会社の経営状況を報告している冊子があるが、この冊子の「警戒企業」とか「現状低迷型の最低E判定」という評価をされている会社は、新城市においては入札の資格があるか?
こんな感じ。
これだと暗に打桐議員の会社を指してはいるものの、具体的に名前を挙げてはいない。
それでいて、具体的な入札資格について回答を引き出せる質問になり得る。
(もちろん、こういう質問にハッキリ回答する新城市ではないことは十分考えられるけど)
質問するうえではこれくらいの配慮をしてほしい、というA議員のお考えなのだな。
「なるほどなぁ」という感じだ。
確かにこういう言い回しなら具体的には打桐議員の会社の経営状況に触れずに済む。
が、『 暗に 』 打桐議員の会社について言っていることはわかる。
議運がそのあたりに食いついてくる可能性は十分考えられる。なんせ「浅尾議員の過去の発言からして云々」とか言ってる議員さんもいて、浅尾議員になんとか一泡吹かせたい一心であるようにも見受けられるからだ。
と言ったところで、これは議運の持ち分でA議員には関係がない。
だからこの件では最初に「私個人の考えとしては・・・」とエクスキューズが入っている。
浅尾議員のこの質問があってから懲罰動議が為されるまでに数日あり、その間に浅尾議員に謝罪を促せなかったか? と言う件も聞いてみたがやはり「議運ではないから」と言葉を濁していた。
唐突だが、自分の記憶力の無さにガッカリしている。
他にも、例えば人事院勧告に基づく議員報酬アップの件とかも聞いたはずだが、肝心のA議員の結論はなんだったかが思い出せないでいる。
今回の話を聞く機会は、事前に色々臨む姿勢を考えてはみたのだが方向性が定まらず、その場次第の成り行き任せな感じになってしまった。
やはり聞きたいことを具体的にピックアップしておき、答えてもらいたいポイントをはっきりさせておかなくてはいけない。
さて、・・・実際に会って話を聞くと、これを「情が移る」と言うのだろうか。
どうも日頃このブログで吐いているような毒っぽさが失われてしまう。情けない限りだが。
選挙で候補者がやたらと握手してくるのも、こういう効果を狙っているんだろう。
とはいえ、議員さん個人の人となりを垣間見たことや日頃の考え方、意見を聞くことができたことは、これはこれで大変参考になったことも事実だ。
今年は市議会議員選挙が10月末にある。
新庁舎の住民投票以来市政に関心を持って眺めてきたが、産廃問題とか打桐問題、政倫審の報復合戦、議会改革に逆行するような会派結成騒ぎ、浅尾議員の懲罰動議などなど、新城市議会はゴタゴタだらけだ。
とにかく市民に、新城市に、良い働きをもって応えてくれる議員さんを選びたいものだ。
できるかどうかわからないが、また他の議員さんにも会って話を伺う機会を作ってみたいと思っている。
浅尾議員の懲罰動議は、結果としては懲罰として戒告がなされた。
その戒告文は「議会しんしろ No48」に掲載されていて、これが最終的な懲罰特別委員会の審査結果なのでこの掲載文を元に書こうと思う。
A議員が重く見たのは「特定し企業の経営状況に関する公の場での発言」について、とのことだ。
浅尾議員はこの打桐議員問題について当時議会で質問した際、打桐議員の会社の経営状況に関して具体的な評価に言及した。
この発言については私も以前に触れた(http://kemanomake.dosugoi.net/e931386.html)
浅尾議員の挙げた具体的な評価は実際根拠のあるものだったわけだから、ウソ偽りではない。
ウソ発言でなければ、では何が問題になるのか?
それは、「その発言がなければ浅尾議員の質問が成り立たないものであるかどうか」と言う点だ。
・打桐議員の会社の経営評価は低い(具体的な数字を提示)
↓
・そのような会社がなぜ入札資格を得ているのか。
超簡単に書くと上記のような筋道で浅尾議員は当時質問をしたのだが、これを下記のようにできたはずだと言うのだ。
・入札資格において会社の経営状況は考慮されるか?
↓
・例えば、○○(具体的な資料名)という会社の経営状況を報告している冊子があるが、この冊子の「警戒企業」とか「現状低迷型の最低E判定」という評価をされている会社は、新城市においては入札の資格があるか?
こんな感じ。
これだと暗に打桐議員の会社を指してはいるものの、具体的に名前を挙げてはいない。
それでいて、具体的な入札資格について回答を引き出せる質問になり得る。
(もちろん、こういう質問にハッキリ回答する新城市ではないことは十分考えられるけど)
質問するうえではこれくらいの配慮をしてほしい、というA議員のお考えなのだな。
「なるほどなぁ」という感じだ。
確かにこういう言い回しなら具体的には打桐議員の会社の経営状況に触れずに済む。
が、『 暗に 』 打桐議員の会社について言っていることはわかる。
議運がそのあたりに食いついてくる可能性は十分考えられる。なんせ「浅尾議員の過去の発言からして云々」とか言ってる議員さんもいて、浅尾議員になんとか一泡吹かせたい一心であるようにも見受けられるからだ。
と言ったところで、これは議運の持ち分でA議員には関係がない。
だからこの件では最初に「私個人の考えとしては・・・」とエクスキューズが入っている。
浅尾議員のこの質問があってから懲罰動議が為されるまでに数日あり、その間に浅尾議員に謝罪を促せなかったか? と言う件も聞いてみたがやはり「議運ではないから」と言葉を濁していた。
唐突だが、自分の記憶力の無さにガッカリしている。
他にも、例えば人事院勧告に基づく議員報酬アップの件とかも聞いたはずだが、肝心のA議員の結論はなんだったかが思い出せないでいる。
今回の話を聞く機会は、事前に色々臨む姿勢を考えてはみたのだが方向性が定まらず、その場次第の成り行き任せな感じになってしまった。
やはり聞きたいことを具体的にピックアップしておき、答えてもらいたいポイントをはっきりさせておかなくてはいけない。
さて、・・・実際に会って話を聞くと、これを「情が移る」と言うのだろうか。
どうも日頃このブログで吐いているような毒っぽさが失われてしまう。情けない限りだが。
選挙で候補者がやたらと握手してくるのも、こういう効果を狙っているんだろう。
とはいえ、議員さん個人の人となりを垣間見たことや日頃の考え方、意見を聞くことができたことは、これはこれで大変参考になったことも事実だ。
今年は市議会議員選挙が10月末にある。
新庁舎の住民投票以来市政に関心を持って眺めてきたが、産廃問題とか打桐問題、政倫審の報復合戦、議会改革に逆行するような会派結成騒ぎ、浅尾議員の懲罰動議などなど、新城市議会はゴタゴタだらけだ。
とにかく市民に、新城市に、良い働きをもって応えてくれる議員さんを選びたいものだ。
できるかどうかわからないが、また他の議員さんにも会って話を伺う機会を作ってみたいと思っている。
2017年04月15日 Posted by けま at 05:55 │Comments(0) │新城市議会
市議会議員と話してきた
とある議員さんと直接話をする機会を得て、先週土曜日に会ってきた。
こちらのブログでは浅尾議員や白井議員の記事を多く取り上げさせてもらって、それらの情報を元にいろいろ書いてきた。
でありながら、実はこのお二人とはあいさつぐらいはしたことがあるものの、直接に会う機会を得て詳しく考えを伺ったことは無い。
今回会ってきたのは、むしろ浅尾・白井議員とは対極にある議員だ。
で、感想なのだが。
自分という人間を、逆に強く意識してしまった、という感じだ。
関係ないようだが、まずこの記事。
「【速報】タナカ新城工場◆水質汚濁事故」(「山本拓哉のひとりごと」より)
→ http://takuya-y.jugem.jp/?eid=3015
見出しを読み、「タナカ興業が汚水を垂れ流したか!」 と思ったが、よくよく記事を読めば、タナカ内で工事をしている車両が入り口付近で事故を起こし、燃料の軽油が公道上に漏れ出して、黒田川に流れ込んだ、という出来事。
責任は事故を起こした会社・人にあり、タナカには関係ない、と言えそうな記事だ。
この事故にタナカを絡めるのは、印象操作に繋がるように思う。
ので、山本氏のブログに上記のようなコメントをした。(反映されないでしょうが)
私は山本氏と特に親しくもないので、どんなことでも意見として言う事に躊躇は無い。
で、この事件、コチラの方も取り上げている。
https://www.facebook.com/tooru.sugimoto.90/posts/630157740513828?pnref=story
先ほどの山本氏の記事と同じ事故の件を書いている。
かなり詳しい経過がわかるのだけれども、やはり責任は車両に直接関係する会社にあり、タナカは関係ないだろう、と思わざるを得ない。
のだけれども、こちらには私はコメントしていない。
この方を知っているからだ。
あちらは多分私のことを知らないと思う。しかし私は産廃問題はじめ、その他諸々他の人のために色々と働いている方であることを知っている。
なので、正直に言えば、知っている人に対してその人の気分を害するようなことは言いづらい、のだ。
知らない人にはケチをつけ、知っている人には遠慮するのが自分だと、そういうことだ。
なので、さらに正直言うと、今回会った議員にも言い分があるのだな、と納得する部分があってしまった、そういうことだ。
今回の国会陳情団、陳情したことでわかっているのは
1・R151BP延伸
2・新城駅バリアフリー
3・東名スマートインター
私がこのことに疑問を感じていたのは、「市民の願い」と称してこの陳情を行ったことだ。
「市民の願い」を市議会議員が言うのなら、それは市議会議員全員の総意である「議会の採決」をとっておく必要がある、と思ったのだ。
ところが1、2については、これはもうかなり前から議会でも取り上げられ周知されている課題だと、その議員(A議員としておこう)は言う。
3については白井議員のブログにあるように、委員会としては採択したが議会としてはまだ国に意見書が上げられる段階にない、という状態だった。
これもその事実を認めながら、「自分としてはその陳情については市議会の事情から反対だった」と言う。
そもそもは東京の方で今回の陳情行為とは関係のない勉強会みたいなものがあって、(この辺よく聞いていなかった)その際、国会議員と会う機会に恵まれて、結果陳情となった、という話なのだそうだ。
となると、どちらかといえば議長の日頃の言い分とこの陳情行為に加わる矛盾とか、自分の所属する委員会に一言いれずに東京に行った議員とか、こちらの方がより問題か・・・と思うようになり。
もうこうなると、自分に対して「あかんわい」、と言う感じだ。
舌鋒が鈍るとはこのことだ。
先日あった浅尾議員の懲罰動議と柴田議員の問題発言への対処の差のことなども聞いたので、次の記事に書こうと思う。
長くなったのでまずはこの辺で。
こちらのブログでは浅尾議員や白井議員の記事を多く取り上げさせてもらって、それらの情報を元にいろいろ書いてきた。
でありながら、実はこのお二人とはあいさつぐらいはしたことがあるものの、直接に会う機会を得て詳しく考えを伺ったことは無い。
今回会ってきたのは、むしろ浅尾・白井議員とは対極にある議員だ。
で、感想なのだが。
自分という人間を、逆に強く意識してしまった、という感じだ。
関係ないようだが、まずこの記事。
「【速報】タナカ新城工場◆水質汚濁事故」(「山本拓哉のひとりごと」より)
→ http://takuya-y.jugem.jp/?eid=3015
見出しを読み、「タナカ興業が汚水を垂れ流したか!」 と思ったが、よくよく記事を読めば、タナカ内で工事をしている車両が入り口付近で事故を起こし、燃料の軽油が公道上に漏れ出して、黒田川に流れ込んだ、という出来事。
責任は事故を起こした会社・人にあり、タナカには関係ない、と言えそうな記事だ。
この事故にタナカを絡めるのは、印象操作に繋がるように思う。
ので、山本氏のブログに上記のようなコメントをした。(反映されないでしょうが)
私は山本氏と特に親しくもないので、どんなことでも意見として言う事に躊躇は無い。
で、この事件、コチラの方も取り上げている。
https://www.facebook.com/tooru.sugimoto.90/posts/630157740513828?pnref=story
先ほどの山本氏の記事と同じ事故の件を書いている。
かなり詳しい経過がわかるのだけれども、やはり責任は車両に直接関係する会社にあり、タナカは関係ないだろう、と思わざるを得ない。
のだけれども、こちらには私はコメントしていない。
この方を知っているからだ。
あちらは多分私のことを知らないと思う。しかし私は産廃問題はじめ、その他諸々他の人のために色々と働いている方であることを知っている。
なので、正直に言えば、知っている人に対してその人の気分を害するようなことは言いづらい、のだ。
知らない人にはケチをつけ、知っている人には遠慮するのが自分だと、そういうことだ。
なので、さらに正直言うと、今回会った議員にも言い分があるのだな、と納得する部分があってしまった、そういうことだ。
今回の国会陳情団、陳情したことでわかっているのは
1・R151BP延伸
2・新城駅バリアフリー
3・東名スマートインター
私がこのことに疑問を感じていたのは、「市民の願い」と称してこの陳情を行ったことだ。
「市民の願い」を市議会議員が言うのなら、それは市議会議員全員の総意である「議会の採決」をとっておく必要がある、と思ったのだ。
ところが1、2については、これはもうかなり前から議会でも取り上げられ周知されている課題だと、その議員(A議員としておこう)は言う。
3については白井議員のブログにあるように、委員会としては採択したが議会としてはまだ国に意見書が上げられる段階にない、という状態だった。
これもその事実を認めながら、「自分としてはその陳情については市議会の事情から反対だった」と言う。
そもそもは東京の方で今回の陳情行為とは関係のない勉強会みたいなものがあって、(この辺よく聞いていなかった)その際、国会議員と会う機会に恵まれて、結果陳情となった、という話なのだそうだ。
となると、どちらかといえば議長の日頃の言い分とこの陳情行為に加わる矛盾とか、自分の所属する委員会に一言いれずに東京に行った議員とか、こちらの方がより問題か・・・と思うようになり。
もうこうなると、自分に対して「あかんわい」、と言う感じだ。
舌鋒が鈍るとはこのことだ。
先日あった浅尾議員の懲罰動議と柴田議員の問題発言への対処の差のことなども聞いたので、次の記事に書こうと思う。
長くなったのでまずはこの辺で。
2017年04月10日 Posted by けま at 10:54 │Comments(0) │新城市議会
「議員提出第1号議案」の件で考えたこと
「情報」にはそれを伝える人の意思が働いている、と考えていいだろう。
伝える人にとって都合よく「情報」を改変して、つまりウソの情報にして伝えるなんてこともあり得る。
ウソ情報はちょっと困る。
真実かどうかのウラを取るのが、我々一般市民には困難なことが多いからだ。
が、これはそのうち自然に淘汰されるだろう。オオカミ少年の言う事をそのうち誰も聞かなくなることと同じだ。
情報を伝えることが仕事の中で重要な位置を占めるような人がウソをつけば、たちまち仕事を失うだろう。
では立場上ウソをつけない人が、自分の意思を「情報」に加味させたいときにはどうしたらよいか。
『10ある情報のうち、5くらいしか伝えない。』
コレだろう。
ウソを伝えてはいない。但し自分にとって不都合なことは伝えない。
・「議員報酬は変わらない」
・「期末手当の支給率を変更する」
・「現在の支給率は人事院勧告に基づいている」
今回の「議員提出第1号議案」についての長田議員の説明はコレだ。
上に挙げた情報はどれもウソではない。
で、この情報からだと、
「給料が上がるわけではないし、」
「“率”つまり幾らか変更(多分上げるんだろうけど数パーセントか)するんだけど実額は少ないかもしれんし、」
「人事院勧告(なにやら難しいがお国の基準だろうか)とやらが基になっているなら、まぁいいか。」
と思わせたいのではなかろうかという、長田議員の意思がプンプン臭う。
実際はどうかというと、
・「支給は昨年12月に遡る」
・「新城市特別職報酬等審議会(市議のような特別職の報酬が適正かどうか審議する会)は昨年12月27日に『報酬は据え置きが妥当』という答申を出している」
・・「人事院勧告は国の行政一般職の給与について勧告であって、特別職の報酬とは無関係」
・・「勧告に必ずしも従う必要はない」
これらの情報もウソではないが、本来なら先に挙げた情報と同時に伝えられるべきものだ。
しかしこれらも同時伝えると、
「なんで昨年の手当にも適用されるんだ」
「新城市特別職報酬等審議会が『据え置き』と言っているのになんで上げるんだ」
「従う必要もなく、市議の報酬とはなんの関係もない勧告に基づく必要はない」
と思われてしまうので、そういう事は避けたいという長田議員の意思がブリブリ臭う。
情報というものは基本的には信じてよい、というか我々一般市民は信じるほかないところがある。(ウソを見抜くのは困難だから)
しかし、知らされた情報が、その情報の『全て』ではない。
私たち市民は、これを肝に銘じなければならないだろう。
そして付け加えるならば、やはり日頃情報の理解のための勉強も習慣としたい。
今回の件で言えば「人事院勧告」。
勉強といっても難しく考えることはなく、ちょいとググる、つまりインターネットで検索すればよい。
「人事院勧告」を検索すると、なにやら難しい項目がたくさん出てくるが我々素人ならば「ウィキペディア」での記事を読むのが一番わかりやすい。
最初の数行を読むと「・・国家公務員の一般職職員・・」という語句に気づく。
上から目線と思われると恐縮だが、ここで
『市議会議員って一般職か?』
『国家公務員の一般職職員って、新城市なら市の職員さんと同じ感じか?』
という具合に、さらに疑問が湧くようになることが肝要だ。
そしてさらに検索して何かがわかって、そこからさらに疑問が湧いて・・を繰り返すと人事院勧告が市議の報酬に関係ないことがわかってくる。
この知識があれば、「現在の支給率は人事院勧告に基づいている」はウソではないが、そもそも「基づいている」ことがおかしいことに気づく。
そして市議会議員サマであろうものが、おかしなことをしていることに気づいていない様子がわかる。
その「気づいていない様子」を見ている我々市民は、
1・知らなくてやっているなら頭悪いので次の選挙では落とさなくちゃいけないし、
2・知っていてやっているなら相当な悪なので次の選挙で落とさなくちゃいけない。
どっちにしろ落選させないといけない議員が13名いることはハッキリする。
と、斯様に知識を身に着けることは議員サマの資質を判断することに非常に役に立つ。
情報を伝える議員の意思に惑わされないように、逆に彼らの資質を判断するために、情報の受け取り方をしっかり考えよう。
伝える人にとって都合よく「情報」を改変して、つまりウソの情報にして伝えるなんてこともあり得る。
ウソ情報はちょっと困る。
真実かどうかのウラを取るのが、我々一般市民には困難なことが多いからだ。
が、これはそのうち自然に淘汰されるだろう。オオカミ少年の言う事をそのうち誰も聞かなくなることと同じだ。
情報を伝えることが仕事の中で重要な位置を占めるような人がウソをつけば、たちまち仕事を失うだろう。
では立場上ウソをつけない人が、自分の意思を「情報」に加味させたいときにはどうしたらよいか。
『10ある情報のうち、5くらいしか伝えない。』
コレだろう。
ウソを伝えてはいない。但し自分にとって不都合なことは伝えない。
・「議員報酬は変わらない」
・「期末手当の支給率を変更する」
・「現在の支給率は人事院勧告に基づいている」
今回の「議員提出第1号議案」についての長田議員の説明はコレだ。
上に挙げた情報はどれもウソではない。
で、この情報からだと、
「給料が上がるわけではないし、」
「“率”つまり幾らか変更(多分上げるんだろうけど数パーセントか)するんだけど実額は少ないかもしれんし、」
「人事院勧告(なにやら難しいがお国の基準だろうか)とやらが基になっているなら、まぁいいか。」
と思わせたいのではなかろうかという、長田議員の意思がプンプン臭う。
実際はどうかというと、
・「支給は昨年12月に遡る」
・「新城市特別職報酬等審議会(市議のような特別職の報酬が適正かどうか審議する会)は昨年12月27日に『報酬は据え置きが妥当』という答申を出している」
・・「人事院勧告は国の行政一般職の給与について勧告であって、特別職の報酬とは無関係」
・・「勧告に必ずしも従う必要はない」
これらの情報もウソではないが、本来なら先に挙げた情報と同時に伝えられるべきものだ。
しかしこれらも同時伝えると、
「なんで昨年の手当にも適用されるんだ」
「新城市特別職報酬等審議会が『据え置き』と言っているのになんで上げるんだ」
「従う必要もなく、市議の報酬とはなんの関係もない勧告に基づく必要はない」
と思われてしまうので、そういう事は避けたいという長田議員の意思がブリブリ臭う。
情報というものは基本的には信じてよい、というか我々一般市民は信じるほかないところがある。(ウソを見抜くのは困難だから)
しかし、知らされた情報が、その情報の『全て』ではない。
私たち市民は、これを肝に銘じなければならないだろう。
そして付け加えるならば、やはり日頃情報の理解のための勉強も習慣としたい。
今回の件で言えば「人事院勧告」。
勉強といっても難しく考えることはなく、ちょいとググる、つまりインターネットで検索すればよい。
「人事院勧告」を検索すると、なにやら難しい項目がたくさん出てくるが我々素人ならば「ウィキペディア」での記事を読むのが一番わかりやすい。
最初の数行を読むと「・・国家公務員の一般職職員・・」という語句に気づく。
上から目線と思われると恐縮だが、ここで
『市議会議員って一般職か?』
『国家公務員の一般職職員って、新城市なら市の職員さんと同じ感じか?』
という具合に、さらに疑問が湧くようになることが肝要だ。
そしてさらに検索して何かがわかって、そこからさらに疑問が湧いて・・を繰り返すと人事院勧告が市議の報酬に関係ないことがわかってくる。
この知識があれば、「現在の支給率は人事院勧告に基づいている」はウソではないが、そもそも「基づいている」ことがおかしいことに気づく。
そして市議会議員サマであろうものが、おかしなことをしていることに気づいていない様子がわかる。
その「気づいていない様子」を見ている我々市民は、
1・知らなくてやっているなら頭悪いので次の選挙では落とさなくちゃいけないし、
2・知っていてやっているなら相当な悪なので次の選挙で落とさなくちゃいけない。
どっちにしろ落選させないといけない議員が13名いることはハッキリする。
と、斯様に知識を身に着けることは議員サマの資質を判断することに非常に役に立つ。
情報を伝える議員の意思に惑わされないように、逆に彼らの資質を判断するために、情報の受け取り方をしっかり考えよう。