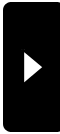最後の市民自治会議
2月9日、平成28年度第10回の市民自治会議があり出席してきた。
次回の3月1日に市長に答申をして今年度の市民自治会議が全て終了となるのだが、その日は答申文書を市長に渡すだけのセレモニーなので、実質的な会議は今回が最後となった。
私もこれで2年の任期を終えることになった。
振り返ってみれば、色々と勉強になった2年間だった。
市民自治に関係する情報や行事などは、他に先駆けて知ることができたり、詳しい資料を頂けたりして、市政に興味を持っている自分としては大変有り難いモノだった。
おかげで今までなら絶対参加しなかったであろう市のイベントにも多く参加することができた。
こちらのブログでも市民自治会議での議題に触発されて記事にしたものも多い。
この委員に応募する際にはその動機を短い文章にする必要がある。
「市政の情報発信を素早く正確にわかりやすくやってほしい」というのが、今も変わらない市政への一番の注文で、これを動機として応募したことが思い起こされる。
が、この会議は自治基本条例が機能しているかをチェックすることがその役割で、こちらから積極的に提案をするというより、毎回提供される議題や報告に意見をすることに重きが置かれているようだった。
ま、私が勝手に勘違いしていただけのことなのだが(^_^;)、欲を言えば提案が通らなくとも自由討論みたいな感じで自論を披露できたらよかったと思っている。
委員になってからは市のHPをよく見るようになり、過去のイベントや会議の資料を多く読むようになった。
で、気づいた事なのだが、この2年間で一緒に委員をやった皆さん、まちづくり集会などの市のイベントで見かける皆さん、この人たちの名前を資料の中によく見かけるのだ。
つまり、市民自治に参加してくれている皆さんの顔ぶれというのは、大体いつも同じようなものばかりなのだなw。
要領を得た人に何回も役を担ってもらうのがよいのか、なるべく初めての方にやってもらうのがよいのか。
市民自治のすそ野の拡がりを期待するなら、色んな世代の方々がなるべく多く係わる方が良いはずだけれども、そういう方々は多分「広報ほのか」とか市のHPをあまり見ない(と思う)。
そういうとこにしか情報が置いてないから、市民自治方面に特に関心が無ければまず気づかない。
結局、以前経験した方たちにお願いすることになる、という負のスパイラル。
やっぱり「市政の情報発信を素早く正確にわかりやすくやってほしい」し、「誰もが目にする(気付くことができる)カタチで情報発信する」ということも大事なんだろうな。
おかげさまでこの2年間で一番多く目を通したと思う「新城市自治基本条例」。
読むたびに常に疑問が増していったのは、このブログでも何回か書いた「“自治”と“まちづくり”の違い」だ。
自治は文字通り「自ら治める」。
「市民自治」ならば、市民が市政を自主的に営んでいくこと、と言っていいだろう。
例えば、若者議会や女性議会、盆ダンスとか新城ラリー。
緊急に必要なモノ、とは言えないだろうと考えている。
しかし若者や女性が市政に関わりを持っていくことは将来的には大きな実りをもたらすだろうし、盆ダンスや市城ラリーはイベントとして市民が楽しめるものだし、運営に市民が携われば「我ら新城市民!」的な一体感も味わえるこれまた実りのあるものだろう。
そして例えば、市南部の産廃問題、少し前なら新庁舎建設問題。
今現在苦しんでいる人たちがいる故に解決の緊急性の高いモノだが、解決できたからと言ってマイナスに傾いていた生活が今までの日常を取り戻すだけのことだ。心配事が無くなるだけで、先に挙げたような「実り」は無い。
このようなこと、つまり「実りのあること」にも「実りは無く日常を取り戻すだけのこと」にも市民が自らの課題として取り組むのが「市民自治」と言うのだ、と私は考えている。
新城市自治基本条例の第1条はこうだ。
「この条例は、新城市のまちづくりに関する基本的な理念並びに市民、議会及び行政の役割及び仕組みを明らかにすることにより、市民が主役のまちづくりを推進し、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちを協働してつくることを目的とします。」
『「自治」とは「まちづくり」のことなんです!』、と言っていいだろう。
だったら「新城市まちづくり基本条例」という名称にすればよかったんじゃないか?
なぜ題名に「自治」と付けておきながら、その第1条に「自治」の文字がひとつもないのだろう?
「まちづくり」という言葉には「積極的に何かを作り出す」とか「ポジティブな取組み」というイメージがある。
新城市自治基本条例を根拠にしている「若者議会、女性議会」「地域自治区」などはまさに「まちづくり」のための産物であって、積極的な予算付けが為されているのは御存知の通りだ。
一方、「市南部の産廃問題、新庁舎建設問題」などを解決するためには、この「新城市自治基本条例」をどう活用すればいいのだろう?
ネックとなるのは「協働」という言葉ではないだろうか。
第2条には条例内で使う言葉の定義が書いてあり、その中に「協働」という言葉がある。
「(6)協働 市民同士又は市民、議会及び行政が対等な関係で協力及び連携し、まちづくりを行うことをいいます。」
ちなみに他にも「住民」「市民」「市」「行政」「まちづくり」「行政区等」という言葉も定義されている。
まず産廃業者が「市民」の定義に当てはまらず、どうしても生活をおびやかされる地域住民とは対立してしまう構造になってしまう。
なので地域住民=「市民」または「住民」と「市」・「行政」が連携して対処しなければならないのだが、どうも「市」・「行政」が積極的でない。
新庁舎建設でもそうだ。
「市民」が建設費を見直してほしいと言っても、当初「市」「行政」は取り上げてくれなく、仕方なく住民投票に至ってしまった。
「協働」ではなく対立する構造ができてしまった。
「市民」が「これは問題ではないか?」と思い、それを自らの手で解決しようとすることは私は立派な「自治」だと思うのだが、「市」や「行政」がそれに連携してくれようとしないのはなぜか。
「自治」の中に「協働」できないことがあり、特に何かと対立してしまう構造になるともうそれは「まちづくり」ではない、と判断されてしまう感じだ。
それならそれで先にも書いたように「新城市まちづくり基本条例」にしてしまえばいいと思うのだ。
私がなぜ名前に拘ってしまうかと言えば、自治というには片落ちな「新城市自治基本条例」が対外的に「マニフェスト大賞」とかいう賞を取ってしまうと、新城市では市内の様々な問題全てに「自治=市民が自ら問題に取り組んでいる」と思われしまうことを危惧するからだ。
「自治」なんて新城市では半分しか機能していないのに、市外のみなさんに「新城市は市民自治が進んでますなぁ」とか言われて市長やら市議がニヤニヤ笑っているその裏で、住民投票にまで至ったことや産廃業者に苦しい思いをしている住民のみなさんの苦労が隠れている現実をその市長や市議が見ようとしないことに腹が立ってくる。
「まちづくり基本条例」という名前で若者議会や地域自治区の取り組みが評価されて賞を取るなら、それは名前と取組みとの間になんら矛盾は無く「表彰されてよかったね」と文句なく評価できるのだが。
最後がかなり長くなってしまったが、これで市民自治会議委員の任期も終わった。
もうこの任に就くことはないけれども、引き続き市政ウオッチは続けていきたい。
次回の3月1日に市長に答申をして今年度の市民自治会議が全て終了となるのだが、その日は答申文書を市長に渡すだけのセレモニーなので、実質的な会議は今回が最後となった。
私もこれで2年の任期を終えることになった。
振り返ってみれば、色々と勉強になった2年間だった。
市民自治に関係する情報や行事などは、他に先駆けて知ることができたり、詳しい資料を頂けたりして、市政に興味を持っている自分としては大変有り難いモノだった。
おかげで今までなら絶対参加しなかったであろう市のイベントにも多く参加することができた。
こちらのブログでも市民自治会議での議題に触発されて記事にしたものも多い。
この委員に応募する際にはその動機を短い文章にする必要がある。
「市政の情報発信を素早く正確にわかりやすくやってほしい」というのが、今も変わらない市政への一番の注文で、これを動機として応募したことが思い起こされる。
が、この会議は自治基本条例が機能しているかをチェックすることがその役割で、こちらから積極的に提案をするというより、毎回提供される議題や報告に意見をすることに重きが置かれているようだった。
ま、私が勝手に勘違いしていただけのことなのだが(^_^;)、欲を言えば提案が通らなくとも自由討論みたいな感じで自論を披露できたらよかったと思っている。
委員になってからは市のHPをよく見るようになり、過去のイベントや会議の資料を多く読むようになった。
で、気づいた事なのだが、この2年間で一緒に委員をやった皆さん、まちづくり集会などの市のイベントで見かける皆さん、この人たちの名前を資料の中によく見かけるのだ。
つまり、市民自治に参加してくれている皆さんの顔ぶれというのは、大体いつも同じようなものばかりなのだなw。
要領を得た人に何回も役を担ってもらうのがよいのか、なるべく初めての方にやってもらうのがよいのか。
市民自治のすそ野の拡がりを期待するなら、色んな世代の方々がなるべく多く係わる方が良いはずだけれども、そういう方々は多分「広報ほのか」とか市のHPをあまり見ない(と思う)。
そういうとこにしか情報が置いてないから、市民自治方面に特に関心が無ければまず気づかない。
結局、以前経験した方たちにお願いすることになる、という負のスパイラル。
やっぱり「市政の情報発信を素早く正確にわかりやすくやってほしい」し、「誰もが目にする(気付くことができる)カタチで情報発信する」ということも大事なんだろうな。
おかげさまでこの2年間で一番多く目を通したと思う「新城市自治基本条例」。
読むたびに常に疑問が増していったのは、このブログでも何回か書いた「“自治”と“まちづくり”の違い」だ。
自治は文字通り「自ら治める」。
「市民自治」ならば、市民が市政を自主的に営んでいくこと、と言っていいだろう。
例えば、若者議会や女性議会、盆ダンスとか新城ラリー。
緊急に必要なモノ、とは言えないだろうと考えている。
しかし若者や女性が市政に関わりを持っていくことは将来的には大きな実りをもたらすだろうし、盆ダンスや市城ラリーはイベントとして市民が楽しめるものだし、運営に市民が携われば「我ら新城市民!」的な一体感も味わえるこれまた実りのあるものだろう。
そして例えば、市南部の産廃問題、少し前なら新庁舎建設問題。
今現在苦しんでいる人たちがいる故に解決の緊急性の高いモノだが、解決できたからと言ってマイナスに傾いていた生活が今までの日常を取り戻すだけのことだ。心配事が無くなるだけで、先に挙げたような「実り」は無い。
このようなこと、つまり「実りのあること」にも「実りは無く日常を取り戻すだけのこと」にも市民が自らの課題として取り組むのが「市民自治」と言うのだ、と私は考えている。
新城市自治基本条例の第1条はこうだ。
「この条例は、新城市のまちづくりに関する基本的な理念並びに市民、議会及び行政の役割及び仕組みを明らかにすることにより、市民が主役のまちづくりを推進し、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちを協働してつくることを目的とします。」
『「自治」とは「まちづくり」のことなんです!』、と言っていいだろう。
だったら「新城市まちづくり基本条例」という名称にすればよかったんじゃないか?
なぜ題名に「自治」と付けておきながら、その第1条に「自治」の文字がひとつもないのだろう?
「まちづくり」という言葉には「積極的に何かを作り出す」とか「ポジティブな取組み」というイメージがある。
新城市自治基本条例を根拠にしている「若者議会、女性議会」「地域自治区」などはまさに「まちづくり」のための産物であって、積極的な予算付けが為されているのは御存知の通りだ。
一方、「市南部の産廃問題、新庁舎建設問題」などを解決するためには、この「新城市自治基本条例」をどう活用すればいいのだろう?
ネックとなるのは「協働」という言葉ではないだろうか。
第2条には条例内で使う言葉の定義が書いてあり、その中に「協働」という言葉がある。
「(6)協働 市民同士又は市民、議会及び行政が対等な関係で協力及び連携し、まちづくりを行うことをいいます。」
ちなみに他にも「住民」「市民」「市」「行政」「まちづくり」「行政区等」という言葉も定義されている。
まず産廃業者が「市民」の定義に当てはまらず、どうしても生活をおびやかされる地域住民とは対立してしまう構造になってしまう。
なので地域住民=「市民」または「住民」と「市」・「行政」が連携して対処しなければならないのだが、どうも「市」・「行政」が積極的でない。
新庁舎建設でもそうだ。
「市民」が建設費を見直してほしいと言っても、当初「市」「行政」は取り上げてくれなく、仕方なく住民投票に至ってしまった。
「協働」ではなく対立する構造ができてしまった。
「市民」が「これは問題ではないか?」と思い、それを自らの手で解決しようとすることは私は立派な「自治」だと思うのだが、「市」や「行政」がそれに連携してくれようとしないのはなぜか。
「自治」の中に「協働」できないことがあり、特に何かと対立してしまう構造になるともうそれは「まちづくり」ではない、と判断されてしまう感じだ。
それならそれで先にも書いたように「新城市まちづくり基本条例」にしてしまえばいいと思うのだ。
私がなぜ名前に拘ってしまうかと言えば、自治というには片落ちな「新城市自治基本条例」が対外的に「マニフェスト大賞」とかいう賞を取ってしまうと、新城市では市内の様々な問題全てに「自治=市民が自ら問題に取り組んでいる」と思われしまうことを危惧するからだ。
「自治」なんて新城市では半分しか機能していないのに、市外のみなさんに「新城市は市民自治が進んでますなぁ」とか言われて市長やら市議がニヤニヤ笑っているその裏で、住民投票にまで至ったことや産廃業者に苦しい思いをしている住民のみなさんの苦労が隠れている現実をその市長や市議が見ようとしないことに腹が立ってくる。
「まちづくり基本条例」という名前で若者議会や地域自治区の取り組みが評価されて賞を取るなら、それは名前と取組みとの間になんら矛盾は無く「表彰されてよかったね」と文句なく評価できるのだが。
最後がかなり長くなってしまったが、これで市民自治会議委員の任期も終わった。
もうこの任に就くことはないけれども、引き続き市政ウオッチは続けていきたい。
2017年02月11日 Posted by けま at 11:03 │Comments(0) │市民自治会議
【自治基本条例ってなんだ?】
今回もお知らせ。
「おくみかわ市民政策研究所」さん主催のイベント。
(https://www.facebook.com/siminthinktank.okumikawa/)
『そもそも研究①』のお題は【自治基本条例ってなんだ?】
→https://www.facebook.com/events/1854795211463578/
私が新城市で市民自治会議の委員をやっていることから興味が湧いた。
新城市にも自治基本条例があって、この前あった「市民まちづくり集会」や「若者議会」や「地域自治区」、私の参加している「市民自治会議」などは、この自治基本条例が具体的なカタチになったものと考えていい。
「条例である以上、書かれていることは執行しなければならない」というのが行政の「執行権」とかいう使命みたいなモノで、先に書いた具体的なカタチがキチンとカタチになっているのも行政の頑張りが大きい、と感じている。
「自治」と言いながら、頑張っているのは行政、と私は感じているのだが、他の市民の皆さんはどう思っているのだろう?
自分の住んでる地域の事をなかなか客観的に見ることができない。
ひよっとしたら今現在の新城市の自治基本条例は実に良く機能している、と他の地域の人は見るのかもしれない。
決して新城市の良い評価をもらいたいのではなく、新城市“外”の目で見た評価を知りたいと思っている。
このイベントで新しい気づきが得られたらよいなぁ。
「おくみかわ市民政策研究所」さん主催のイベント。
(https://www.facebook.com/siminthinktank.okumikawa/)
『そもそも研究①』のお題は【自治基本条例ってなんだ?】
→https://www.facebook.com/events/1854795211463578/
私が新城市で市民自治会議の委員をやっていることから興味が湧いた。
新城市にも自治基本条例があって、この前あった「市民まちづくり集会」や「若者議会」や「地域自治区」、私の参加している「市民自治会議」などは、この自治基本条例が具体的なカタチになったものと考えていい。
「条例である以上、書かれていることは執行しなければならない」というのが行政の「執行権」とかいう使命みたいなモノで、先に書いた具体的なカタチがキチンとカタチになっているのも行政の頑張りが大きい、と感じている。
「自治」と言いながら、頑張っているのは行政、と私は感じているのだが、他の市民の皆さんはどう思っているのだろう?
自分の住んでる地域の事をなかなか客観的に見ることができない。
ひよっとしたら今現在の新城市の自治基本条例は実に良く機能している、と他の地域の人は見るのかもしれない。
決して新城市の良い評価をもらいたいのではなく、新城市“外”の目で見た評価を知りたいと思っている。
このイベントで新しい気づきが得られたらよいなぁ。
2017年01月27日 Posted by けま at 00:33 │Comments(0) │市民自治会議
平成28年度 千郷地域意見交換会
10月24日、千郷地域意見交換会に行ってきた。
昨年に続き今回で2回目。
前回はこの意見交換会の直前に行われる「地域協議会」も傍聴してから参加したことを思い出した。
この直前の「地域協議会」では、意見交換会で建議する内容はもう完全に出来上がっていて、委員全員で最後の確認をしただけだった。
ま、あと30分で意見交換会が始まるってのに変更なんてあるはずがない。
そして、これは今回の意見交換会で「そういうことか・・」と腑に落ちたことなのだけど、協議会の会長さんが委員さんたちに「積極的に挙手して意見してくださいね」と言っていたこと。
意見交換会と言っても、一般の人たちは、挙手して、立って、意見を言うのもなかなかハードルが高い。
一年かけて地域の課題について意見を述べ合ってきた委員さんたちの方が発言しやすいだろうし、大体発言が無ければ「意見交換会」が盛り上がらない(笑、って感じだったのだろう。
今回も協議会委員さんたちがまずは率先して意見を述べていた。
千郷小、中学校の施設修繕のこと、臼子地区の第二東名開通による騒音問題、その他環境への影響のこと、地域こども園の草刈・駐車場メンテナンスなどが園によって偏りがあること、横浜ゴム南側道路の舗装問題のこと等など。
これらについては市長がまずは回答し、細かいことを市民席横にズラッと控えている市のエラい人たちが答える、という図式で会は進んだ。
歯切れの悪い回答もあるのだが、それでも資料を捲りめくり答えるエラい人たちも大変だなぁと思いつつも、これらの問題って、つまり今回の意見交換会冒頭で建議されてることなんじゃないの?とも思った。
地域の課題を解決するのもひとつの目的として、地域協議会は4月からこの日まで協議を続けてきた。
じゃあ今、この場で出ている地域課題って一体なんなのだろう?
例えばその課題が今日建議された中にあったとしたら、その場での市長の鶴の一声で解決できるぐらいのことを協議会でわざわざ話し合ってきたということになるのか?
ではあるまい。
そんな協議会のメンツをつぶすようなことを市がやってしまっては、地域協議会委員のヤル気を大きく削いでしまう。
と考えれば、これはもうひとつのパフォーマンスだ。
市長が直接回答する、という「市長は市民の声に耳を傾けていますよ」パフォーマンス。
エラい人が直接その場で回答する、という「市職員はその場で回答できるくらい有能で、真摯に課題解決に努めてます」パフォーマンス。
全て事前に今年の建議が市には伝わっていて、意見する委員さんも決まっていて(委員さんの中にはこんな出来レースに不満もお持ちの方もいるかもしれない)、回答のやり方も決まっている、というね。
なんて風に見えてくると、心なしか今年の意見交換会はなんだか活気が無いように感じた。
昨年はもう少し活気があるように感じたのだけれども、こんなヤラセっぽい雰囲気を皆さんも感じたのだろうか。
マトモに考えるなら、意見交換会は4月か5月の年度初めにやるべきだろう。
地域協議会のその年度のスタート時に地域のナマの声を拾い上げて、その場で市として対応できることは回答してもらって、残った重要な提案は地域協議会において10月の建議まで話し合うとすればどうだろうか。
そして10月の意見交換会は、「年度初めに提案してもらった課題をこんな風に解決するカタチで予算を付けました」という報告会にしては?
で、私のブログではくどいように言っているけれども、その話し合いの過程を随時市のHPにアップして「見える化」してほしい。
傍聴もできるよう、会議の日程も事前にインフォメーションしてほしい。
市民・住民が自治に参加している実感を持ってもらうことは重要な事だろう。
意見交換会の見直しや、協議会の「見える化」、ぜひやってほしい。
昨年に続き今回で2回目。
前回はこの意見交換会の直前に行われる「地域協議会」も傍聴してから参加したことを思い出した。
この直前の「地域協議会」では、意見交換会で建議する内容はもう完全に出来上がっていて、委員全員で最後の確認をしただけだった。
ま、あと30分で意見交換会が始まるってのに変更なんてあるはずがない。
そして、これは今回の意見交換会で「そういうことか・・」と腑に落ちたことなのだけど、協議会の会長さんが委員さんたちに「積極的に挙手して意見してくださいね」と言っていたこと。
意見交換会と言っても、一般の人たちは、挙手して、立って、意見を言うのもなかなかハードルが高い。
一年かけて地域の課題について意見を述べ合ってきた委員さんたちの方が発言しやすいだろうし、大体発言が無ければ「意見交換会」が盛り上がらない(笑、って感じだったのだろう。
今回も協議会委員さんたちがまずは率先して意見を述べていた。
千郷小、中学校の施設修繕のこと、臼子地区の第二東名開通による騒音問題、その他環境への影響のこと、地域こども園の草刈・駐車場メンテナンスなどが園によって偏りがあること、横浜ゴム南側道路の舗装問題のこと等など。
これらについては市長がまずは回答し、細かいことを市民席横にズラッと控えている市のエラい人たちが答える、という図式で会は進んだ。
歯切れの悪い回答もあるのだが、それでも資料を捲りめくり答えるエラい人たちも大変だなぁと思いつつも、これらの問題って、つまり今回の意見交換会冒頭で建議されてることなんじゃないの?とも思った。
地域の課題を解決するのもひとつの目的として、地域協議会は4月からこの日まで協議を続けてきた。
じゃあ今、この場で出ている地域課題って一体なんなのだろう?
例えばその課題が今日建議された中にあったとしたら、その場での市長の鶴の一声で解決できるぐらいのことを協議会でわざわざ話し合ってきたということになるのか?
ではあるまい。
そんな協議会のメンツをつぶすようなことを市がやってしまっては、地域協議会委員のヤル気を大きく削いでしまう。
と考えれば、これはもうひとつのパフォーマンスだ。
市長が直接回答する、という「市長は市民の声に耳を傾けていますよ」パフォーマンス。
エラい人が直接その場で回答する、という「市職員はその場で回答できるくらい有能で、真摯に課題解決に努めてます」パフォーマンス。
全て事前に今年の建議が市には伝わっていて、意見する委員さんも決まっていて(委員さんの中にはこんな出来レースに不満もお持ちの方もいるかもしれない)、回答のやり方も決まっている、というね。
なんて風に見えてくると、心なしか今年の意見交換会はなんだか活気が無いように感じた。
昨年はもう少し活気があるように感じたのだけれども、こんなヤラセっぽい雰囲気を皆さんも感じたのだろうか。
マトモに考えるなら、意見交換会は4月か5月の年度初めにやるべきだろう。
地域協議会のその年度のスタート時に地域のナマの声を拾い上げて、その場で市として対応できることは回答してもらって、残った重要な提案は地域協議会において10月の建議まで話し合うとすればどうだろうか。
そして10月の意見交換会は、「年度初めに提案してもらった課題をこんな風に解決するカタチで予算を付けました」という報告会にしては?
で、私のブログではくどいように言っているけれども、その話し合いの過程を随時市のHPにアップして「見える化」してほしい。
傍聴もできるよう、会議の日程も事前にインフォメーションしてほしい。
市民・住民が自治に参加している実感を持ってもらうことは重要な事だろう。
意見交換会の見直しや、協議会の「見える化」、ぜひやってほしい。
2016年10月29日 Posted by けま at 08:21 │Comments(2) │市民自治会議│市政を考える
第8回新城市市民自治会議 2
市民自治会議からの「第二次総合計画」へのアプローチはどのようにしたらよいのか?
市民自治課と議長の鈴木誠先生からは「自治基本条例の第4条を今後どのようにしたらいいか?という観点で各委員は意見交換してほしい」と、あらかじめ通達があった。
自治基本条例第4条はこんな条文。
第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1)市民主役の原則 市民一人ひとりが主役となってまちづくりを進めます。
(2)参加協働の原則 市民、議会及び行政は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。
(3)情報共有の原則 市民、議会及び行政は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。
色んな意見が出た。 私的に気になったご意見を書いてみよう。
・圧倒的に多いのは若者も含めて現役で働いている世代。この世代が市民自治に参加しやすい環境をつくるが大切ではないか。例えば市民自治に関する会議やイベントに参加・出席することが会社(勤務先)での評価に繋がる、など。市民自治参加への「会社の理解」、「社会の理解」が必要ではないか。
この時の会議でも全参加者10名中7名は学生、主婦、リタイア世代。(ちなみに女性は4名)
女性議会、若者議会と叫ばれるが、叫んでいるのは行政側で、このご意見のような現役世代からの声は意外に聞かない。
「自治参加が勤務先での評価に繋がれば」というご意見は、なかなかの慧眼だ。
本人の意思があっても、会社などの環境がなかなか許さないのが勤め人の現状だ。「市民自治」を掲げる新城市ならば、積極的に社員の自治参加を促すよう企業に働きかけるのも大事だろう。
・基本原則はよくできている。新庁舎に関する住民投票もこの基本原則がうまく機能していれば起こりえなかったのでは?例えば「(3)情報共有の原則」。行政、市民との情報共有のギャップがひとつの原因だったのでは?基本原則が効果的に機能しているかを考えなければならない。
市民自治会議ではすでに片付いた事になっている「新庁舎に関する住民投票」がこの場で出てきたことに、まずは驚いた。
新城市においては「住民投票」は自治基本条例に組み込まれているが、その際にいつも問題になるのは住民投票実施に至るまでのハードルが高い、という仕組み・手続き的な面だ。
このご意見は、まちづくり基本原則からあの「住民投票」を検証することで、第4条が効果的に機能するための経験則が得られないか? という意味であろうと受け取った。
これもなかなかのご慧眼だ。
今でもあの住民投票については、経緯や結果、事前に行われたまちづくり集会での各陣営の扱いとか、疑問はあるけれども、それらはひとまず置いておいて、まちづくり基本原則に照らし合わせてあの住民投票を考えてみるのはイイかもしれない。
この「第4条、まちづくり基本原則」は今回改めて読み直してみて、確かによくできているなぁと感じている。
若者議会、女性議会、まちづくり集会や地域自治区、市長のやること、議会のやること、全てこの「まちづくり基本原則」に照らし合わせて評価してみるとおもしろいだろう。
他にも色々な意見が出て、久々に面白いと感じた市民自治会議だった。
この意見交換が「第二次総合計画」の策定に役立ってもらえればうれしいことだ。
最後に、私はこんなことを意見しました。
前回の会議後、疑問点があったので8月3日に市に質問メールをしたが返信がなかった。9月26日に再度同じ内容でメールしたが、これも返信がなかった。(ちなみにこの会議の日の午後に返信が来ていたが気づかずw) これは(1)市民主役の原則に冷や水を浴びせるような行為で、市民が市政に参加すべく勇気を出してメールしたものを無視するのは著しく市民のヤル気を失せさせる行為だ。まちづくりのための仕組みは自治基本条例にあるこの基本原則をはじめ、若者議会や女性議会、地域自治区などよいものが整えられつつあるが、それを運用する「人間」も整備が必要だ。聞けば市民自治課の職員さんは午後3時から9時近くまで、若者議会の会議につきあっているらしい。そういう仕事の大変さに比べて職員数が少なすぎないだろうか。そして先ほど挙げた市民への対応の仕方の悪さ。「市民自治」を掲げる新城市ならば、今後の市民自治進展のために職員数の充実、質の充実を図るべきだろう。
と、述べさせていただいた。
実際は早口でまとまりのない、多分聞き取りにくい意見だったろうと思うw 反省。
市民自治課と議長の鈴木誠先生からは「自治基本条例の第4条を今後どのようにしたらいいか?という観点で各委員は意見交換してほしい」と、あらかじめ通達があった。
自治基本条例第4条はこんな条文。
第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1)市民主役の原則 市民一人ひとりが主役となってまちづくりを進めます。
(2)参加協働の原則 市民、議会及び行政は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。
(3)情報共有の原則 市民、議会及び行政は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。
色んな意見が出た。 私的に気になったご意見を書いてみよう。
・圧倒的に多いのは若者も含めて現役で働いている世代。この世代が市民自治に参加しやすい環境をつくるが大切ではないか。例えば市民自治に関する会議やイベントに参加・出席することが会社(勤務先)での評価に繋がる、など。市民自治参加への「会社の理解」、「社会の理解」が必要ではないか。
この時の会議でも全参加者10名中7名は学生、主婦、リタイア世代。(ちなみに女性は4名)
女性議会、若者議会と叫ばれるが、叫んでいるのは行政側で、このご意見のような現役世代からの声は意外に聞かない。
「自治参加が勤務先での評価に繋がれば」というご意見は、なかなかの慧眼だ。
本人の意思があっても、会社などの環境がなかなか許さないのが勤め人の現状だ。「市民自治」を掲げる新城市ならば、積極的に社員の自治参加を促すよう企業に働きかけるのも大事だろう。
・基本原則はよくできている。新庁舎に関する住民投票もこの基本原則がうまく機能していれば起こりえなかったのでは?例えば「(3)情報共有の原則」。行政、市民との情報共有のギャップがひとつの原因だったのでは?基本原則が効果的に機能しているかを考えなければならない。
市民自治会議ではすでに片付いた事になっている「新庁舎に関する住民投票」がこの場で出てきたことに、まずは驚いた。
新城市においては「住民投票」は自治基本条例に組み込まれているが、その際にいつも問題になるのは住民投票実施に至るまでのハードルが高い、という仕組み・手続き的な面だ。
このご意見は、まちづくり基本原則からあの「住民投票」を検証することで、第4条が効果的に機能するための経験則が得られないか? という意味であろうと受け取った。
これもなかなかのご慧眼だ。
今でもあの住民投票については、経緯や結果、事前に行われたまちづくり集会での各陣営の扱いとか、疑問はあるけれども、それらはひとまず置いておいて、まちづくり基本原則に照らし合わせてあの住民投票を考えてみるのはイイかもしれない。
この「第4条、まちづくり基本原則」は今回改めて読み直してみて、確かによくできているなぁと感じている。
若者議会、女性議会、まちづくり集会や地域自治区、市長のやること、議会のやること、全てこの「まちづくり基本原則」に照らし合わせて評価してみるとおもしろいだろう。
他にも色々な意見が出て、久々に面白いと感じた市民自治会議だった。
この意見交換が「第二次総合計画」の策定に役立ってもらえればうれしいことだ。
最後に、私はこんなことを意見しました。
前回の会議後、疑問点があったので8月3日に市に質問メールをしたが返信がなかった。9月26日に再度同じ内容でメールしたが、これも返信がなかった。(ちなみにこの会議の日の午後に返信が来ていたが気づかずw) これは(1)市民主役の原則に冷や水を浴びせるような行為で、市民が市政に参加すべく勇気を出してメールしたものを無視するのは著しく市民のヤル気を失せさせる行為だ。まちづくりのための仕組みは自治基本条例にあるこの基本原則をはじめ、若者議会や女性議会、地域自治区などよいものが整えられつつあるが、それを運用する「人間」も整備が必要だ。聞けば市民自治課の職員さんは午後3時から9時近くまで、若者議会の会議につきあっているらしい。そういう仕事の大変さに比べて職員数が少なすぎないだろうか。そして先ほど挙げた市民への対応の仕方の悪さ。「市民自治」を掲げる新城市ならば、今後の市民自治進展のために職員数の充実、質の充実を図るべきだろう。
と、述べさせていただいた。
実際は早口でまとまりのない、多分聞き取りにくい意見だったろうと思うw 反省。
2016年10月18日 Posted by けま at 03:59 │Comments(0) │市民自治会議
第8回新城市市民自治会議
10月5日、新城消防防災センターにて「第8回新城市市民自治会議」が行われた。
前回の会議において、他の議題で時間を取られて意見交換に至らなかった議題、
「第二次新城市総合計画」
について多くの時間を割いて、意見交換が行われた。
「第二次総合計画」だが、まずその根拠は「市城市自治基本条例第22条」にある。
(http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,30160,c,html/30160/20131225-170332.pdf)
*リンクの17ページをご覧ください。
ちなみに「第一次総合計画」はこちら。
少し解説すると、「第一次総合計画」は「地方自治法」という法律に基づき、作らなければならないものだった。
しかしこの「地方自治法」が平成23年5月に改正されて、「総合計画」とやらは「作らなければならない」という、法律による縛りは無くなった。
だが新城市は平成24年12月に「新城市自治基本条例」を策定し、先ほど挙げた第22条により、自主的に「地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために基本構想を策定」することにしている。
こういう理由で市は「第二次総合計画」を策定すべく、この平成28年度から取り組んでいるワケだ。
先を見据えた総合的な構想は必要だろう。その年度ごとに行き当たりばったり的な計画で市政が運営されては非常に不安だ。
決して裕福ではない新城市なのだから、計画的に予算を分配して必要な政策が滞りなく実行できるような体制を作っておいてほしい。
なので地方自治法の縛りがなくとも、このような総合計画的なモノは新城市だけでなく必ずどの自治体も作るはずだと考えられる。
しかし想像するに、他の自治体では、誰が、あるいはどの部署がどういうタイミングで、「策定しなくちゃいけないんじゃないの?」と言い出すのかわからないし、その後には策定発動のための長い会議が延々と続くのではないだろうか?(笑。
その点、新城市は条例により「策定します」とすでに決まっている。
法(条例)で決まっていれば、行政としてはスタートしやすいのではないか。
行政の体質(スタートすれば黙々と実行に邁進する)を見抜いた上で、「第22条」を盛り込んだのならば、これはなかなか先見の明がある、といえるだろうか。(そこまで考えたかどうか)
この「第一次総合計画」は期限が平成30年度(平成31年3月)まで。
来年度、つまり平成29年度中に「第二次総合計画」の素案が庁内で作られ、市民検討会とか審議会とかパブコメとか市民への説明会とか、様々な経緯を経て、最終的に議会で「第二次総合計画」が議決される。
翌30年度中に「第二次総合計画」に基づいた事業計画が練られる。予算づけもされる。
そして30年度末に、事業予算提案が為され、議会の議決となる。
晴れて31年度から「第二次総合計画」による新しい事業がスタートする。
こういう計画でいきたいと、市は考えている。
そこでこの時期、第二次総合計画の基本構想はどのようにすべきか、どうあるべきか、というアイディアを様々な分野から募っている。
その中のひとつとして、この市民自治会議にもお鉢が回ってきたというわけだ。
前説明だけで長くなってしまった。
続きます。
前回の会議において、他の議題で時間を取られて意見交換に至らなかった議題、
「第二次新城市総合計画」
について多くの時間を割いて、意見交換が行われた。
「第二次総合計画」だが、まずその根拠は「市城市自治基本条例第22条」にある。
(http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,30160,c,html/30160/20131225-170332.pdf)
*リンクの17ページをご覧ください。
ちなみに「第一次総合計画」はこちら。
少し解説すると、「第一次総合計画」は「地方自治法」という法律に基づき、作らなければならないものだった。
しかしこの「地方自治法」が平成23年5月に改正されて、「総合計画」とやらは「作らなければならない」という、法律による縛りは無くなった。
だが新城市は平成24年12月に「新城市自治基本条例」を策定し、先ほど挙げた第22条により、自主的に「地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために基本構想を策定」することにしている。
こういう理由で市は「第二次総合計画」を策定すべく、この平成28年度から取り組んでいるワケだ。
先を見据えた総合的な構想は必要だろう。その年度ごとに行き当たりばったり的な計画で市政が運営されては非常に不安だ。
決して裕福ではない新城市なのだから、計画的に予算を分配して必要な政策が滞りなく実行できるような体制を作っておいてほしい。
なので地方自治法の縛りがなくとも、このような総合計画的なモノは新城市だけでなく必ずどの自治体も作るはずだと考えられる。
しかし想像するに、他の自治体では、誰が、あるいはどの部署がどういうタイミングで、「策定しなくちゃいけないんじゃないの?」と言い出すのかわからないし、その後には策定発動のための長い会議が延々と続くのではないだろうか?(笑。
その点、新城市は条例により「策定します」とすでに決まっている。
法(条例)で決まっていれば、行政としてはスタートしやすいのではないか。
行政の体質(スタートすれば黙々と実行に邁進する)を見抜いた上で、「第22条」を盛り込んだのならば、これはなかなか先見の明がある、といえるだろうか。(そこまで考えたかどうか)
この「第一次総合計画」は期限が平成30年度(平成31年3月)まで。
来年度、つまり平成29年度中に「第二次総合計画」の素案が庁内で作られ、市民検討会とか審議会とかパブコメとか市民への説明会とか、様々な経緯を経て、最終的に議会で「第二次総合計画」が議決される。
翌30年度中に「第二次総合計画」に基づいた事業計画が練られる。予算づけもされる。
そして30年度末に、事業予算提案が為され、議会の議決となる。
晴れて31年度から「第二次総合計画」による新しい事業がスタートする。
こういう計画でいきたいと、市は考えている。
そこでこの時期、第二次総合計画の基本構想はどのようにすべきか、どうあるべきか、というアイディアを様々な分野から募っている。
その中のひとつとして、この市民自治会議にもお鉢が回ってきたというわけだ。
前説明だけで長くなってしまった。
続きます。
2016年10月11日 Posted by けま at 07:20 │Comments(0) │市民自治会議
若者
新城市について色んな方が情報発信をしているが、今、大注目しているのがこちらのブログ。
zen-tsttkhrのブログ → http://ameblo.jp/zen-tsttkhr/
若者議会の第2期メンバーの方です。
若者議会については市民自治会議委員をやっている関係で、様々な資料を見たり現在取り組んでいることを知ることができる立場にあるのだが、今一つフワフワした印象しか持てず、しっかりとした政策を提言できるようになるのはいつになるのだろう?とやきもきしていた。
しかしこの方のブログを読んで、「若者議会、やってくれるんじゃないか!?」という大きな期待と楽しみを持てるようになった。
「若者」に期待したいのは、私のようなおっさんには思いつかないような奇抜な発想、そしてフットワークの軽い行動力、だろうか。
今まではこれが見えにくかった。
多分話し合いの現場では闊達な意見交換が為されているのだろうし、意外と色んなところに足を運んでいるのかもしれない。
そういう現場の動き、現場からの声が、ようやくこのzen-tsttkhrさんのブログを通して見ることができるようになった。
加えて良いと思うのは、社会人でもあるzen-tsttkhrさんがご自身の仕事から得てきたであろう「仕事眼」でもって、若者議会の取り組みを眺めていることだ。
実社会において仕事というものは、事業の対象(要は「お客さん」だ)に満足してもらわなくてはならない。
そしてそこからさらに利益を出さなくてはいけない。
理念や発想だけでは立ち行かない世界だ。
理念、発想をどうやって現実化するのか。zen-tsttkhrさんはお若いながら、そういう世界で揉まれているのだろう。
他の若者メンバーからの考えや、ご自身の理想をいかに実現可能なものにするのか、その考え方の道筋が地に足をつけたもののように感じられる。
実に頼もしく、この先どう展開していくのか非常に楽しみだ。
皆さんも、ぜひこちら zen-tsttkhrのブログ → http://ameblo.jp/zen-tsttkhr/ ブックマークして見守ってあげてください。
若さを妬んだ輩のつまらないコメントにも、頭を垂れて自ら反省点を探す、実に大器量を感じさせる若者ですw
皆さんもできたら建設的なコメント、そして応援コメントをしてあげてください。
zen-tsttkhrのブログ → http://ameblo.jp/zen-tsttkhr/
若者議会の第2期メンバーの方です。
若者議会については市民自治会議委員をやっている関係で、様々な資料を見たり現在取り組んでいることを知ることができる立場にあるのだが、今一つフワフワした印象しか持てず、しっかりとした政策を提言できるようになるのはいつになるのだろう?とやきもきしていた。
しかしこの方のブログを読んで、「若者議会、やってくれるんじゃないか!?」という大きな期待と楽しみを持てるようになった。
「若者」に期待したいのは、私のようなおっさんには思いつかないような奇抜な発想、そしてフットワークの軽い行動力、だろうか。
今まではこれが見えにくかった。
多分話し合いの現場では闊達な意見交換が為されているのだろうし、意外と色んなところに足を運んでいるのかもしれない。
そういう現場の動き、現場からの声が、ようやくこのzen-tsttkhrさんのブログを通して見ることができるようになった。
加えて良いと思うのは、社会人でもあるzen-tsttkhrさんがご自身の仕事から得てきたであろう「仕事眼」でもって、若者議会の取り組みを眺めていることだ。
実社会において仕事というものは、事業の対象(要は「お客さん」だ)に満足してもらわなくてはならない。
そしてそこからさらに利益を出さなくてはいけない。
理念や発想だけでは立ち行かない世界だ。
理念、発想をどうやって現実化するのか。zen-tsttkhrさんはお若いながら、そういう世界で揉まれているのだろう。
他の若者メンバーからの考えや、ご自身の理想をいかに実現可能なものにするのか、その考え方の道筋が地に足をつけたもののように感じられる。
実に頼もしく、この先どう展開していくのか非常に楽しみだ。
皆さんも、ぜひこちら zen-tsttkhrのブログ → http://ameblo.jp/zen-tsttkhr/ ブックマークして見守ってあげてください。
若さを妬んだ輩のつまらないコメントにも、頭を垂れて自ら反省点を探す、実に大器量を感じさせる若者ですw
皆さんもできたら建設的なコメント、そして応援コメントをしてあげてください。
2016年08月04日 Posted by けま at 11:24 │Comments(0) │市民自治会議│市政を考える
第7回新城市市民自治会議
先月27日に第7回新城市市民自治会議が行われた。
いつもの流れで、最初は報告。
すでに行われたものやこの先行われる色んな行事やらイベント、その報告が担当の方々からある。
私たち自治会議委員もその都度疑問があれば質問して、また担当の方々が回答する、といった具合。
今年で2年目なのだけれども、なんとなくこういう「会議」のお作法が呑み込めてきた。
今回でも、最初の報告「産業自治推進協議会による地域産業総合振興ビジョンおよび振興計画」と、
3番目の報告「めざせ明日のまちづくり事業(コミュニティビジネス)」で疑問に感じたことを聞いてみたのだけれども。
最初の報告はやたらと題名が長いけれども、要は「地域の産業を活性化させ、儲かる仕組みを地域で作っていくこと」と言えるだろうか。
3番目のは「地域で起業した若者や女性たちをの事業を補助する仕組み」だ。
後から勉強してみると自分の勘違いも多くて(^_^;)、その勘違いのまま質問しているから相手も自分も分からなくなるのだろうけれども、とも言い訳しておいて。
最初の「産業自治」も3番目の「めざまち(と、こう略しているらしい)」も、共に地域での起業を支援するわけだから、起業する人にとって「窓口が多い」メリットはあると思うけれども、同時に自分の起業がどの窓口に一番マッチするのかわかりにくいデメリットもあるんじゃないか?
とか、
どちらの起業支援も税金をつぎ込むわけだけれども、同じような企画が双方に申し込まれた場合、「産業自治」と「めざまち」とのヨコのつながりで調整するような仕組みはあるのだろうか?
とか、質問してみたが、なんだか「メンドクサイこと言うやつ」的な扱いだった(と感じた)。
つまり、今は「報告」の段階だから、そういう議論めいたことはしてほしくないのだな。
報告はさらっと聞き流して、次に控える議題「第2次新城市総合計画」に時間を使いたかったのだ。
なのだが、私は市民公募の委員なので、進行の人も市職員も私の発言をぞんざいに扱うわけにもいかないのだな、きっと。
という感じで、会議の「空気を読んで」質問しないとイカンのだ。
結局この「報告」で時間が多くかかり、議題に取り掛かることができなかった。
次回は10月5日。
議題の「第2次新城市総合計画」を中心に会議が行われる。
いつもの流れで、最初は報告。
すでに行われたものやこの先行われる色んな行事やらイベント、その報告が担当の方々からある。
私たち自治会議委員もその都度疑問があれば質問して、また担当の方々が回答する、といった具合。
今年で2年目なのだけれども、なんとなくこういう「会議」のお作法が呑み込めてきた。
今回でも、最初の報告「産業自治推進協議会による地域産業総合振興ビジョンおよび振興計画」と、
3番目の報告「めざせ明日のまちづくり事業(コミュニティビジネス)」で疑問に感じたことを聞いてみたのだけれども。
最初の報告はやたらと題名が長いけれども、要は「地域の産業を活性化させ、儲かる仕組みを地域で作っていくこと」と言えるだろうか。
3番目のは「地域で起業した若者や女性たちをの事業を補助する仕組み」だ。
後から勉強してみると自分の勘違いも多くて(^_^;)、その勘違いのまま質問しているから相手も自分も分からなくなるのだろうけれども、とも言い訳しておいて。
最初の「産業自治」も3番目の「めざまち(と、こう略しているらしい)」も、共に地域での起業を支援するわけだから、起業する人にとって「窓口が多い」メリットはあると思うけれども、同時に自分の起業がどの窓口に一番マッチするのかわかりにくいデメリットもあるんじゃないか?
とか、
どちらの起業支援も税金をつぎ込むわけだけれども、同じような企画が双方に申し込まれた場合、「産業自治」と「めざまち」とのヨコのつながりで調整するような仕組みはあるのだろうか?
とか、質問してみたが、なんだか「メンドクサイこと言うやつ」的な扱いだった(と感じた)。
つまり、今は「報告」の段階だから、そういう議論めいたことはしてほしくないのだな。
報告はさらっと聞き流して、次に控える議題「第2次新城市総合計画」に時間を使いたかったのだ。
なのだが、私は市民公募の委員なので、進行の人も市職員も私の発言をぞんざいに扱うわけにもいかないのだな、きっと。
という感じで、会議の「空気を読んで」質問しないとイカンのだ。
結局この「報告」で時間が多くかかり、議題に取り掛かることができなかった。
次回は10月5日。
議題の「第2次新城市総合計画」を中心に会議が行われる。
2016年08月03日 Posted by けま at 10:23 │Comments(3) │市民自治会議
第3回市民自治会議 2
この前の第3回市民自治会議の続き。
最初に、1・地域産業総合振興条例策定事業について
パブリックコメントには7名19件の意見が寄せられた。
会議は10月28日開催、すでにパブコメは締め切られ自治会議での話し合いも終わっているが、いまだに市のHPへの掲載はなし。
会議では市のHPにおいて市民への公開は約束されたが、この遅さはどうだろう。
まぁ忙しいのだろうけど、いつも言うように情報開示のスピードが遅い。
このパブコメは実際にすべての意見を見てもらうのが一番よいのだけれども、ひとつ挙げてみる。
自分も意見したことなのだが、同じように自治委員の中でも意見した方がいて、同じところに着目しているところに心強さを覚えた。
それは、条例素案の第6条に市民の役割として「事業者が提供する商品及びサービスに関心を深め、購入するよう努めること」という条文。
この条文の「強制するような表現」と「その強制を条例化する危うさ」が指摘され、委員の間で大きな懸念が示された。
ここの表現はこの条例素案を策定した委員さんたちでも大きく議論されたところらしい。
市民にも参加協同意識を持ってほしい、という意気込みの表れとしてこういう表現になったということだが、決して強制するものではないと説明者は言っていた。
が、表現の裏にそのような「隠れた考え」がある条文は問題だと思うのだ。
いったん条例化されればこの条文はこの先ずっと残る。
この「隠れた考え」をわかっている人が死に絶えても条文は残る。
そして未来に「隠れた考え」を知らない人がこの条文を条文だけで解釈して、市民に「地元のモノを買え。買わなければ条例違反だ。」とか言い出したらどうなるか。
大袈裟に考えすぎかもしれないが、条例つまり法律とはそういうものだろう。
条例があるおかげで未来を守ることもできる。例えば環境保全条例などは未来に予想される環境汚染を防ぐためのものだ。
でも条文が拙ければ裏の意図など忘れ去られ、条文の拙さゆえに時の権力者にいいように解釈されて結局市民を苦しめることにもなる。
この条例素案第6条は自治会議委員によって強く懸念が示された。よくよく再考されて、条例文を工夫してほしい。
次は、3・集会を妨げる事態等への対応について
持論であった「ヤジ対策(「ヤジについて」http://kemanomake.dosugoi.net/e797458.html)」を意見してみたが、なんというか一笑に付された感じだった(笑
まぁ、そうだろうなと思いつつ後は黙って皆さんの意見を聞いていた。
私の意見を受けて、とある委員さんが「驚くべき性善説(私の持論のコト)で云々」と語りだしたのが「ヤジは絶対イカン」という御意見。
福井県高浜町の原発説明会を例に出して、「運動員などの猛烈なヤジや反対意見で説明会どころではなくなり、結果的に一番に説明を受けなければならない市民が怖がって参加しなくなってしまった」と言われた。
これには議長の鈴木先生も言及されて、この第3回まちづくり集会の時でも(この時鈴木先生は壇上でコーディネーターを任されていた)「警察には連絡を入れてくれてますか?」と訊ねていたと言われた。
高浜町のような、集会を妨害するような激しい行為があることをかなり本気に危惧していたらしい。
ヤジに代表されるような、集会を妨害する行為はとにかく御法度、というのが通例らしいのだな。
私はヤジを飛ばしていた「守る会」の皆さんの気持ちもよく理解できるのだが、あの場には「善良な市民」も多くいたわけで、やはり「大きな声でヤジる」という行為がその「善良な子羊のような市民」に大きな恐怖を与えたであろうことも想像できる。
まちづくり集会でのヤジの第一発目は選択肢2の説明をしてた人が、選択肢2に不利に働く私見を述べたところから始まった。
このことは最初に持論を意見した時に言及した。
鈴木先生はこのことを受けてくれたのだろうと思うのだが「例えヤジにつながる発言があったとしても、集会はそういうのも含めて進行されなくてはならない。その発言がきっかけのヤジだとしてもヤジに良いも悪いもなく云々」というようなことも言われた。
あの集会が討論会なら失言もアリ、というのはわかる。
しかしあの集会は「情報を共有する会」だったはずで、賛成も反対もしないのが約束だった。
どちらかの選択肢を誘導するような私見を述べたら、それはもう「情報を共有する会」ではなく「討論会」というのがふさわしいだろう。
意見を述べ合うのが討論会なのだから、壇上で私見を言うのが許されてしまった時になぜ客席で黙っていなくてはならないのか。
互いに壇上に立たなければ「公平公正」ではないだろう。
と、あの時に言えたら・・・。
これは今思いついて書いていて、自分の「その場のディベート力」の不甲斐なさに情けなくなる。
結局のところ集会の妨害行為に対しては、集会の企画とはまた別に、妨害行為対策を考えることも必要だろうという結論になった。
「まちづくり集会」は「まちづくり集会実行委員」に企画運営がすべて任されているが、今度からこのような対立がある事柄を集会で企画するときには妨害行為対策も同時に実行委員会の方で話し合われることになるのだろう。
しかしなぁ、ヤジとか妨害行為の恐れがあるのなら、市民とかが集会に集まる意味ってなんなのだろうって思ってしまう。
その場に足を運ぶ意味っていうのかな。
こんだけインターネットが発達してくれば、集会なんて直に参加しないで中継にして、パソコンで市民参加でもいいんじゃないか?
実際ネットで生中継って行われているし。
チャットでその場でどんどん意見してもらったりして、それをサブ画面に流したり。ニコ動みたく画面に意見が流れるのもおもしろいかもなぁ。
というわけで第3回市民自治会議は終了。
次回は12月8日の予定。
最初に、1・地域産業総合振興条例策定事業について
パブリックコメントには7名19件の意見が寄せられた。
会議は10月28日開催、すでにパブコメは締め切られ自治会議での話し合いも終わっているが、いまだに市のHPへの掲載はなし。
会議では市のHPにおいて市民への公開は約束されたが、この遅さはどうだろう。
まぁ忙しいのだろうけど、いつも言うように情報開示のスピードが遅い。
このパブコメは実際にすべての意見を見てもらうのが一番よいのだけれども、ひとつ挙げてみる。
自分も意見したことなのだが、同じように自治委員の中でも意見した方がいて、同じところに着目しているところに心強さを覚えた。
それは、条例素案の第6条に市民の役割として「事業者が提供する商品及びサービスに関心を深め、購入するよう努めること」という条文。
この条文の「強制するような表現」と「その強制を条例化する危うさ」が指摘され、委員の間で大きな懸念が示された。
ここの表現はこの条例素案を策定した委員さんたちでも大きく議論されたところらしい。
市民にも参加協同意識を持ってほしい、という意気込みの表れとしてこういう表現になったということだが、決して強制するものではないと説明者は言っていた。
が、表現の裏にそのような「隠れた考え」がある条文は問題だと思うのだ。
いったん条例化されればこの条文はこの先ずっと残る。
この「隠れた考え」をわかっている人が死に絶えても条文は残る。
そして未来に「隠れた考え」を知らない人がこの条文を条文だけで解釈して、市民に「地元のモノを買え。買わなければ条例違反だ。」とか言い出したらどうなるか。
大袈裟に考えすぎかもしれないが、条例つまり法律とはそういうものだろう。
条例があるおかげで未来を守ることもできる。例えば環境保全条例などは未来に予想される環境汚染を防ぐためのものだ。
でも条文が拙ければ裏の意図など忘れ去られ、条文の拙さゆえに時の権力者にいいように解釈されて結局市民を苦しめることにもなる。
この条例素案第6条は自治会議委員によって強く懸念が示された。よくよく再考されて、条例文を工夫してほしい。
次は、3・集会を妨げる事態等への対応について
持論であった「ヤジ対策(「ヤジについて」http://kemanomake.dosugoi.net/e797458.html)」を意見してみたが、なんというか一笑に付された感じだった(笑
まぁ、そうだろうなと思いつつ後は黙って皆さんの意見を聞いていた。
私の意見を受けて、とある委員さんが「驚くべき性善説(私の持論のコト)で云々」と語りだしたのが「ヤジは絶対イカン」という御意見。
福井県高浜町の原発説明会を例に出して、「運動員などの猛烈なヤジや反対意見で説明会どころではなくなり、結果的に一番に説明を受けなければならない市民が怖がって参加しなくなってしまった」と言われた。
これには議長の鈴木先生も言及されて、この第3回まちづくり集会の時でも(この時鈴木先生は壇上でコーディネーターを任されていた)「警察には連絡を入れてくれてますか?」と訊ねていたと言われた。
高浜町のような、集会を妨害するような激しい行為があることをかなり本気に危惧していたらしい。
ヤジに代表されるような、集会を妨害する行為はとにかく御法度、というのが通例らしいのだな。
私はヤジを飛ばしていた「守る会」の皆さんの気持ちもよく理解できるのだが、あの場には「善良な市民」も多くいたわけで、やはり「大きな声でヤジる」という行為がその「善良な子羊のような市民」に大きな恐怖を与えたであろうことも想像できる。
まちづくり集会でのヤジの第一発目は選択肢2の説明をしてた人が、選択肢2に不利に働く私見を述べたところから始まった。
このことは最初に持論を意見した時に言及した。
鈴木先生はこのことを受けてくれたのだろうと思うのだが「例えヤジにつながる発言があったとしても、集会はそういうのも含めて進行されなくてはならない。その発言がきっかけのヤジだとしてもヤジに良いも悪いもなく云々」というようなことも言われた。
あの集会が討論会なら失言もアリ、というのはわかる。
しかしあの集会は「情報を共有する会」だったはずで、賛成も反対もしないのが約束だった。
どちらかの選択肢を誘導するような私見を述べたら、それはもう「情報を共有する会」ではなく「討論会」というのがふさわしいだろう。
意見を述べ合うのが討論会なのだから、壇上で私見を言うのが許されてしまった時になぜ客席で黙っていなくてはならないのか。
互いに壇上に立たなければ「公平公正」ではないだろう。
と、あの時に言えたら・・・。
これは今思いついて書いていて、自分の「その場のディベート力」の不甲斐なさに情けなくなる。
結局のところ集会の妨害行為に対しては、集会の企画とはまた別に、妨害行為対策を考えることも必要だろうという結論になった。
「まちづくり集会」は「まちづくり集会実行委員」に企画運営がすべて任されているが、今度からこのような対立がある事柄を集会で企画するときには妨害行為対策も同時に実行委員会の方で話し合われることになるのだろう。
しかしなぁ、ヤジとか妨害行為の恐れがあるのなら、市民とかが集会に集まる意味ってなんなのだろうって思ってしまう。
その場に足を運ぶ意味っていうのかな。
こんだけインターネットが発達してくれば、集会なんて直に参加しないで中継にして、パソコンで市民参加でもいいんじゃないか?
実際ネットで生中継って行われているし。
チャットでその場でどんどん意見してもらったりして、それをサブ画面に流したり。ニコ動みたく画面に意見が流れるのもおもしろいかもなぁ。
というわけで第3回市民自治会議は終了。
次回は12月8日の予定。
2015年11月11日 Posted by けま at 12:04 │Comments(0) │市民自治会議
第3回市民自治会議
10月28日、第3回市民自治会議に参加してきた。
普段仕事を持っている方も多くなかなか全員がそろう事がない会議だが、私は今のところ皆勤だ。
よっぽどヒマなのかと思われそうだが、応募理由200字程度書いてまで獲得した委員だし(笑、
報酬もあるし(7,500円/回(2時間以内の場合5,000円))、出られる限り頑張るよ。
まずは報告。
1つめは「第4回市民まちづくり集会」について。
これはこの前傍聴させてもらった「まちづくり集会実行委員会」で聞かせてもらったことが整理されて報告された。
開催日は、平成28年1月24日(日)午後。
テーマは「市政10年 ~そしてこれから」。
第1部が「新城再発見!こんなの知ってました?(発表)」
・市内各地域(自治区か中学校区かはまだ議論中)からの代表が自分の地域にあるモノやコト、活動を発表してもらう。
第2部が「みんなでつくろう未来予想図(ワークショップ)」
・いくつかのグループに分かれ、第1部での発表をもとに色々話し合いをする。
こんな感じ。ちょうど合併して記念式典も開かれたことだし、足元を見つめなおして未来を考えるテーマは良いと思う。
この先の実行委員会のがんばりに期待したい。
2つめは「地域自治区活動状況について」
この前千郷地区の「地域意見交換会」に参加した時に、「平成28年度地域自治区予算事業計画案」が市長に建議された。
きちんと正確に書こうとするとどうしてもムズカシイ漢字の羅列になってしまう。
千郷地区で話し合って決まった「こんなことしたい」的な計画の予算今年度分を、市長に「よろしく頼んます」とお願いした、と。
この「よろしく頼んます」が市内各地域全てでおこなわれ、それらの報告があった。
各地域の今年度の事業計画案がすべて書かれた表をもらったので、各地域間の比較ができて大変面白かった。
そして事業計画案の元になる、申請のあった事業案の詳細(これも市内全地域)が書かれた表ももらって、これも読んでいると大変面白い。
特に申請の審査結果が興味深く、ほとんどが採択になるのだが不採択になった申請案ってなんだろう?と、ほとんど野次馬的な興味で見させてもらった。
で、気づいたことがあった。
どの地域でも似たような内容の事業案の申請があって、同じような内容にもかかわらず地域のよって採択されたり不採択になったりしているのだ。
地域協議会では公正に話し合われ、申請者にもしっかり説明された上で採択不採択が決まっているのでそこは問題ない。
しかしこの時不採択になった申請者がたまたま他地域の、たまたま同じような内容の申請者で採択になった人と話す機会があったらどうなるだろうか?
地域の違いはあるとしても同じ新城市民。同じような申請案が片や採択、片や不採択。不公平感が湧きあがるのが人情ではないか。
で、このことを質問してみた。
報告、説明してくれた事務の方もここは苦しそうだった。
つまり、まず 1・地域によって予算が違う事。 2・地域内での申請案に対する優先順位が異なる事。
この2つの絡みで同じような申請案でも違いが出てきてしまう、ということらしい。
予算はざっくり言うと、地域の人口と地域の広さ(面積)で決まる。
(予算の名称は「地域活動交付金」人口×500円+面積×1万円)
広くて人口の多い地域の申請案は採択されやすいし、狭くて人口が少ないと採択されにくいだろうし、狭くて人口少ないのに市民活動が盛んで申請案が多かったりすると不採択も格段に増えそう。
だから逆に広くて人口多いのに市民活動が鈍いと予算が余っちゃうなんてこともあるのかもね。
確か今年度から事務所長が民間から任用された「自治振興事務所」がこの調整を図るべきなのだろう。
(市長のブログに書いてあった。→http://tomako.dosugoi.net/e756631.html)
自治振興事務所は市内に3つあり、それぞれが担当する地域間の調整を図るの事が仕事の一部だが、この3つの自治振興事務所でも話し合いを持ち、申請者に不公平感を持たせないように調整してほしいものだ。
以上が報告。
メインは議題の
1・地域産業総合振興条例策定事業について
2・自治基本条例の改正等について
3・集会を妨げる事態等への対応について
2は今度の選挙から18歳以上の選挙権が認められることに伴う改正のことで、市のHPから見られる自治基本条例などの条文にある「20才」という記述を「18才」に変える、というもの。
これは問題ない。
1はブログでも書いたし、実際パブリックコメントもメールで送ったし、その顛末を次回書いてみよう。
3は、ブログでもずっと書いてたことで一応の結果が出たのだが、なんだかムカついたのでこれも次回書く。
普段仕事を持っている方も多くなかなか全員がそろう事がない会議だが、私は今のところ皆勤だ。
よっぽどヒマなのかと思われそうだが、応募理由200字程度書いてまで獲得した委員だし(笑、
報酬もあるし(7,500円/回(2時間以内の場合5,000円))、出られる限り頑張るよ。
まずは報告。
1つめは「第4回市民まちづくり集会」について。
これはこの前傍聴させてもらった「まちづくり集会実行委員会」で聞かせてもらったことが整理されて報告された。
開催日は、平成28年1月24日(日)午後。
テーマは「市政10年 ~そしてこれから」。
第1部が「新城再発見!こんなの知ってました?(発表)」
・市内各地域(自治区か中学校区かはまだ議論中)からの代表が自分の地域にあるモノやコト、活動を発表してもらう。
第2部が「みんなでつくろう未来予想図(ワークショップ)」
・いくつかのグループに分かれ、第1部での発表をもとに色々話し合いをする。
こんな感じ。ちょうど合併して記念式典も開かれたことだし、足元を見つめなおして未来を考えるテーマは良いと思う。
この先の実行委員会のがんばりに期待したい。
2つめは「地域自治区活動状況について」
この前千郷地区の「地域意見交換会」に参加した時に、「平成28年度地域自治区予算事業計画案」が市長に建議された。
きちんと正確に書こうとするとどうしてもムズカシイ漢字の羅列になってしまう。
千郷地区で話し合って決まった「こんなことしたい」的な計画の予算今年度分を、市長に「よろしく頼んます」とお願いした、と。
この「よろしく頼んます」が市内各地域全てでおこなわれ、それらの報告があった。
各地域の今年度の事業計画案がすべて書かれた表をもらったので、各地域間の比較ができて大変面白かった。
そして事業計画案の元になる、申請のあった事業案の詳細(これも市内全地域)が書かれた表ももらって、これも読んでいると大変面白い。
特に申請の審査結果が興味深く、ほとんどが採択になるのだが不採択になった申請案ってなんだろう?と、ほとんど野次馬的な興味で見させてもらった。
で、気づいたことがあった。
どの地域でも似たような内容の事業案の申請があって、同じような内容にもかかわらず地域のよって採択されたり不採択になったりしているのだ。
地域協議会では公正に話し合われ、申請者にもしっかり説明された上で採択不採択が決まっているのでそこは問題ない。
しかしこの時不採択になった申請者がたまたま他地域の、たまたま同じような内容の申請者で採択になった人と話す機会があったらどうなるだろうか?
地域の違いはあるとしても同じ新城市民。同じような申請案が片や採択、片や不採択。不公平感が湧きあがるのが人情ではないか。
で、このことを質問してみた。
報告、説明してくれた事務の方もここは苦しそうだった。
つまり、まず 1・地域によって予算が違う事。 2・地域内での申請案に対する優先順位が異なる事。
この2つの絡みで同じような申請案でも違いが出てきてしまう、ということらしい。
予算はざっくり言うと、地域の人口と地域の広さ(面積)で決まる。
(予算の名称は「地域活動交付金」人口×500円+面積×1万円)
広くて人口の多い地域の申請案は採択されやすいし、狭くて人口が少ないと採択されにくいだろうし、狭くて人口少ないのに市民活動が盛んで申請案が多かったりすると不採択も格段に増えそう。
だから逆に広くて人口多いのに市民活動が鈍いと予算が余っちゃうなんてこともあるのかもね。
確か今年度から事務所長が民間から任用された「自治振興事務所」がこの調整を図るべきなのだろう。
(市長のブログに書いてあった。→http://tomako.dosugoi.net/e756631.html)
自治振興事務所は市内に3つあり、それぞれが担当する地域間の調整を図るの事が仕事の一部だが、この3つの自治振興事務所でも話し合いを持ち、申請者に不公平感を持たせないように調整してほしいものだ。
以上が報告。
メインは議題の
1・地域産業総合振興条例策定事業について
2・自治基本条例の改正等について
3・集会を妨げる事態等への対応について
2は今度の選挙から18歳以上の選挙権が認められることに伴う改正のことで、市のHPから見られる自治基本条例などの条文にある「20才」という記述を「18才」に変える、というもの。
これは問題ない。
1はブログでも書いたし、実際パブリックコメントもメールで送ったし、その顛末を次回書いてみよう。
3は、ブログでもずっと書いてたことで一応の結果が出たのだが、なんだかムカついたのでこれも次回書く。
2015年11月01日 Posted by けま at 06:30 │Comments(0) │市民自治会議
「新城市地域産業総合振興条例(案)」(長い、難しい)
「新城市地域産業総合振興条例(案)」という長い名前の条例案があって、これが次回の会議の議題になっている。
今度で3回目の会議だが、その3回ともこの条例案の事がなにかと取り上げられている。
産業振興と市民自治会議がどう関係するのだろうと思っていたが、この案のなかに「産業自治」なる新しい言葉が盛り込まれていて、この関連で市民「自治」会議にも話が持って来られているようだ。
「産業自治」の定義は、「市民・事業者・市が自らの意思でそれぞれの役割を果たすとともに、お互いに協力しあうこと」だそうだ。
この案は市のホームページで公開されています。
→http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,44058,169,782,html
ページ内、「2.意見募集項目」の「1 条例(案)のポイント」でわかりやすく解説されています。
まちづくり集会のところで書いたが、「条例で定めた以上執行しなくてはならない」という言葉がとても印象に残っている。
実際には「第○条~」と書かれた具体的な項目が執行されるわけだが、それらの大本の考え方が常に実現化される可能性を秘めていることに注意したいところだ。
で、気になるのが先に挙げた産業自治の定義にある「市民・事業者・市が自らの意思で~」というところ。
条例で、つまり法律でもって、なんで私たち市民の「自らの意思で~」とか決められなくてはならないのか?
自分の意思は自分のモノであって、それを条例で定められる、こちらの意思など無視するように定められる、ってどういうことなのだろうか?
その「市民」には言葉の定義、求められる役割が決まっていて、
まず「市民」
↓
住民、市内で働く人若しくは学ぶ人又は市内において公益活動をする団体をいいます。
(案 第2条(1))
そして「市民の役割」
↓
1 事業者が提供する商品及びサービスに関心を深め、購入するよう努めること。
2 事業者が提供する商品及びサービスについて、事業者に対して提案し、又は意見を伝えるよう努めること。
(案 第6条 (1)(2))
と、こうなっている。
市民は新城市に住んでる人ってことで問題ないけれども、次の「役割」ってのもまた疑問にあふれた内容だ。
要するに地元企業の商品を買おう、商品に意見を言おう、ということだが、そんなことをなぜ条例で決められなきゃならんのか?
「地域産業振興」の名のもとに買う義務を法律的に負わせられるコト、なわけだ。モノを買う自由を制限させられる内容とならないのだろうか?
この条例は、一番の大本は「地域産業振興」だ。
産業の主体はこの条例の言葉の定義で言えば「事業者」で、「産業振興」は「事業者支援」とイコールで結ばれる。
それは条例(案)にもしっかり書かれていて、
1 事業者への支援
2 起業・創業の支援
3 コミュニティビジネスへの支援
4 連携・交流への支援
(案 第7条 (1)~(6))
1はそのまま事業者支援、2は起業・創業した人はイコール事業者、3はコミュニティビジネスをする人は事業者、4は事業者が「連携・交流」する支援、というわけで支援を受けるのは専ら事業者なのだな。
で、市民はその事業者の売るものを買え、と。
市民もそのフトコロで持って事業者を支えるわけで、徹底して事業者支援の条例であることがわかる。
市民のフトコロから出たお金は商品売上として事業者に渡り、そのお金を元手に再生産された商品を市民がまた買う。
こうしてお金が地域で循環する仕組みが作られる、と。
マコトに結構な仕組みだし、そりゃこれが理想とする姿なのもわかる。
しかしさぁ、「市民に強制的に買わせる仕組み」を条例で作っといてお金が地域を循環する仕組みでござい、って計画経済みたいじゃないの。これでソ連はつぶれたぞ。
事業者が魅力的な商品を産み出して、市外からお金が入ってくるようにして、そのお金を再生産に回し市内市民の雇用を生み出すのが最も理想的なんじゃないのかな。
魅力的な商品を産み出す支援としての条例でなくては、経済規模の大きくない新城市で高齢者の年金を資本にしてお金を循環させても先細りじゃないか?
書いているうちに色々気づいてきたぞ。これがブログに書く私なりのメリットだ。
私のような素人の戯言には違いないが、ひとつパブコメに書いてやろう。
今度で3回目の会議だが、その3回ともこの条例案の事がなにかと取り上げられている。
産業振興と市民自治会議がどう関係するのだろうと思っていたが、この案のなかに「産業自治」なる新しい言葉が盛り込まれていて、この関連で市民「自治」会議にも話が持って来られているようだ。
「産業自治」の定義は、「市民・事業者・市が自らの意思でそれぞれの役割を果たすとともに、お互いに協力しあうこと」だそうだ。
この案は市のホームページで公開されています。
→http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/7,44058,169,782,html
ページ内、「2.意見募集項目」の「1 条例(案)のポイント」でわかりやすく解説されています。
まちづくり集会のところで書いたが、「条例で定めた以上執行しなくてはならない」という言葉がとても印象に残っている。
実際には「第○条~」と書かれた具体的な項目が執行されるわけだが、それらの大本の考え方が常に実現化される可能性を秘めていることに注意したいところだ。
で、気になるのが先に挙げた産業自治の定義にある「市民・事業者・市が自らの意思で~」というところ。
条例で、つまり法律でもって、なんで私たち市民の「自らの意思で~」とか決められなくてはならないのか?
自分の意思は自分のモノであって、それを条例で定められる、こちらの意思など無視するように定められる、ってどういうことなのだろうか?
その「市民」には言葉の定義、求められる役割が決まっていて、
まず「市民」
↓
住民、市内で働く人若しくは学ぶ人又は市内において公益活動をする団体をいいます。
(案 第2条(1))
そして「市民の役割」
↓
1 事業者が提供する商品及びサービスに関心を深め、購入するよう努めること。
2 事業者が提供する商品及びサービスについて、事業者に対して提案し、又は意見を伝えるよう努めること。
(案 第6条 (1)(2))
と、こうなっている。
市民は新城市に住んでる人ってことで問題ないけれども、次の「役割」ってのもまた疑問にあふれた内容だ。
要するに地元企業の商品を買おう、商品に意見を言おう、ということだが、そんなことをなぜ条例で決められなきゃならんのか?
「地域産業振興」の名のもとに買う義務を法律的に負わせられるコト、なわけだ。モノを買う自由を制限させられる内容とならないのだろうか?
この条例は、一番の大本は「地域産業振興」だ。
産業の主体はこの条例の言葉の定義で言えば「事業者」で、「産業振興」は「事業者支援」とイコールで結ばれる。
それは条例(案)にもしっかり書かれていて、
1 事業者への支援
2 起業・創業の支援
3 コミュニティビジネスへの支援
4 連携・交流への支援
(案 第7条 (1)~(6))
1はそのまま事業者支援、2は起業・創業した人はイコール事業者、3はコミュニティビジネスをする人は事業者、4は事業者が「連携・交流」する支援、というわけで支援を受けるのは専ら事業者なのだな。
で、市民はその事業者の売るものを買え、と。
市民もそのフトコロで持って事業者を支えるわけで、徹底して事業者支援の条例であることがわかる。
市民のフトコロから出たお金は商品売上として事業者に渡り、そのお金を元手に再生産された商品を市民がまた買う。
こうしてお金が地域で循環する仕組みが作られる、と。
マコトに結構な仕組みだし、そりゃこれが理想とする姿なのもわかる。
しかしさぁ、「市民に強制的に買わせる仕組み」を条例で作っといてお金が地域を循環する仕組みでござい、って計画経済みたいじゃないの。これでソ連はつぶれたぞ。
事業者が魅力的な商品を産み出して、市外からお金が入ってくるようにして、そのお金を再生産に回し市内市民の雇用を生み出すのが最も理想的なんじゃないのかな。
魅力的な商品を産み出す支援としての条例でなくては、経済規模の大きくない新城市で高齢者の年金を資本にしてお金を循環させても先細りじゃないか?
書いているうちに色々気づいてきたぞ。これがブログに書く私なりのメリットだ。
私のような素人の戯言には違いないが、ひとつパブコメに書いてやろう。