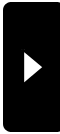裁判傍聴に行ってきた 3
7月18日の名古屋地裁での裁判では、午前中に加藤さん、午後は市役所側からの2人への尋問が行われた。
午後の尋問に関しては私の拙いメモや記憶よりも、白井みちひろさんのブログの方がはるかに詳しく正確だ。
→ 白井みちひろ後援会公式ブログ 裁判傍聴記「新城市役所は大丈夫?」(2018年07月19日)
是非こちらを読んでみてください。
今回の記事を書くにあたってネットで色々と検索をしていたらこんなサイトがあった。
→ 民事裁判における当事者尋問の様子
このサイトに書いてあること、まさにこの通りのことが行われていたなぁと再確認できた。
で、こちらのサイトの言葉を借りると、
“次は法廷で尋問手続が行われます。 必ず行われるわけではなく裁判所が必要と認めたときのみですが、事実関係を巡るお互いの主張に隔たりがある場合は、大体行われるものと思っていいです。”
ということは、加藤さんの言い分と市側の言い分に隔たりがあるので今回の尋問が行われた、という事だろう。
ではその隔たりとは何か?
私が傍聴していた記憶とメモによれば、後で補足しますが、今回の焦点である用地補償について、
加藤さんは市側から「相談を受けた」と言っている。
市側は加藤さんに「相談していない」と言っている。
(※加藤さんは市議以外のご自身の仕事として、不動産の関係のお仕事をされていて土地取引のことについて詳しい。市職員もそのことを知っていたからこそ相談した。)
ここの食い違いの事だろうと思っている。
最初の記事に書いた加藤さん側の弁護士が、午前中の加藤さんへの尋問でも、午後の市側への尋問でも同じ質問をしているのだ。
加藤さんには「市の職員から(この用地補償の件について)相談を受けたか?」
市側には「加藤さんに(用地補償の件について)相談をしたか?」と。
そしてその回答が先に書いた、加藤さん「相談を受けた」・市側「相談をしていない」。
ほぉ~・・・・、という気持ちだ。
尋問の最初には裁判官に向って「宣誓」をする。
「真実を述べ、嘘をつかないことを誓う」のだ。
この時は双方の弁護士も、私たち傍聴者も起立を求められた。
多分に形式的、儀式がかっているなぁとは感じたものの、ウソであれば罰を被るものであるらしいし(偽証罪、になるらしい)、法廷での発言はやはり重いモノなのだと改めて感じさせられた。
にも関わらず、互いの証言が食い違うのだ。 一体どういうことか?
どちらかがウソをついているとしか考えられない。
午前の加藤さんの尋問の時には件の2人は傍聴席にはいなかったと記憶しているが、午後の尋問では加藤さんは傍聴席にいた。
果たして市側のこの回答をどういう気持ちで聞いたのか。
なにより、裁判官は双方のこの食い違う回答を本人の口から実際に聞いて、どう感じたのだろうか。
新城市議会や委員会を傍聴に行くと、基本的には傍聴者は黙って聞いていなきゃならないのだが、結構皆さんがやがやと聞こえるような声でつぶやくというか口を開く(笑。
新城市らしくておもしろいのだが、さすがにこの法廷ではそういう声は聞こえない。
この沈黙した空気がまた重みを感じさせる。
という感じで双方の尋問も終わり、一日かかった傍聴も終わった。
次回は8月1日(水)に、今回欠席した現新城市長が法廷に立つ。
一体どんな尋問が行われ、市長はどう答えるのか。
市民のみなさんもぜひ傍聴へ。私も仕事がありますが傍聴に行くべく調整中w
午後の尋問に関しては私の拙いメモや記憶よりも、白井みちひろさんのブログの方がはるかに詳しく正確だ。
→ 白井みちひろ後援会公式ブログ 裁判傍聴記「新城市役所は大丈夫?」(2018年07月19日)
是非こちらを読んでみてください。
今回の記事を書くにあたってネットで色々と検索をしていたらこんなサイトがあった。
→ 民事裁判における当事者尋問の様子
このサイトに書いてあること、まさにこの通りのことが行われていたなぁと再確認できた。
で、こちらのサイトの言葉を借りると、
“次は法廷で尋問手続が行われます。 必ず行われるわけではなく裁判所が必要と認めたときのみですが、事実関係を巡るお互いの主張に隔たりがある場合は、大体行われるものと思っていいです。”
ということは、加藤さんの言い分と市側の言い分に隔たりがあるので今回の尋問が行われた、という事だろう。
ではその隔たりとは何か?
私が傍聴していた記憶とメモによれば、後で補足しますが、今回の焦点である用地補償について、
加藤さんは市側から「相談を受けた」と言っている。
市側は加藤さんに「相談していない」と言っている。
(※加藤さんは市議以外のご自身の仕事として、不動産の関係のお仕事をされていて土地取引のことについて詳しい。市職員もそのことを知っていたからこそ相談した。)
ここの食い違いの事だろうと思っている。
最初の記事に書いた加藤さん側の弁護士が、午前中の加藤さんへの尋問でも、午後の市側への尋問でも同じ質問をしているのだ。
加藤さんには「市の職員から(この用地補償の件について)相談を受けたか?」
市側には「加藤さんに(用地補償の件について)相談をしたか?」と。
そしてその回答が先に書いた、加藤さん「相談を受けた」・市側「相談をしていない」。
ほぉ~・・・・、という気持ちだ。
尋問の最初には裁判官に向って「宣誓」をする。
「真実を述べ、嘘をつかないことを誓う」のだ。
この時は双方の弁護士も、私たち傍聴者も起立を求められた。
多分に形式的、儀式がかっているなぁとは感じたものの、ウソであれば罰を被るものであるらしいし(偽証罪、になるらしい)、法廷での発言はやはり重いモノなのだと改めて感じさせられた。
にも関わらず、互いの証言が食い違うのだ。 一体どういうことか?
どちらかがウソをついているとしか考えられない。
午前の加藤さんの尋問の時には件の2人は傍聴席にはいなかったと記憶しているが、午後の尋問では加藤さんは傍聴席にいた。
果たして市側のこの回答をどういう気持ちで聞いたのか。
なにより、裁判官は双方のこの食い違う回答を本人の口から実際に聞いて、どう感じたのだろうか。
新城市議会や委員会を傍聴に行くと、基本的には傍聴者は黙って聞いていなきゃならないのだが、結構皆さんがやがやと聞こえるような声でつぶやくというか口を開く(笑。
新城市らしくておもしろいのだが、さすがにこの法廷ではそういう声は聞こえない。
この沈黙した空気がまた重みを感じさせる。
という感じで双方の尋問も終わり、一日かかった傍聴も終わった。
次回は8月1日(水)に、今回欠席した現新城市長が法廷に立つ。
一体どんな尋問が行われ、市長はどう答えるのか。
市民のみなさんもぜひ傍聴へ。私も仕事がありますが傍聴に行くべく調整中w
2018年07月30日 Posted by けま at 09:58 │Comments(0) │新庁舎建設
裁判傍聴に行ってきた 2
原告(加藤さん)の弁護士でありながら原告に不利な状況を導き出す悪徳弁護士!
まさか被告側(新城市)の息のかかった輩では?
一体いくら積まれたんだ!
などというのは三文小説でもあり得ない陳腐な設定で、やはり弁護士足る者依頼者に有利な判決を得るべく職務に全力を尽くすのは疑いない。
となればあの加藤さんへの尋問も、あのように“見せる”必要があったのだと考える方が筋が通るのではないか?
考えてみれば判決を下すのは裁判官で、弁護士が依頼者の希望に沿った判決を下してもらうためには、その裁判官に「ウチの依頼者に有利な判決をしてくださいよ!」とアピールをしなくてはならないのではないか?
私たちは尋問場面を傍聴、というか傍観しているだけの存在で、尋問している弁護士にとっては何の配慮もする必要がない。
私たち、つまりこのブログを書いているけまがあの尋問にどういう感想を持とうが関係なくて、裁判官がどのように思ってくれるかが弁護士にとっては一番の関心事なのだと思うのだ。
などと考えると、あの尋問にもまた別な面が見えてくるような・・・・。
前のブログでも書いた「調査をした時には長屋は実在したのか?」という弁護士の質問。
この質問に私は、
→ 「加藤さんが調査を始めた時には長屋は存在していなかったはずなのに、なぜそんな詳しい調査ができたのか?」とでも言いたげな痛いトコロをつく質問
という感想を持ったのだが、これは、
→ 「補償の対象である物件(長屋)がすでに無くなっているにも関わらず、隣近所への地道な聞き込み、物件の持ち主の母親の状況の調査など、粘り強く真実を明らかにするための努力を惜しまなかった」ともアピールできる質問
とも捉えることができるような・・。
さらには、確信は無いのに議会で質問したことやコンサルタントを訪問したことに対して「ホントに悪いコトしていたわけでもないのに疑ってかかっていたってことだよね?」とでも言いたげな質問を重ねたことも、
→ 「少しの疑念であっても、こと市民の税金に関することであれば、市民に負託を受けた議員として疑念がゼロになるまでとことん職務を全うする姿勢」をアピールできるような答えを導き出すような質問を重ねていた
とも捉えることができるような・・(笑。
そして最後には、加藤さんはコンサルタントに関係する人物の使用していたパソコンのバックアップデータから重要な証拠「甲9号証」を発見するに至った。
この「甲9号証」、パソコン内のデータはすでに消去されていたが、パソコンを使用する人たちに共通するバックアップデータが残っていたため、それをしらみつぶしに調査して発見したのだと言う。
面倒な作業だったろうによくもやったものだと、その努力労苦に脱帽してしまう。
こんな風に書くと、前とは逆に「真実を探し当てるために不断の努力を惜しまなかった加藤氏!」みたいな印象を持ってしまいますなぁ(笑。
こんなことをアピールすべく、原告弁護士さんはあのような厳しい感じの質問を“敢えて”行っていたのだろうか?つまり裁判官の前でのパフォーマンスとして。
それとも、元々ああいう言い方で尋問するのがあの弁護士さんのスタイルなのか。
先にも書いた通り私は傍聴していただけなので、弁護士さんのあの尋問の本当の意図はわからないし、あの尋問に裁判官がどういう印象を持ったのかもわからない。
加藤さんへの尋問は午前中に終了して、午後からは市役所側から出廷した2人への尋問があった。
こちらの尋問の感想もまた書きたいと思うが、全体を通しての感想は新城市側にムリがあるような感じだ。
加藤さん側の弁護士の厳しいパフォーマンスが、裁判官に良い心証を与えたであろうことを期待したい。
まさか被告側(新城市)の息のかかった輩では?
一体いくら積まれたんだ!
などというのは三文小説でもあり得ない陳腐な設定で、やはり弁護士足る者依頼者に有利な判決を得るべく職務に全力を尽くすのは疑いない。
となればあの加藤さんへの尋問も、あのように“見せる”必要があったのだと考える方が筋が通るのではないか?
考えてみれば判決を下すのは裁判官で、弁護士が依頼者の希望に沿った判決を下してもらうためには、その裁判官に「ウチの依頼者に有利な判決をしてくださいよ!」とアピールをしなくてはならないのではないか?
私たちは尋問場面を傍聴、というか傍観しているだけの存在で、尋問している弁護士にとっては何の配慮もする必要がない。
私たち、つまりこのブログを書いているけまがあの尋問にどういう感想を持とうが関係なくて、裁判官がどのように思ってくれるかが弁護士にとっては一番の関心事なのだと思うのだ。
などと考えると、あの尋問にもまた別な面が見えてくるような・・・・。
前のブログでも書いた「調査をした時には長屋は実在したのか?」という弁護士の質問。
この質問に私は、
→ 「加藤さんが調査を始めた時には長屋は存在していなかったはずなのに、なぜそんな詳しい調査ができたのか?」とでも言いたげな痛いトコロをつく質問
という感想を持ったのだが、これは、
→ 「補償の対象である物件(長屋)がすでに無くなっているにも関わらず、隣近所への地道な聞き込み、物件の持ち主の母親の状況の調査など、粘り強く真実を明らかにするための努力を惜しまなかった」ともアピールできる質問
とも捉えることができるような・・。
さらには、確信は無いのに議会で質問したことやコンサルタントを訪問したことに対して「ホントに悪いコトしていたわけでもないのに疑ってかかっていたってことだよね?」とでも言いたげな質問を重ねたことも、
→ 「少しの疑念であっても、こと市民の税金に関することであれば、市民に負託を受けた議員として疑念がゼロになるまでとことん職務を全うする姿勢」をアピールできるような答えを導き出すような質問を重ねていた
とも捉えることができるような・・(笑。
そして最後には、加藤さんはコンサルタントに関係する人物の使用していたパソコンのバックアップデータから重要な証拠「甲9号証」を発見するに至った。
この「甲9号証」、パソコン内のデータはすでに消去されていたが、パソコンを使用する人たちに共通するバックアップデータが残っていたため、それをしらみつぶしに調査して発見したのだと言う。
面倒な作業だったろうによくもやったものだと、その努力労苦に脱帽してしまう。
こんな風に書くと、前とは逆に「真実を探し当てるために不断の努力を惜しまなかった加藤氏!」みたいな印象を持ってしまいますなぁ(笑。
こんなことをアピールすべく、原告弁護士さんはあのような厳しい感じの質問を“敢えて”行っていたのだろうか?つまり裁判官の前でのパフォーマンスとして。
それとも、元々ああいう言い方で尋問するのがあの弁護士さんのスタイルなのか。
先にも書いた通り私は傍聴していただけなので、弁護士さんのあの尋問の本当の意図はわからないし、あの尋問に裁判官がどういう印象を持ったのかもわからない。
加藤さんへの尋問は午前中に終了して、午後からは市役所側から出廷した2人への尋問があった。
こちらの尋問の感想もまた書きたいと思うが、全体を通しての感想は新城市側にムリがあるような感じだ。
加藤さん側の弁護士の厳しいパフォーマンスが、裁判官に良い心証を与えたであろうことを期待したい。
2018年07月29日 Posted by けま at 03:36 │Comments(0) │新庁舎建設
裁判傍聴に行ってきた
お誘いを受けて7月18日、名古屋地裁での裁判傍聴に行ってきた。
この話を聞かせてもらった時には現新城市長も法廷に立つとのことで、いつも自信満々で弁の立つ彼が一体どう尋問に答えるのかものすごく興味が湧き、二つ返事で同行させてもらうことに決めた。
・・・のだが、生憎市長は公務のために今回は欠席とのことで当初の野次馬的な目論見はハズレてしまった(笑。
しかし生まれて初めての裁判傍聴は良い経験・勉強になった。
名古屋地裁地下の食堂は安くてウマかった。
この日の詳しいことや正確な情報は白井さんの「白井みちひろ後援会公式ブログ」で紹介されているので、ぜひ読んでみてください。
→ 裁判傍聴記「新城市役所は大丈夫?」
私の方では以前この件について書いてはいるものの新聞記事以上の情報は知り得ていないので、かなり個人的な印象・感想を書いてみたいと思う。
→9月28日朝刊の記事
→9月28日朝刊の記事 2
→事実と全容
最初に中央の証言台に立ったのは、この裁判を訴えた側(原告)の加藤元市議。
私のいる傍聴席から見て左側の席にいる弁護士から加藤市議への尋問が始まった。
弁護士は立って尋問を行う。
証言台に座る加藤さんの左側すぐそばに立ち、上から見下ろすような形でいろいろ聞く。
上から見下ろす形はかなり高圧的な印象を受ける。これは人前で話すことに慣れた加藤元市議でさえもかなりプレッシャーを感ずるのではないかと心配してしまう。
さて案の定というか、この尋問がなかなか厳しい口調・印象を受けるモノで、特に出来事の日にちを詳細に尋ねるものだから加藤さんもなかなか思い出せないようで苦労していた。
傍聴しながら印象に残ったのはこちらの弁護士の言い放った「この甲9号証(“証”で合ってるかわからない)が一番大事なんだ!」(バンッ!っと書類を叩きつける音)
・・・いや、実際こんな書類を叩きつけるようなことはしなかったのだけどw、それくらいの激しさを感じさせる勢いで加藤さんに迫っている印象を受けた。
そんなものだから、私はてっきりこの弁護士が訴えられた側(新城市=被告)の弁護士だと思い、
「さすが敵側の弁護士、なかなか好戦的だ。加藤さんもタジタジだ。」
などと思っていたのだが、実はこの弁護士が加藤さん側の弁護士なのだと後から知ったw
それにしても加藤さんを弁護する側、すなわち味方と言っていい人なのに、なぜこんな激しい感じで迫ったのだろうか?
そのことを書く前に色々と説明しておこう。
先ほど書いた「甲9号証」というのはこの裁判で用いられていた言葉で、最初は何を指しているのかわからなかったが、どうもコンサルタントの報告書を指しているらしいことが傍聴していてわかった。
もうひとつ「乙15号証」という言葉も出てきていて、これも同じくコンサルタントの報告書を指しているらしいこともわかった。
コンサルタント、と言われてもこの事件を知らないと「なんのことやら?」でしょうな。
この事件は簡単に書くと、
1・新城市がとある用地の移転補償の適不適の調査をコンサルタントに依頼した。
2・その報告書が実は2種類存在していて、最初に提出されたモノは「補償に適さない」、その後提出されたモノは「補償に適する」と報告されていた。
3・新城市は後から提出された「適する」報告書に従って用地補償を行った。
こんな感じだ。
つまり、なぜ後から提出された報告書を新城市は採用したのか。最初の報告では不適だったじゃないか、なぜだ?おかしいじゃないか? というのが原告加藤さんの主張だ。
で、先ほどの「甲9号証」=「適さない」報告書 「乙15号証」=「適する」報告書 と対応している。
新城市は「乙15号証」を元に用地補償を行ったことになる。
そして加藤さんは「甲9号証」という報告書を後に発見して、それを証拠として新城市の用地補償のおかしさを訴えたわけなのだな。
加藤さんの弁護士の尋問ではこの「甲9号証」が“何時(いつ)”発見されたのか? を、質問を重ねて特定していく流れであったように思う。
傍聴したものをメモったものなので日付を聞き間違えているかもしれないけれども、
平成24年2月 コンサルタントが調査を行う
平成24年6月 報告書(乙15号証)提出
平成27年3月31日 用地賠償でその対象になった「長屋」はこの日までには壊されていた。
平成27年6月 太田さんから資料の調査依頼を受けた ※ここで加藤さんは用地賠償の不自然さに気づく
平成28年3月 加藤さんが用地賠償の件を議会で質問
平成28年5月 調査のためコンサルタントを訪問
平成28年6月 「甲9号証」を発見
以上のことが尋問から確認された。
日付の確認の途中途中ではこれらの事柄の内容や関係することについても弁護士から尋問された。
例えば、「平成28年5月 調査のためコンサルタントを訪問」。
これは加藤さんが用地賠償の実態を独自に調査したうちのひとつなのだが、そういった調査の内のひとつに「長屋には生活実態がなかったことを突き止めた」ものがあった。
このことについても弁護士は、「調査をした時には長屋は実在したのか?」という質問をした。
加藤さんは決してウソをついていたわけではないのだが、口ぶりからは長屋に踏み込んでその実態を調べた、という印象を受けるモノだったのは確かだった。
つまり「加藤さんが調査を始めた時には長屋は存在していなかったはずなのに、なぜそんな詳しい調査ができたのか?」とでも言いたげな質問なのだ。
(上の時系列を見ればわかるように、加藤さんが調査依頼を受けた時(平成27年6月)にはもう長屋は壊されていた)
味方なのに、やたら痛いトコロを突いてくるのだ。
実際は確かに長屋本体を調べたことはないのだけれども、隣近所からの聞き込みや、その長屋に将来的に住むと言われていた長屋の持ち主の母親が実は養護施設に入っていて到底住むことはできない状態であることを、実際に養護施設まで足を運ぶなどして詳しい調査を行っている。
そして「長屋に生活実態がない」という重要な情報はことを加藤さんは突きとめているのだけどね。
加藤さんが用地賠償のおかしさを“確信”するに至ったのは「甲9号証」の発見だったのだが、これについてもいやらしく尋問している。
例えば平成28年3月での議会での質問でも、用地補償のおかしさを“確信”して質問したわけではないし、平成28年5月にコンサルを訪問した時も、用地補償のおかしさを“確信”していたわけではなかった。
というようなことを弁護士の質問から導かれ答えさせられていた感じだ。
この「確信していたわけではないんですね?」という感じの弁護士の言い方がまたいやらしい感じで、「ホントに悪いコトしていたわけでもないのに疑ってかかっていたってことだよね?」とでも言いたげな感じなのだ。
この弁護士が加藤さん側の人とは知らずに傍聴していた私は、
「うわー、敵の弁護士の巧妙なことよ。まるで加藤さんが悪人だよ。」
などと気が気ではなかったのだ、この時、マジで。
で、尋問というのはこの後、「これで終わります」みたいな感じで、割とあっさり終わる。
「すなわちこの人が悪いんです!」的な決めつける言葉を言う事なく結構唐突な感じで終わるのだ。
この後の弁護士、つまり新城市側(被告)の弁護士の方はこんな感じの鋭い迫り方をしない感じで、実はよくメモを取っていなくて、なんて言ったかよく覚えていない。
あらら、加藤さん不利なんじゃないの、なんて思っていたら先に書いた通り、最初に尋問した弁護士が加藤さんの弁護士だったと知った。
となると、ますます疑問が膨らむ。
あの加藤さんを不利に印象付けるような尋問はなんだったのか?
そう感じてしまう私は素人なのか・・・(もちろん素人なんだけどw)?
長くなったので続く。
この話を聞かせてもらった時には現新城市長も法廷に立つとのことで、いつも自信満々で弁の立つ彼が一体どう尋問に答えるのかものすごく興味が湧き、二つ返事で同行させてもらうことに決めた。
・・・のだが、生憎市長は公務のために今回は欠席とのことで当初の野次馬的な目論見はハズレてしまった(笑。
しかし生まれて初めての裁判傍聴は良い経験・勉強になった。
名古屋地裁地下の食堂は安くてウマかった。
この日の詳しいことや正確な情報は白井さんの「白井みちひろ後援会公式ブログ」で紹介されているので、ぜひ読んでみてください。
→ 裁判傍聴記「新城市役所は大丈夫?」
私の方では以前この件について書いてはいるものの新聞記事以上の情報は知り得ていないので、かなり個人的な印象・感想を書いてみたいと思う。
→9月28日朝刊の記事
→9月28日朝刊の記事 2
→事実と全容
最初に中央の証言台に立ったのは、この裁判を訴えた側(原告)の加藤元市議。
私のいる傍聴席から見て左側の席にいる弁護士から加藤市議への尋問が始まった。
弁護士は立って尋問を行う。
証言台に座る加藤さんの左側すぐそばに立ち、上から見下ろすような形でいろいろ聞く。
上から見下ろす形はかなり高圧的な印象を受ける。これは人前で話すことに慣れた加藤元市議でさえもかなりプレッシャーを感ずるのではないかと心配してしまう。
さて案の定というか、この尋問がなかなか厳しい口調・印象を受けるモノで、特に出来事の日にちを詳細に尋ねるものだから加藤さんもなかなか思い出せないようで苦労していた。
傍聴しながら印象に残ったのはこちらの弁護士の言い放った「この甲9号証(“証”で合ってるかわからない)が一番大事なんだ!」(バンッ!っと書類を叩きつける音)
・・・いや、実際こんな書類を叩きつけるようなことはしなかったのだけどw、それくらいの激しさを感じさせる勢いで加藤さんに迫っている印象を受けた。
そんなものだから、私はてっきりこの弁護士が訴えられた側(新城市=被告)の弁護士だと思い、
「さすが敵側の弁護士、なかなか好戦的だ。加藤さんもタジタジだ。」
などと思っていたのだが、実はこの弁護士が加藤さん側の弁護士なのだと後から知ったw
それにしても加藤さんを弁護する側、すなわち味方と言っていい人なのに、なぜこんな激しい感じで迫ったのだろうか?
そのことを書く前に色々と説明しておこう。
先ほど書いた「甲9号証」というのはこの裁判で用いられていた言葉で、最初は何を指しているのかわからなかったが、どうもコンサルタントの報告書を指しているらしいことが傍聴していてわかった。
もうひとつ「乙15号証」という言葉も出てきていて、これも同じくコンサルタントの報告書を指しているらしいこともわかった。
コンサルタント、と言われてもこの事件を知らないと「なんのことやら?」でしょうな。
この事件は簡単に書くと、
1・新城市がとある用地の移転補償の適不適の調査をコンサルタントに依頼した。
2・その報告書が実は2種類存在していて、最初に提出されたモノは「補償に適さない」、その後提出されたモノは「補償に適する」と報告されていた。
3・新城市は後から提出された「適する」報告書に従って用地補償を行った。
こんな感じだ。
つまり、なぜ後から提出された報告書を新城市は採用したのか。最初の報告では不適だったじゃないか、なぜだ?おかしいじゃないか? というのが原告加藤さんの主張だ。
で、先ほどの「甲9号証」=「適さない」報告書 「乙15号証」=「適する」報告書 と対応している。
新城市は「乙15号証」を元に用地補償を行ったことになる。
そして加藤さんは「甲9号証」という報告書を後に発見して、それを証拠として新城市の用地補償のおかしさを訴えたわけなのだな。
加藤さんの弁護士の尋問ではこの「甲9号証」が“何時(いつ)”発見されたのか? を、質問を重ねて特定していく流れであったように思う。
傍聴したものをメモったものなので日付を聞き間違えているかもしれないけれども、
平成24年2月 コンサルタントが調査を行う
平成24年6月 報告書(乙15号証)提出
平成27年3月31日 用地賠償でその対象になった「長屋」はこの日までには壊されていた。
平成27年6月 太田さんから資料の調査依頼を受けた ※ここで加藤さんは用地賠償の不自然さに気づく
平成28年3月 加藤さんが用地賠償の件を議会で質問
平成28年5月 調査のためコンサルタントを訪問
平成28年6月 「甲9号証」を発見
以上のことが尋問から確認された。
日付の確認の途中途中ではこれらの事柄の内容や関係することについても弁護士から尋問された。
例えば、「平成28年5月 調査のためコンサルタントを訪問」。
これは加藤さんが用地賠償の実態を独自に調査したうちのひとつなのだが、そういった調査の内のひとつに「長屋には生活実態がなかったことを突き止めた」ものがあった。
このことについても弁護士は、「調査をした時には長屋は実在したのか?」という質問をした。
加藤さんは決してウソをついていたわけではないのだが、口ぶりからは長屋に踏み込んでその実態を調べた、という印象を受けるモノだったのは確かだった。
つまり「加藤さんが調査を始めた時には長屋は存在していなかったはずなのに、なぜそんな詳しい調査ができたのか?」とでも言いたげな質問なのだ。
(上の時系列を見ればわかるように、加藤さんが調査依頼を受けた時(平成27年6月)にはもう長屋は壊されていた)
味方なのに、やたら痛いトコロを突いてくるのだ。
実際は確かに長屋本体を調べたことはないのだけれども、隣近所からの聞き込みや、その長屋に将来的に住むと言われていた長屋の持ち主の母親が実は養護施設に入っていて到底住むことはできない状態であることを、実際に養護施設まで足を運ぶなどして詳しい調査を行っている。
そして「長屋に生活実態がない」という重要な情報はことを加藤さんは突きとめているのだけどね。
加藤さんが用地賠償のおかしさを“確信”するに至ったのは「甲9号証」の発見だったのだが、これについてもいやらしく尋問している。
例えば平成28年3月での議会での質問でも、用地補償のおかしさを“確信”して質問したわけではないし、平成28年5月にコンサルを訪問した時も、用地補償のおかしさを“確信”していたわけではなかった。
というようなことを弁護士の質問から導かれ答えさせられていた感じだ。
この「確信していたわけではないんですね?」という感じの弁護士の言い方がまたいやらしい感じで、「ホントに悪いコトしていたわけでもないのに疑ってかかっていたってことだよね?」とでも言いたげな感じなのだ。
この弁護士が加藤さん側の人とは知らずに傍聴していた私は、
「うわー、敵の弁護士の巧妙なことよ。まるで加藤さんが悪人だよ。」
などと気が気ではなかったのだ、この時、マジで。
で、尋問というのはこの後、「これで終わります」みたいな感じで、割とあっさり終わる。
「すなわちこの人が悪いんです!」的な決めつける言葉を言う事なく結構唐突な感じで終わるのだ。
この後の弁護士、つまり新城市側(被告)の弁護士の方はこんな感じの鋭い迫り方をしない感じで、実はよくメモを取っていなくて、なんて言ったかよく覚えていない。
あらら、加藤さん不利なんじゃないの、なんて思っていたら先に書いた通り、最初に尋問した弁護士が加藤さんの弁護士だったと知った。
となると、ますます疑問が膨らむ。
あの加藤さんを不利に印象付けるような尋問はなんだったのか?
そう感じてしまう私は素人なのか・・・(もちろん素人なんだけどw)?
長くなったので続く。
2018年07月26日 Posted by けま at 05:07 │Comments(0) │新庁舎建設
東庁舎改修事業費、一体誰が?
少し前の記事になるけれども、お馴染みの新城市議会議員 浅尾洋平さんがまたまたすっぱ抜いてくれた。
「東庁舎改修工事費用に2億円以上?!」
→ http://asao.dosugoi.net/e904184.html
(浅井洋平さんのブログ「浅尾洋平の日々こつこつと。」より)
なんだかスゴイ計画ですな。
東庁舎は住民投票の結果として残すことになった庁舎だ。
その結果の趣旨とは「なるべく無駄な費用をかけない新庁舎建設」というものだ。
ならば、常識的に考えて、約2億円もの改修事業費は高すぎる。
浅尾議員の反論はごもっともだ。
議場には何回か傍聴に行ったことはあるけれども、空調の効きが悪いなぁと感じたことはある。
その辺の感覚で、空調設備工事をすることには、まぁイイだろうとも思う。
議場を仕事の場としている議員さん方の感覚で、仕事をより効率よく気分よく進められるための改修なら、それは結構なことだと思う。
どんどん議論してほしい。
しかし、それが「部会」とかいう私たち市民の見えないところで議論が行われ、見えないのをイイことに住民投票結果の趣旨を忘れ、内定的な決定が行われ、議会に出てきたときにはもう変更の余地のない状態になってしまっている、とか。
こういう事態が今の新城市議会においては非常に強く懸念されるし、だ か ら 非常に腹立たしいのだ。
腹立たしさを少し静めて、順を追って考えてみよう。この改修事業は一体誰が要望したものなのだろうか?
浅尾議員のブログを読むと、
「議決権のない「全協」で「議員止め」資料を渡し、3ヶ月後の「部会」(傍聴者・議事録なし)で「資料」に沿って予算要望する新城市議会!」
と書いてあって、どうも要望したのは「議会」のようなのだが、ならばなぜ浅尾議員が今の際まで知らなかったのか?と疑問に思うのだが・・・。
ま、浅尾議員はあまりに正直すぎて、議会に不利な内容までこんな感じですっぱ抜くから、ハブにされてたのかもしれないけど。
改修事業の内容的には、加藤議員、白井議員あたりも反対の立場を取るように思うけれども今のところはそういう声も聞こえず。
この資料に見るような具体的な事業内容は、市議会事務局が上げてきたものらしい。
これはfacebookの「考えよう!しんしろ新市庁舎」の10月19日の記事からわかる。
→ https://www.facebook.com/sincityhall/posts/1124387937615252
「新城市新庁舎建設工事 近隣説明会」でこのことについて質問してくれたようだ。
では、それは事務局が議員を無視して考えたのか、議員全員の総意を酌んで事務局が考えたのか、ある一部の議員の要望から事務局が考えたのか。
真相はどこにあるのだろうか。
部会での会議が密室になってしまうのは現状では仕方ないにしても、その次の段階は「総合政策特別委員会」になるだろう。
そこで、「誰が」言いだしっぺなのかをはっきりさせて、「なぜ」この改修事業が必要なのかをしっかり議論してほしいものだ。
「東庁舎改修工事費用に2億円以上?!」
→ http://asao.dosugoi.net/e904184.html
(浅井洋平さんのブログ「浅尾洋平の日々こつこつと。」より)
なんだかスゴイ計画ですな。
東庁舎は住民投票の結果として残すことになった庁舎だ。
その結果の趣旨とは「なるべく無駄な費用をかけない新庁舎建設」というものだ。
ならば、常識的に考えて、約2億円もの改修事業費は高すぎる。
浅尾議員の反論はごもっともだ。
議場には何回か傍聴に行ったことはあるけれども、空調の効きが悪いなぁと感じたことはある。
その辺の感覚で、空調設備工事をすることには、まぁイイだろうとも思う。
議場を仕事の場としている議員さん方の感覚で、仕事をより効率よく気分よく進められるための改修なら、それは結構なことだと思う。
どんどん議論してほしい。
しかし、それが「部会」とかいう私たち市民の見えないところで議論が行われ、見えないのをイイことに住民投票結果の趣旨を忘れ、内定的な決定が行われ、議会に出てきたときにはもう変更の余地のない状態になってしまっている、とか。
こういう事態が今の新城市議会においては非常に強く懸念されるし、だ か ら 非常に腹立たしいのだ。
腹立たしさを少し静めて、順を追って考えてみよう。この改修事業は一体誰が要望したものなのだろうか?
浅尾議員のブログを読むと、
「議決権のない「全協」で「議員止め」資料を渡し、3ヶ月後の「部会」(傍聴者・議事録なし)で「資料」に沿って予算要望する新城市議会!」
と書いてあって、どうも要望したのは「議会」のようなのだが、ならばなぜ浅尾議員が今の際まで知らなかったのか?と疑問に思うのだが・・・。
ま、浅尾議員はあまりに正直すぎて、議会に不利な内容までこんな感じですっぱ抜くから、ハブにされてたのかもしれないけど。
改修事業の内容的には、加藤議員、白井議員あたりも反対の立場を取るように思うけれども今のところはそういう声も聞こえず。
この資料に見るような具体的な事業内容は、市議会事務局が上げてきたものらしい。
これはfacebookの「考えよう!しんしろ新市庁舎」の10月19日の記事からわかる。
→ https://www.facebook.com/sincityhall/posts/1124387937615252
「新城市新庁舎建設工事 近隣説明会」でこのことについて質問してくれたようだ。
では、それは事務局が議員を無視して考えたのか、議員全員の総意を酌んで事務局が考えたのか、ある一部の議員の要望から事務局が考えたのか。
真相はどこにあるのだろうか。
部会での会議が密室になってしまうのは現状では仕方ないにしても、その次の段階は「総合政策特別委員会」になるだろう。
そこで、「誰が」言いだしっぺなのかをはっきりさせて、「なぜ」この改修事業が必要なのかをしっかり議論してほしいものだ。
2016年10月20日 Posted by けま at 10:38 │Comments(0) │新庁舎建設
事実と全容
今回もしつこく、監査請求の新聞記事のはなし。
元記事はこちら、パパさんのブログ → 「今日の朝刊記事(住民監査請求に関する)」(「パパゲーノの夢」より)
ほとんどの人は新聞記事に書いてあることは事実であり、それが事柄の全容だと思っているだろう。
事実であることは確かなのだが、例えば記事に出てくる「平屋の建物」という言葉。
この言葉だけで具体的にどういう建物かわかる人はまずいないだろう
きっと各々の常識的な想像で「平屋の建物像」を補完して、そのまま特に疑問も持たないでいるに違いない。
ではこの「平屋の建物」について、リンクしてある加藤市議の一般質問の議事録からわかることを抜き出してみよう。
箇条書きにしてみると、
1・「母屋(事業用地内)」と「離れ(事業用地外)」は同時期に(補償のための)調査していない。
2・「離れ」は「借家」で「4軒長屋」
3・「住まいがなされていない」→人が住んでいる形跡がない
「借家で4軒長屋」だそうだ。
一 体 誰 が、 「平屋の建物」、しかも「母屋と離れのような関係」という言葉から「借家の4軒長屋」を想像するだろうか。
しかも「住まいがなされていない」のだそうだ。
と、こうなるとなぜこのことが新聞では書かれなかったのか? と、誰もが思うだろう。
んー? なぜだ(笑
整理してみると、加藤市議の議会での質問によって明らかにされた「住まいがなされてない4軒長屋」は、加藤市議が独自に調査してわかったことだ。
一方この「住まいがなされていない4軒長屋」は、コンサルタント会社も調査し報告書を市に提出している。
しかしその報告書では、加藤市議の調査したところの「住まいがなされていない4軒長屋」という部分が黒塗りされていて『わかっていない』。
この『わかっていない部分について監査請求をした』、という事。
これが新聞記事が一番に伝えたいところ、新聞記事の主題、といっていいだろうか。
黒塗りされてわかっていない部分があるのに、そのわかっていない部分を「4軒長屋」と具体的には書けなかった、ということだろうか。
なんだか理屈をこねくり回しているようで、自分でも書いててめまいがするようだ。
しかしこうしないと、記事の主題と矛盾が生じる、か・・・。
新聞記事に書かれていること、ニュースで報道されることなどなど、メディアの発表は事実ではあるが、全てではない。
こんなことが今回の事件から見て取れる。
気になる事件は、今回のように詳しい人のブログとか、議事録のような別のソースで調べるクセをつけないといけないな。
しかしこの事件。
加藤市議の調査による「住まいがなされていない4軒長屋」、つまり常識的に補償基準を満たす物件ではないのに、実際に1200万円の補償がすでに行われている。
一体報告書にはどのように書かれているのだろうか?
そしてその書かれていることを、「補償基準を満たす」と判断した市は正しかったのか。
監査請求が正式に受理されれば11月26日までに結果が出るとのこと。
どういう事実があったのか、発表が待たれる。
元記事はこちら、パパさんのブログ → 「今日の朝刊記事(住民監査請求に関する)」(「パパゲーノの夢」より)
ほとんどの人は新聞記事に書いてあることは事実であり、それが事柄の全容だと思っているだろう。
事実であることは確かなのだが、例えば記事に出てくる「平屋の建物」という言葉。
この言葉だけで具体的にどういう建物かわかる人はまずいないだろう
きっと各々の常識的な想像で「平屋の建物像」を補完して、そのまま特に疑問も持たないでいるに違いない。
ではこの「平屋の建物」について、リンクしてある加藤市議の一般質問の議事録からわかることを抜き出してみよう。
箇条書きにしてみると、
1・「母屋(事業用地内)」と「離れ(事業用地外)」は同時期に(補償のための)調査していない。
2・「離れ」は「借家」で「4軒長屋」
3・「住まいがなされていない」→人が住んでいる形跡がない
「借家で4軒長屋」だそうだ。
一 体 誰 が、 「平屋の建物」、しかも「母屋と離れのような関係」という言葉から「借家の4軒長屋」を想像するだろうか。
しかも「住まいがなされていない」のだそうだ。
と、こうなるとなぜこのことが新聞では書かれなかったのか? と、誰もが思うだろう。
んー? なぜだ(笑
整理してみると、加藤市議の議会での質問によって明らかにされた「住まいがなされてない4軒長屋」は、加藤市議が独自に調査してわかったことだ。
一方この「住まいがなされていない4軒長屋」は、コンサルタント会社も調査し報告書を市に提出している。
しかしその報告書では、加藤市議の調査したところの「住まいがなされていない4軒長屋」という部分が黒塗りされていて『わかっていない』。
この『わかっていない部分について監査請求をした』、という事。
これが新聞記事が一番に伝えたいところ、新聞記事の主題、といっていいだろうか。
黒塗りされてわかっていない部分があるのに、そのわかっていない部分を「4軒長屋」と具体的には書けなかった、ということだろうか。
なんだか理屈をこねくり回しているようで、自分でも書いててめまいがするようだ。
しかしこうしないと、記事の主題と矛盾が生じる、か・・・。
新聞記事に書かれていること、ニュースで報道されることなどなど、メディアの発表は事実ではあるが、全てではない。
こんなことが今回の事件から見て取れる。
気になる事件は、今回のように詳しい人のブログとか、議事録のような別のソースで調べるクセをつけないといけないな。
しかしこの事件。
加藤市議の調査による「住まいがなされていない4軒長屋」、つまり常識的に補償基準を満たす物件ではないのに、実際に1200万円の補償がすでに行われている。
一体報告書にはどのように書かれているのだろうか?
そしてその書かれていることを、「補償基準を満たす」と判断した市は正しかったのか。
監査請求が正式に受理されれば11月26日までに結果が出るとのこと。
どういう事実があったのか、発表が待たれる。
2016年10月07日 Posted by けま at 12:40 │Comments(0) │新庁舎建設│市政を考える
9月28日朝刊の記事 2
予定地外の平屋の建物の所有者さんに対して実際に補償はすでに支払われているのだから、その「居住実態」は補償理由に値したのだろう。
その理由を確認するために、加藤市議をはじめとする皆さんはその補償理由の書かれた報告書の情報開示請求を行った、と記事にある。
ところが開示されたものは、肝心の理由部分が非開示(黒々と墨塗りされていた)だったワケなのだ。
こうなってくると市の態度に疑いを持たざるを得なくなる。
新聞記事ではこの補償に関する調査をコンサルタント会社に依頼したようで、その報告書は市に渡された。
市が直接調査をしたのではないのだな。
市が自ら書いたモノなら、書いたモノの責任は市にある。
だから見せちゃマズイものに、市自らスミを塗るのはわかる。
しかし報告書は市とは全く別のコンサルタント会社が書いたモノで、書いたモノの責任はコンサルタントにある。
市は別に隠す必要はなく、「コンサルタントがこんな風に報告してきたので私ら(市)はそれに基づいたまでの事ですぅ。」
としていればイイんじゃないか?
なぜ他人が書いたモノに、市がスミを塗るのだ?(非開示なのだ?)
考えられることは、「その報告書に書かれていることは、市にも責任があるから」しかないだろう。
くどいようだけれども、報告書はコンサルタントが作ったものでその内容に対して市には何も責任はない。
市に責任があるとしたら、
・個人のプライバシーに関することが書かれている部分なので非開示にした。
これは昨今の風潮からすれば十分あり得る。
非開示だけれどもそのスミ塗り報告書の下には「居住実態あり」と書かれており、それに基づき市は補償を行った。
市の対応に何の問題も無し。加藤市議らも納得。
これぐらいしかないだろう。
しかし加藤市議らは一度は情報開示請求を行い、実際にスミ塗り文を読んでいる。
プライバシー部分だけが非開示になっているわけではないと踏んだからこそ、監査請求を行なったはずだ。
加藤市議らは何か切り札的なモノを握っているのではないか?
あと考えられるのは、
・報告書の内容に対して市からなんらかの指示が出されていた。
指示、もしくは依頼して、それを盛り込んだ報告書だからこそ市も責任があると考え非開示部分を設けたのだ。
「責任がある」というより「バレたらマズイ」という感覚だろう。
一体バレたらマズイことって何なのだ?
それは非開示部分で、新聞記事によれば「補償理由」だ。
バレたらマズイ「補償理由」ってなんだ?
このバレたらマズイ補償理由と、加藤市議たちが「行政裁判にすることも検討している」という覚悟がこの事件の重要なカギだろう。
行方を注視していきたい。
その理由を確認するために、加藤市議をはじめとする皆さんはその補償理由の書かれた報告書の情報開示請求を行った、と記事にある。
ところが開示されたものは、肝心の理由部分が非開示(黒々と墨塗りされていた)だったワケなのだ。
こうなってくると市の態度に疑いを持たざるを得なくなる。
新聞記事ではこの補償に関する調査をコンサルタント会社に依頼したようで、その報告書は市に渡された。
市が直接調査をしたのではないのだな。
市が自ら書いたモノなら、書いたモノの責任は市にある。
だから見せちゃマズイものに、市自らスミを塗るのはわかる。
しかし報告書は市とは全く別のコンサルタント会社が書いたモノで、書いたモノの責任はコンサルタントにある。
市は別に隠す必要はなく、「コンサルタントがこんな風に報告してきたので私ら(市)はそれに基づいたまでの事ですぅ。」
としていればイイんじゃないか?
なぜ他人が書いたモノに、市がスミを塗るのだ?(非開示なのだ?)
考えられることは、「その報告書に書かれていることは、市にも責任があるから」しかないだろう。
くどいようだけれども、報告書はコンサルタントが作ったものでその内容に対して市には何も責任はない。
市に責任があるとしたら、
・個人のプライバシーに関することが書かれている部分なので非開示にした。
これは昨今の風潮からすれば十分あり得る。
非開示だけれどもそのスミ塗り報告書の下には「居住実態あり」と書かれており、それに基づき市は補償を行った。
市の対応に何の問題も無し。加藤市議らも納得。
これぐらいしかないだろう。
しかし加藤市議らは一度は情報開示請求を行い、実際にスミ塗り文を読んでいる。
プライバシー部分だけが非開示になっているわけではないと踏んだからこそ、監査請求を行なったはずだ。
加藤市議らは何か切り札的なモノを握っているのではないか?
あと考えられるのは、
・報告書の内容に対して市からなんらかの指示が出されていた。
指示、もしくは依頼して、それを盛り込んだ報告書だからこそ市も責任があると考え非開示部分を設けたのだ。
「責任がある」というより「バレたらマズイ」という感覚だろう。
一体バレたらマズイことって何なのだ?
それは非開示部分で、新聞記事によれば「補償理由」だ。
バレたらマズイ「補償理由」ってなんだ?
このバレたらマズイ補償理由と、加藤市議たちが「行政裁判にすることも検討している」という覚悟がこの事件の重要なカギだろう。
行方を注視していきたい。
2016年09月30日 Posted by けま at 12:43 │Comments(0) │新庁舎建設
9月28日朝刊の記事
新城新庁舎建設に伴う用地補償について、疑わしい事柄があるようだ。
これはパパパさんのブログに経緯が詳しく書かれており、新聞記事の切り抜きも載っていて事柄の中身がわかる。
→「今日の朝刊記事(住民監査請求に関する)」 http://pensee.dosugoi.net/e902389.html(「パパゲーノの夢」より)
まず確認しておきたいのは記事で使われている「事業用地」という言葉だ。
「用地補償」とか「用地取得」とか「用地買収」とかいう言葉に使われている「用地」。
ま、当たり前なんだけど、これは「新庁舎建設のために必要な土地」のこと。
もっと具体的に言うと、今は取り壊してなくなっている市民体育館の南側に「新たに取得した土地」のこと、だ。
「事業用地」には新庁舎が建てられるわけだから、「建設予定地」とも書かれている。
さてこの「事業用地」=「建設予定地」。
ここに昔から住んでいた人にはどこかに移転してもらわなければならないので、市から補償が支払われることになった。
これは当然のことで、よく理解できる。
しかしこの「事業用地」=「建設予定地」の『外』の『物件』に対しても補償が支払われているケースがあるらしい。
?? ちょっとわからんゾ。
なぜ「事業用地」『外』の物件(建物)に補償が支払われるんだ?
私の家は市内野田にあって十分「事業用地外」だけれども、この私の家(物件)にも補償が支払われる可能性があった、ってことか!?
しまった!もらい損ねたワイ・・・。
とヒートアップしてしまいそうな頭を冷やしつつ、中日新聞の記事をよっく読んでみると市用地開発課担当の人がこう言っている。
「用地の内外で建物を一体的に利用する場合は補償の対象になり得る。」
「今回のケースは母屋と離れのような関係で住める状態と判断して補償した。」※1
なるほど、母屋と離れ、みたいな関係は「建物を一体的に利用する場合」に相当するわけか。
そして市用地開発課の人の説明の前段ではこう書いてある。
「平屋の建物の所有者は用地内に住居があり、」
(この「所有者」は用地内に住んでるから補償を受ける対象なのだな。)
「平屋でも家族が居住していたとして、市が補償した」※2
(そうか、この「平屋」が、「所有者」の住居を母屋とすると離れに当たるわけか。)
ん? 「平屋の建物」ってなんだ?
新聞記事の最初にこう書いてある。
「建設予定地外にあった『平屋の建物』の所有者に対して市が補償を支払った・・」
あー、そうか。この「平屋の建物」が「離れ」で、「平屋の建物=離れ」が「予定地外」なのか。
ようやく繋がった。なんで最初からよく読まないんだ、オレw
「母屋と離れ」を常識的に解釈すれば、同じ土地に二棟あるパターンとか、同じ土地でなくても狭い道を挟んでの二棟で家族ともども行き交っているとか、そんな感じだろうか。
この所有者さんの家もそんな実態だったのだろう(好意的に解釈)。
「用地内に母屋があり野田に離れがあるので、野田の離れを立て直す費用も補償してほしい!」と言ってもこれは「母屋と離れ」と言うにはあまりに無理スジな話というわけか(笑。
ん? じゃあこの新聞記事まとめるとこんな感じだと思うが・・・
↓
「平屋の建物」は用地外だから、本来は補償の対象ではない。
しかし「母屋と離れ」を適用できるパターンとして、「離れ=平屋の建物」は用地外だけれども補償の対象になった。
一体この記事の何が問題なワケ? なにか見落としてるか?
そこでもう一度記事をよっく読むと、多分これではないかと。
・「平屋でも『家族が居住していた』として」←※2
・「母屋と離れのような関係で『住める状態』と判断して」←※1
・「加藤市議らは平屋の建物の『居住実態』についても争う」←新聞記事最後の段
離れに「家族が住んでいたのか?」、離れが「住める状態であればいいのか?」
というような「居住実態」が重要なカギになっているようだ。
長くなったので続く。
これはパパパさんのブログに経緯が詳しく書かれており、新聞記事の切り抜きも載っていて事柄の中身がわかる。
→「今日の朝刊記事(住民監査請求に関する)」 http://pensee.dosugoi.net/e902389.html(「パパゲーノの夢」より)
まず確認しておきたいのは記事で使われている「事業用地」という言葉だ。
「用地補償」とか「用地取得」とか「用地買収」とかいう言葉に使われている「用地」。
ま、当たり前なんだけど、これは「新庁舎建設のために必要な土地」のこと。
もっと具体的に言うと、今は取り壊してなくなっている市民体育館の南側に「新たに取得した土地」のこと、だ。
「事業用地」には新庁舎が建てられるわけだから、「建設予定地」とも書かれている。
さてこの「事業用地」=「建設予定地」。
ここに昔から住んでいた人にはどこかに移転してもらわなければならないので、市から補償が支払われることになった。
これは当然のことで、よく理解できる。
しかしこの「事業用地」=「建設予定地」の『外』の『物件』に対しても補償が支払われているケースがあるらしい。
?? ちょっとわからんゾ。
なぜ「事業用地」『外』の物件(建物)に補償が支払われるんだ?
私の家は市内野田にあって十分「事業用地外」だけれども、この私の家(物件)にも補償が支払われる可能性があった、ってことか!?
しまった!もらい損ねたワイ・・・。
とヒートアップしてしまいそうな頭を冷やしつつ、中日新聞の記事をよっく読んでみると市用地開発課担当の人がこう言っている。
「用地の内外で建物を一体的に利用する場合は補償の対象になり得る。」
「今回のケースは母屋と離れのような関係で住める状態と判断して補償した。」※1
なるほど、母屋と離れ、みたいな関係は「建物を一体的に利用する場合」に相当するわけか。
そして市用地開発課の人の説明の前段ではこう書いてある。
「平屋の建物の所有者は用地内に住居があり、」
(この「所有者」は用地内に住んでるから補償を受ける対象なのだな。)
「平屋でも家族が居住していたとして、市が補償した」※2
(そうか、この「平屋」が、「所有者」の住居を母屋とすると離れに当たるわけか。)
ん? 「平屋の建物」ってなんだ?
新聞記事の最初にこう書いてある。
「建設予定地外にあった『平屋の建物』の所有者に対して市が補償を支払った・・」
あー、そうか。この「平屋の建物」が「離れ」で、「平屋の建物=離れ」が「予定地外」なのか。
ようやく繋がった。なんで最初からよく読まないんだ、オレw
「母屋と離れ」を常識的に解釈すれば、同じ土地に二棟あるパターンとか、同じ土地でなくても狭い道を挟んでの二棟で家族ともども行き交っているとか、そんな感じだろうか。
この所有者さんの家もそんな実態だったのだろう(好意的に解釈)。
「用地内に母屋があり野田に離れがあるので、野田の離れを立て直す費用も補償してほしい!」と言ってもこれは「母屋と離れ」と言うにはあまりに無理スジな話というわけか(笑。
ん? じゃあこの新聞記事まとめるとこんな感じだと思うが・・・
↓
「平屋の建物」は用地外だから、本来は補償の対象ではない。
しかし「母屋と離れ」を適用できるパターンとして、「離れ=平屋の建物」は用地外だけれども補償の対象になった。
一体この記事の何が問題なワケ? なにか見落としてるか?
そこでもう一度記事をよっく読むと、多分これではないかと。
・「平屋でも『家族が居住していた』として」←※2
・「母屋と離れのような関係で『住める状態』と判断して」←※1
・「加藤市議らは平屋の建物の『居住実態』についても争う」←新聞記事最後の段
離れに「家族が住んでいたのか?」、離れが「住める状態であればいいのか?」
というような「居住実態」が重要なカギになっているようだ。
長くなったので続く。
2016年09月30日 Posted by けま at 09:18 │Comments(0) │新庁舎建設
県立高校統合の跡地利用
最近の動きで気になったのはこれ。
https://www.facebook.com/sincityhall/posts/1074042419316471
『「新城希望都市を目指す若者の会」(共同代表、今泉・伊藤)が穂積市長に、統合後の跡地利活用について、新城市の将来にかかわる問題であり、予想外の新たな状況が生まれたのだから、これをチャンスに変え、これまでのいきさつを白紙に戻して、庁舎移転を含めて市民の負担が必要最小限になるように、聖域なき検討をしていただきたいと市民提案をした』
発想としてはよく理解できる。
代表者の方もご自身のfacebookで同じようなケースの紹介もされていて、新城でもできるんじゃないか?とも思う。
(こちら→https://www.facebook.com/yoshitaka.imaizumi.37/posts/832486816887870?pnref=story)
今現在、新庁舎建設で最優先したいことは、
1・なるべく早く完成したい 2・大地震にも耐えられる構造である
であると個人的に思っている。
万が一、大地震が発生してしまったら、その後の私たち市民の生活の立て直しは市職員のみなさんの頑張りに頼る他ない。
その職員さんたちを守る頑丈なハコを、早急に完成させてほしい。
職員さんの命を守ることは、私たち市民の命を守ることと同義と考えていいと思う。
もちろん、だからと言って無駄にデカく、無駄に高価な建物を作っていいものでもない。
この間の住民投票ではこの視点で、不完全ではあるが庁舎の大きさ、建設費の見直しをさせることに一応の成功を収めた。
しかし、「新庁舎見直しに関する実務協議」での市側の不誠実な対応は自分にとって忘れがたい。
この先は『特に建設費に関するお金の動きに十分目を光らせて、新庁舎建設を見守っていきたい』と、個人的にはそう考えている。
というわけで、この「跡地利用」の話、今現在の新庁舎建設に対する私の見方からすると、「庁舎完成が遅れてしまわないか?」という懸念が一番大きい。
「新城希望都市を目指す若者の会」さんは早速請願に向けた署名活動を始めているとのことだが、同時に私のような疑問をもつ市民もいるだろうから、できるだけの説明をしてほしいと思う。
署名活動中に説明はするだろうけど、できたらネット上でも見解を示してもらえればありがたいなぁ。
https://www.facebook.com/sincityhall/posts/1074042419316471
『「新城希望都市を目指す若者の会」(共同代表、今泉・伊藤)が穂積市長に、統合後の跡地利活用について、新城市の将来にかかわる問題であり、予想外の新たな状況が生まれたのだから、これをチャンスに変え、これまでのいきさつを白紙に戻して、庁舎移転を含めて市民の負担が必要最小限になるように、聖域なき検討をしていただきたいと市民提案をした』
発想としてはよく理解できる。
代表者の方もご自身のfacebookで同じようなケースの紹介もされていて、新城でもできるんじゃないか?とも思う。
(こちら→https://www.facebook.com/yoshitaka.imaizumi.37/posts/832486816887870?pnref=story)
今現在、新庁舎建設で最優先したいことは、
1・なるべく早く完成したい 2・大地震にも耐えられる構造である
であると個人的に思っている。
万が一、大地震が発生してしまったら、その後の私たち市民の生活の立て直しは市職員のみなさんの頑張りに頼る他ない。
その職員さんたちを守る頑丈なハコを、早急に完成させてほしい。
職員さんの命を守ることは、私たち市民の命を守ることと同義と考えていいと思う。
もちろん、だからと言って無駄にデカく、無駄に高価な建物を作っていいものでもない。
この間の住民投票ではこの視点で、不完全ではあるが庁舎の大きさ、建設費の見直しをさせることに一応の成功を収めた。
しかし、「新庁舎見直しに関する実務協議」での市側の不誠実な対応は自分にとって忘れがたい。
この先は『特に建設費に関するお金の動きに十分目を光らせて、新庁舎建設を見守っていきたい』と、個人的にはそう考えている。
というわけで、この「跡地利用」の話、今現在の新庁舎建設に対する私の見方からすると、「庁舎完成が遅れてしまわないか?」という懸念が一番大きい。
「新城希望都市を目指す若者の会」さんは早速請願に向けた署名活動を始めているとのことだが、同時に私のような疑問をもつ市民もいるだろうから、できるだけの説明をしてほしいと思う。
署名活動中に説明はするだろうけど、できたらネット上でも見解を示してもらえればありがたいなぁ。
2016年08月19日 Posted by けま at 11:30 │Comments(0) │新庁舎建設│新城市高校統合
新庁舎見直し基本設計案説明会
今日、新庁舎見直し基本設計案説明会が開催される。
リコール署名運動が行われていている中、現市長が辞任ともなればこの設計案も大きく見直しされるのだろうが、
リコールならなければこの設計案のまま突き進むのだろう。
などと思うとなんだかどうでもいいやという気分にもなってしまうが、市内有権者全員に配られた「新城市新庁舎見直し基本設計案 概要版」を眺めて気になったところを書いてみよう。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,32417,c,html/32417/20130530-103743.pdf
こちら2013年6月の「ほのか」。
この最後のページに「新庁舎建設事業の財源計画の例」の図が載っている。
この棒グラフの「庁舎等建設基金 1511」、「一般財源 166」(単位:百万円)。
一方「概要版」、「頭金(庁舎等建設基金活用) 589」、「市負担分1023.3」(単位:百万円)。
(*比較しやすいように単位を揃えました。)
頭金の庁舎等建設基金が減ってますが、なぜ?
代わりに一般財源からの負担が大きく増えてますが、これもなぜ?
私今日、仕事で参加できないのですが、どなたか質問してくれないかしら?
(住民投票のときの説明パンフでのC用地の費用に充てたのかね?)
リコール署名運動が行われていている中、現市長が辞任ともなればこの設計案も大きく見直しされるのだろうが、
リコールならなければこの設計案のまま突き進むのだろう。
などと思うとなんだかどうでもいいやという気分にもなってしまうが、市内有権者全員に配られた「新城市新庁舎見直し基本設計案 概要版」を眺めて気になったところを書いてみよう。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,32417,c,html/32417/20130530-103743.pdf
こちら2013年6月の「ほのか」。
この最後のページに「新庁舎建設事業の財源計画の例」の図が載っている。
この棒グラフの「庁舎等建設基金 1511」、「一般財源 166」(単位:百万円)。
一方「概要版」、「頭金(庁舎等建設基金活用) 589」、「市負担分1023.3」(単位:百万円)。
(*比較しやすいように単位を揃えました。)
頭金の庁舎等建設基金が減ってますが、なぜ?
代わりに一般財源からの負担が大きく増えてますが、これもなぜ?
私今日、仕事で参加できないのですが、どなたか質問してくれないかしら?
(住民投票のときの説明パンフでのC用地の費用に充てたのかね?)
2016年01月16日 Posted by けま at 07:14 │Comments(0) │新庁舎建設
権利を行使しているだけ
市長のブログ、久々に更新されたなぁと思っていたらまさかの2日連続更新。
そしてこの2日目の記事がなかなか香ばしい。
山の舟歌・第3章(新城市長ブログ)
2016年01月05日「人の批判は簡単」、ではない話(甘え型リコール論)
→http://tomako.dosugoi.net/e828543.html
リコール運動の主体は求める会なので、求める会に対して「甘え型リコール」と言っているのだろう。
求める会のみなさんも地方公共団体の住民であり、リコールは地方自治法で認められている地方公共団体住民の権利だ。
新城市住民がその権利を、手続きに則って粛々と遂行している。ただそれだけのことだ。
それに対して「甘え型」とかいう批判をしているのが現市長だ。
先にも書いた通り「求める会」に対して個別に批判しているのだろうし、署名する市民もその同類だと批判しているのだろう。
批判されればなんとなく「署名しちゃマズイかな・・・」なんて思う市民もいるかもしれない。
なんせ市議会議員さんからも、市民自治関連でアドバイスいただいている学識経験者の方からも「人の悪口を言わない」と評されている現市長だ。
その市長の、この怒りと敵愾心に満ちた記事を読めばなおさらだ。
そういう風に思わせるのが市長の策略だろう。
結果的に市民の権利の行使を妨害しているということに気づかないのだろうか。
この日の市長の記事に、
「何よりも批判者自身の思考や人格がもろに露呈して、批判の刃は必ず自分にも向いてきます。」
と書いてある。
そのまま市長にお返ししよう。
市民自治を謳う市長が、市民自治に基づく権利の行使を妨害しているのだ。
そしてこの2日目の記事がなかなか香ばしい。
山の舟歌・第3章(新城市長ブログ)
2016年01月05日「人の批判は簡単」、ではない話(甘え型リコール論)
→http://tomako.dosugoi.net/e828543.html
リコール運動の主体は求める会なので、求める会に対して「甘え型リコール」と言っているのだろう。
求める会のみなさんも地方公共団体の住民であり、リコールは地方自治法で認められている地方公共団体住民の権利だ。
新城市住民がその権利を、手続きに則って粛々と遂行している。ただそれだけのことだ。
それに対して「甘え型」とかいう批判をしているのが現市長だ。
先にも書いた通り「求める会」に対して個別に批判しているのだろうし、署名する市民もその同類だと批判しているのだろう。
批判されればなんとなく「署名しちゃマズイかな・・・」なんて思う市民もいるかもしれない。
なんせ市議会議員さんからも、市民自治関連でアドバイスいただいている学識経験者の方からも「人の悪口を言わない」と評されている現市長だ。
その市長の、この怒りと敵愾心に満ちた記事を読めばなおさらだ。
そういう風に思わせるのが市長の策略だろう。
結果的に市民の権利の行使を妨害しているということに気づかないのだろうか。
この日の市長の記事に、
「何よりも批判者自身の思考や人格がもろに露呈して、批判の刃は必ず自分にも向いてきます。」
と書いてある。
そのまま市長にお返ししよう。
市民自治を謳う市長が、市民自治に基づく権利の行使を妨害しているのだ。